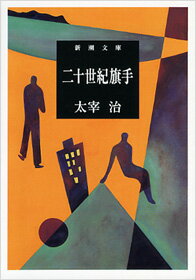太宰の短編『創生記――愛ハ惜シミナク奪ウ。』読了。
冒頭、石坂洋二郎の悪口から始まり、
最後の佐藤春夫とのエピソードまで続く
何の脈絡もないイメージ、ことばの羅列は、
一見狂気じみているようにも見えるが、
これは寧ろ「表層的な狂気」とでも言うべきものだろう。
「表層」と「狂気」といえば僕などは
ドゥルーズによるキャロル像(『意味の論理学』及び『批評と臨床』ほか)を
連想するが、
勿論、太宰は太宰であり、断じてキャロルではない。
ルイス・キャロルからストア派へ、パラドックスの考察にはじまり、意味と無意味、表面と深層、アイオーンとクロノス、そして「出来事」とはなにかを問うかつてなかった哲学。『差異と反復』から『アンチ・オイディプス』への飛躍を画し、核心的主題にあふれたドゥルーズの代表作を、気鋭の哲学者が新訳。
出来事とは何か。そして意味とは何か。アイオーンとクロノス、表面と深層、意味と無意味の探求の果てに、ストア哲学がよみがえる。下巻には「トゥルニエ論」「ルクレティウス論」などの重要テクストも収録。
文学とは錯乱/健康の企てであり、その役割は来たるべき民衆=人民を創造することなのだ。「神の裁き」から生を解き放つため極限の思考。ドゥルーズの思考の到達点を示す生前最後の著書にして不滅の名著。
一個の文学作品として寧ろここで問題となるのは、
内容的には(薬物中毒に因る)全く脈絡のない文章にも拘らず、
読者の目をつかんで離そうとしない、その講談調とも言えそうな饒舌体だろう。
僕はここで「読む」ということと「聴く」ということの関連性を考える。
「読む」ことはそのまま、脳内で、「聴く」ことに変換される。
ヒトはそれによって書物や文書を理解する。
鳥や獣がそうであるように、ヒトもまた、
(注意喚起としての)音声を「聴く」ことによって身体を反応させる。
つまり音声とは或る領土を示す符号であり、
ヒトは路肩の看板を見るように、それによって判断する。
例えば常に鳴り響いているサイレンなどがあれば、
ヒトはそれに耳を傾けざるを得ないだろう。
本作での太宰の語りはそのような種のものであり、
一般的な意味での「狂気」とはまるで別物なのだ。
「読む」ことは「聴く」ことである。
或るモノローグを「読む」ことは、
その人(ケモノでもいいが)の声を「聴く」こと、
その人の領土に触れることである。
繰り返されるサイレンの音は、カナリアの泣き声にも似て、
ヒトを常に警戒させる。
太宰はちょうど本作を書いたころに
井伏など周囲の人びとによって精神科に入院させられているが、
まさに太宰の声こそが、人びとをしてそうさせたのだろう。
なんとも痛ましいことである。