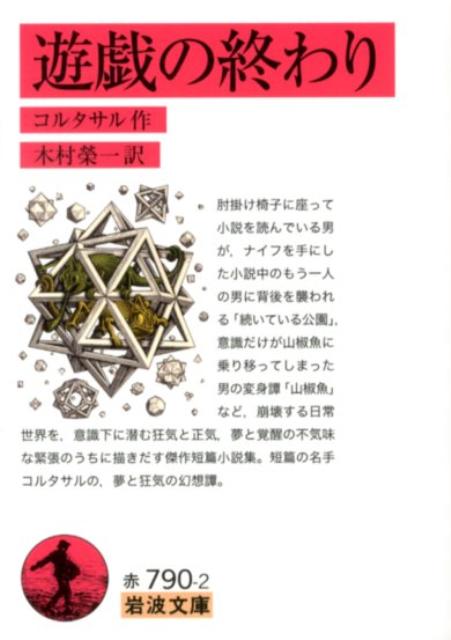コルタサルの短編『殺虫剤』読了。
自宅の庭に蟻の巨大な巣穴があることが分かり、
叔父が奇妙な機械と薬剤をもって退治に来ることになる。
語り手の少年(カウボーイの物語に憧れている)はそれを手伝うが、
巣穴は隣家にも広がっているようでひと騒動になる。
アルゼンチンの地方部を舞台に多感な少年の失恋を描いているのだが、
コルタサルにしては意外とも言えるほどにオーソドックスな小説で、
なにかR.カーヴァーあたりの小説を読んでいるような錯覚に陥る。
蟻退治の奇妙な機械が出て来なければ、
「カーヴァーの作品だ」と言われてもそのまま信じてしまいそうである。
トリッキーな作風の印象があるコルタサルにも、
こんな作品があるのかという、ある種新鮮な驚きを感じる。