柴宜弘さんの『ユーゴスラヴィア現代史』を読み終えた。
- ユーゴスラヴィア現代史 (岩波新書)/岩波書店

- ¥842
- Amazon.co.jp
約10年ほど前、イラク戦争が終わったころから、
僕は90年代に悲惨な内戦が繰り広げられた
ボスニア・ヘルツェゴビナに関心を持つようになり、
それ以来、本や映画など、色々な文物を渉猟している。
古代から様々な民族や信仰が行きかい、
多様なアイデンティティーを持つ人々が混住、
独自な文化を形成してきたボスニアでの内戦は、
最近のウクライナ情勢やアフリカ中東情勢も含めた
冷戦終結後の地域紛争や対立のひな形と言ってよく、
その意味でボスニアを含めた旧ユーゴ連邦が
内戦から解体へと至った経緯を点検することは重要だと思う。
以前にも書いたかもしれないが、
そもそも旧ユーゴ地域は歴史的に東西文化の十字路で、
「七つの国境、六つの共和国、五つの民族、四つの言語、
三つの宗教、二つの文字、ひとつの国家」とも言われたように
様々な民族や信仰を持つ人々が
地理的にも民族的にも複雑に入り混じって居住していて、
それらの人々が程よく共生してきた。
しかし西欧を中心に各地で民族意識が高まってきた19世紀以降、
「バルカンの火薬庫」と言われるまでに緊張が高まり、
1914年6月28日には
当時のオーストリア=ハンガリー帝国皇太子が
セルビア民族主義者の青年G.プリンツィプに暗殺されたことによって、
第一次世界大戦へと発展するまでに至ってしまう。
第二次大戦では実質的にナチス・ドイツの支配下に置かれるが、
共産主義者を中心にしたパルチザンの活躍によって自力解放、
戦後は共産主義国家が作られることになる。
しかしカリスマ的元首ヨJ.ティトーとソ連のスターリンとの対立から
旧ユーゴは他の東欧諸国と違い共産主義国家としても
「自主管理社会主義」という独自の路線を歩むことになった。
カリスマ・ティトーの下、
「自主管理社会主義」の理念に基づく連邦制の中で
社会主義国家としては異例の経済発展を遂げた旧ユーゴだが、
1980年のティトーの死後は債務の拡大や民族主義の高まりなどから
次第に崩壊への道を辿っていくことになる。
各民族・宗教の代表者でもあった政治家たちが自分たちの利益のみを
主張し合うようになり、
その事がひいては「兄弟殺し」「家族殺し」とまで言われた対立や紛争、
挙句には苛酷な民族浄化にまでつながっていってしまった。
ボスニアでの民族浄化はすさまじく、
捕虜となった男性は悉く殺害、女性は強姦された上に出産を強制され、
互いに互いの民族的な「純粋さ」を消すことに労力が注がれたらしい。
例えば映画『サラエボの花』では、
内戦中こうした民族浄化にあったムスリム女性と娘の姿を通して、
ボスニアの人々の中に今も残る内戦の深い傷を描き出している。
- サラエボの花 [DVD]/アルバトロス
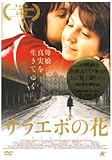
- ¥5,184
- Amazon.co.jp
内戦中こうした戦争犯罪は
実際にはセルビア、クロアチア、ムスリムのどの勢力も行なっていたが、
ボスニア地域に常駐の報道網を持たず、
主に欧米の報道に頼っていた当時(今も?)の日本では
欧米のメディアや政府に倣ってセルビア人勢力を悪役にする
「セルビア悪玉論」が横行していたような気がする。
ボスニア内戦の当時、僕はまだ中学生で、
内戦の背景とか詳しい経緯とかは知る由もなかったが、
TVや新聞の報道からはなんとなくそんな雰囲気があることを
肌で感じていた。
現地では実際にはそうした「セルビア悪玉論」が
セルビア人勢力の孤立化、反発を生み、
逆に紛争の長期化や暴力性を増大させた面があったようだ。
日本とバルカンという物理的な距離、政治的経済的利害の無さも、
日本人に紛争を他人事として捉えさせる大きな要因だったろう。
しかし、紛争終結後にはむしろそうした距離にこそ、
主に人道支援において日本が果たすべき役割の中で
有益性、重要性がある(96年初版の本なので)と、柴さんも書いている。
この事はボスニアに限らず、
また、集団的自衛権の名の下で軍事的支援の重要性のみが
取りざたされる昨今の日本で、
最も注目されるべき点じゃないかと思う。
柴さんはさらに、
上のように日本が果たすべき役割の重要性を書いた終章の中で、
ボスニア内戦の過程で「民族」という概念の果たした役割について
振り返りながら、
現在、国際社会の常識のように捉えられている「民族自決」という
概念の再考をも促している。
「民族自決」は第一次大戦以降の国際秩序を考える上では
極めて重要な考え方だが、
ボスニア(東欧)や中東、アフリカのように歴史的な背景から
複数の民族、信仰が混在している地域では、
逆に対立や紛争の火種になっている現実があり、
「民族」というものだけに人間の帰属意識を求めることの危うさは
非常に高いと思うし、
既存の制度、概念を十分に生かしつつ、
平和へ向けた新たな考え方を創り出していくことこそ、
今を生きる僕らの最優先の課題なんじゃないかと思う。