ドキュメンタリー映画『革命の子どもたち』を観た。
革命の子どもたち
http://www.u-picc.com/kakumeinokodomo/index.html
1968年と言えば革命の年である。
フランスではパリを中心に5月革命が起こり、
英米では学生運動やベトナム反戦運動が盛り上がりを見せ、
社会主義体制下のチェコ・プラハでは
「人間の顔をした社会主義」を求めた人々が
体制に異議申立てをしていた。
そうした中で日独両国ではふたつのグループが
誕生しようとしていた。
よど号事件を起こした赤軍派を抑々の母体とした日本赤軍と
バーダー・マインホフ・グルッペとも呼ばれたドイツ赤軍。
ともに国際的なテロ組織として知られたグループで、
映画ではそれぞれを象徴するような存在だった
重信房子被告とウルリケ・マインホフの半生を、
娘の重信メイさんとベティーナ・ロールさんら
関係者の目を通して描き出すとともに、
そうした母親の元に生まれたがゆえに、
特異な半生を歩まざるを得なかった娘たちをも
強く逆照射している。
そして、作品的には、むしろこちらの方が主眼なのだ
(だからタイトルが『革命の子どもたち』なんで)。
当たり前のことだが、人は誰しも、
生まれる環境を選ぶことができない。
貧乏な家庭に生まれればそれなりの暮らしに甘んじざるを得ず、
裕福な家であれば余裕のある暮らしができる。
少なくとも「自由」が立て前であるはずのこの国でさえ、
それが現実だろう。
60年代の若者たちがそうした現実の矛盾に対して抱いた
怒り、違和感は、僕も大いに共感するところがある。
が、今日から見れば、彼ら(日本・ドイツ両赤軍)がとった、
他人の生命や生活を武力の犠牲にしてでも
自らの正義を貫こうとする手法は、
やはり間違いだったと言わざるを得ないだろうし、
そのことは、今日ではメイさんやベティーナさんのみならず、
重信被告本人も認めているようだし、
ウルリケ・マインホフも、娘のベティーナさんによれば、
生前逮捕後に同様の主旨の発言をしていたという
(ウルリケは1976年獄中で自死したとされる。
なお、ウルリケやドイツ赤軍については
以前、哲学者の國分功一郎さんも紹介していた映画
『バーダー・マインホフ 理想の果てに』でおおよそのことは
分かると思う)。
バーダー・マインホフ 理想の果てに [DVD]/Happinet(SB)(D)
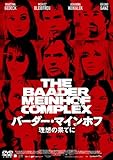
¥4,104
Amazon.co.jp
2001年9月11日のテロとそれに続くアフガニスタン戦争、
あるいはイラク戦争などにも見られるように、
あらゆる戦争行為は「正義」の名の下に行なわれてきた。
例えそれがいかなる「正義」であれ、
その名の下で行われるすべての行為は「正しい」のか、
この映画はそうした問いを突き付けてくる。
例え信念は正しくとも、
それを実行するための手法が間違っていれば、
やはりその信念も正しくないことにされてしまうし、
作品中でメイさんも言うように、
パレスティナ闘争に参加する「解放戦士」たちが
テロの他にこの問題を世界に周知する手段を持ってなかった
当時と違って、今ではSNSなど、多くの手段があるし、
より他者を傷つけずに信念を貫く手法はいくらでもあるのだ
(そもそも国家の巨大な軍事力に武力で対抗するというなら、
我々は皆核兵器を常備しなければならないことになる)。
もちろん、圧制に対する抵抗権は誰しもに備わっている。
が、抵抗とはあくまでもその場限りのものであり、
抵抗が一般的な意味での権力に変質した時点で、
それはもう抵抗ではないのではないかと思う。
そうしたことが、同じように特異な環境に育ちながら、
例えばメイさんとベティーナさんの間にある、
母親に対する微妙な距離感の違いを生んでるような気がする。
さらにいろんなことを考えさせてくれたのは、
やはり重信メイさんの半生についての、
本人や関係者たちの語りだろう。
「テロリスト」の娘として生まれたがゆえに、
28年間国籍を持てなかった彼女は、
行く先々で自分の本当の身分を隠して生きねばならず、
そのため幼年時代の彼女は常に
アイデンティティーの不安に襲われていたといえるだろう。
戸籍など法的な文書を除けば、
人は自他の記憶によってのみ、
己が己であるという確証を得ることができる。
だからこそ記憶障害に陥った重度の認知症の人などは
強い不安に襲われるのだろうし、認知症の諸症状は、
根本的にはそうした強い不安を苗床にしてると思う。
そうした中でメイさんを救ってくれたのはやはり、
母親である重信被告やその同志たちアラブの人々の、
日常性への感覚だろう。
政治的主張は政治的主張として、日常の生活、
個々の権利とは切り離して考えていた彼らの思想は、
その意味ではやはり徹底して自由を希求していたと
言えるような気がするし、
メイさんとベティーナさんの母親への感覚、距離感の違いは、
やはりそこにあると思う。
言い換えればこれは、自分という主体の形成を、
どれだけ自由な環境で行なえるかということ、
人生の選択をどれだけ自分の意志として為し得、
それを自分の信念にまで高め得るかということと
深く関わってくるように思えるし、
母親を含めた他者への尊敬の感情は、
やはりそういうところにしか根差し得ないことの、
ひとつの証であるような気がする。
革命の子どもたち
http://www.u-picc.com/kakumeinokodomo/index.html
1968年と言えば革命の年である。
フランスではパリを中心に5月革命が起こり、
英米では学生運動やベトナム反戦運動が盛り上がりを見せ、
社会主義体制下のチェコ・プラハでは
「人間の顔をした社会主義」を求めた人々が
体制に異議申立てをしていた。
そうした中で日独両国ではふたつのグループが
誕生しようとしていた。
よど号事件を起こした赤軍派を抑々の母体とした日本赤軍と
バーダー・マインホフ・グルッペとも呼ばれたドイツ赤軍。
ともに国際的なテロ組織として知られたグループで、
映画ではそれぞれを象徴するような存在だった
重信房子被告とウルリケ・マインホフの半生を、
娘の重信メイさんとベティーナ・ロールさんら
関係者の目を通して描き出すとともに、
そうした母親の元に生まれたがゆえに、
特異な半生を歩まざるを得なかった娘たちをも
強く逆照射している。
そして、作品的には、むしろこちらの方が主眼なのだ
(だからタイトルが『革命の子どもたち』なんで)。
当たり前のことだが、人は誰しも、
生まれる環境を選ぶことができない。
貧乏な家庭に生まれればそれなりの暮らしに甘んじざるを得ず、
裕福な家であれば余裕のある暮らしができる。
少なくとも「自由」が立て前であるはずのこの国でさえ、
それが現実だろう。
60年代の若者たちがそうした現実の矛盾に対して抱いた
怒り、違和感は、僕も大いに共感するところがある。
が、今日から見れば、彼ら(日本・ドイツ両赤軍)がとった、
他人の生命や生活を武力の犠牲にしてでも
自らの正義を貫こうとする手法は、
やはり間違いだったと言わざるを得ないだろうし、
そのことは、今日ではメイさんやベティーナさんのみならず、
重信被告本人も認めているようだし、
ウルリケ・マインホフも、娘のベティーナさんによれば、
生前逮捕後に同様の主旨の発言をしていたという
(ウルリケは1976年獄中で自死したとされる。
なお、ウルリケやドイツ赤軍については
以前、哲学者の國分功一郎さんも紹介していた映画
『バーダー・マインホフ 理想の果てに』でおおよそのことは
分かると思う)。
バーダー・マインホフ 理想の果てに [DVD]/Happinet(SB)(D)
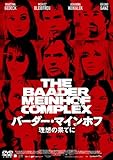
¥4,104
Amazon.co.jp
2001年9月11日のテロとそれに続くアフガニスタン戦争、
あるいはイラク戦争などにも見られるように、
あらゆる戦争行為は「正義」の名の下に行なわれてきた。
例えそれがいかなる「正義」であれ、
その名の下で行われるすべての行為は「正しい」のか、
この映画はそうした問いを突き付けてくる。
例え信念は正しくとも、
それを実行するための手法が間違っていれば、
やはりその信念も正しくないことにされてしまうし、
作品中でメイさんも言うように、
パレスティナ闘争に参加する「解放戦士」たちが
テロの他にこの問題を世界に周知する手段を持ってなかった
当時と違って、今ではSNSなど、多くの手段があるし、
より他者を傷つけずに信念を貫く手法はいくらでもあるのだ
(そもそも国家の巨大な軍事力に武力で対抗するというなら、
我々は皆核兵器を常備しなければならないことになる)。
もちろん、圧制に対する抵抗権は誰しもに備わっている。
が、抵抗とはあくまでもその場限りのものであり、
抵抗が一般的な意味での権力に変質した時点で、
それはもう抵抗ではないのではないかと思う。
そうしたことが、同じように特異な環境に育ちながら、
例えばメイさんとベティーナさんの間にある、
母親に対する微妙な距離感の違いを生んでるような気がする。
さらにいろんなことを考えさせてくれたのは、
やはり重信メイさんの半生についての、
本人や関係者たちの語りだろう。
「テロリスト」の娘として生まれたがゆえに、
28年間国籍を持てなかった彼女は、
行く先々で自分の本当の身分を隠して生きねばならず、
そのため幼年時代の彼女は常に
アイデンティティーの不安に襲われていたといえるだろう。
戸籍など法的な文書を除けば、
人は自他の記憶によってのみ、
己が己であるという確証を得ることができる。
だからこそ記憶障害に陥った重度の認知症の人などは
強い不安に襲われるのだろうし、認知症の諸症状は、
根本的にはそうした強い不安を苗床にしてると思う。
そうした中でメイさんを救ってくれたのはやはり、
母親である重信被告やその同志たちアラブの人々の、
日常性への感覚だろう。
政治的主張は政治的主張として、日常の生活、
個々の権利とは切り離して考えていた彼らの思想は、
その意味ではやはり徹底して自由を希求していたと
言えるような気がするし、
メイさんとベティーナさんの母親への感覚、距離感の違いは、
やはりそこにあると思う。
言い換えればこれは、自分という主体の形成を、
どれだけ自由な環境で行なえるかということ、
人生の選択をどれだけ自分の意志として為し得、
それを自分の信念にまで高め得るかということと
深く関わってくるように思えるし、
母親を含めた他者への尊敬の感情は、
やはりそういうところにしか根差し得ないことの、
ひとつの証であるような気がする。