伊丹十三監督の映画『スーパーの女』を見た。
- 伊丹十三DVDコレクション スーパーの女/ジェネオン エンタテインメント
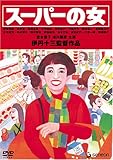
- ¥5,076
- Amazon.co.jp
食の安全への疑念が言われるようになって久しい。
2000年の雪印集団食中毒事件 以降ゼロ年代前半から、
「ささやき女将」で話題になった船場吉兆や
昨年話題になったホテルやレストランでの食材偽装など、
食の安全を脅かす事件は絶え間なく発覚してるし、
また最近ではTPPとの絡みもあって
大企業による遺伝子組み換え食品の安全性にも
疑念が呈されている。
「生き馬の目を抜く」とも言われる資本主義。
食もまたそうした制度の構造上の問題に左右されてるとも
言えると思うが、
この映画のすごいところは
一連の食品偽装、産地偽装が今みたいに話題になる前に
取り上げたことの先見性もさることながら、
伊丹監督独特のユーモアでもって
娯楽性の高い作品に仕上がってることだろう。
考えてみれば「パンとサーカス」と言われたローマの昔から、
庶民は娯楽を求めてきた。
ローマはそれを充実させることによって皮肉にも滅亡したが、
見方を変えれば、このふたつがしっかりしてさえいれば、
庶民というか民衆は安泰だということでもある(政府は知らない)。
これは政治を見る「まなざし」に関しても言えることだろう。
K.マルクスは「宗教は民衆のアヘンである」と言ったというが、
僕は「娯楽(エンターテイメント)は民衆のアヘン」だと考えている。
アヘンと言うと何か悪いものというイメージが先行するが、
マルクスが生きてた当時、アヘンは鎮痛剤としても使われてたし、
現在でもモルヒネは癌の鎮痛薬として使われている。
一方この映画では「職人」と「素人」という言葉が多用される。
同じく伊丹監督の名作『タンポポ』には
素人が分らないようなラーメン作ってどうするの?
という名台詞があるが、ラーメンを映画や政治に置き代えれば、
この言葉はそのまま通用してしまうようにも思える。
昨日見た『民主主義を求めて』では丸山眞男の言葉として、
「民主主義というのは職業政治家じゃない人たちがパートタイムで
政治参加する制度」というのがあったが、
伊丹映画における「職人(プロ)」と「素人」の対比は、
まさにこうした民主主義観と通底するものでもあると思う。
食の安全にしても政治にしても、
政策の如何によってその在り様が決まっていく点では同じだし、
非職業的な「素人」(=消費者、有権者)が監視、関与することで
補完されるという点では同じである。
顔のない民衆が、社会正義などではなく、まさに自己防衛的に、
監視、関与していくことでこそ、
食の安全も政治も、よりよいものになってくんじゃないかと思う。