昨年10月に急逝した
若松孝二監督の遺作となった映画『千年の愉楽』を観た。
- 千年の愉楽 [DVD]/アミューズソフトエンタテインメント

- ¥5,076
- Amazon.co.jp
原作は中上健次。
「路地」と呼ばれる被差別部落に生まれ、
「高貴にして汚れた血」を伝える中本の一族の物語を、
彼らをその手で取り上げたオリュウノオバの語りを通して
紡いでいく物語。
中上が原作の映画を見るのはこれが2本目になる。
1本目は『軽蔑 』で、映画としてはそれなりに面白かった。
原作も、四方田犬彦さんの解説目当てに買ったが、
本編はまだ読んでいない。
正直に言ってしまえば、
僕は中上の小説をあまり好きになれない。
高校の時、
芥川賞受賞作の『岬』が入ってる短編集を図書室で借りたが、
最初の『十九歳の地図』だったかの冒頭を読んで
すでに読む気を失くしていた。
文体が好きになれないのだ。
その後読み始めたW.フォークナーは割と好きで、
今でも短編集や長編をちびちびと読んでいる。
まあ間に翻訳者を挟んでいるから、
翻訳者の感性とたまたま相性が良かったのだろうと思う。
しかしそれにしても
中上健次はどうしてこうも神格化されるのだろう。
映画界でも、
例えば青山真治監督などは中上フリークとして知られるし、
文学界では柄谷行人など多くの作家・評論家が
リスペクトを表明している。
確かに、中上の遺した文学的業績、
その重厚なテーマ性はもっと多くの現代日本文学が
取り組まねばならないものだと思うし、
その文学史的意義は決して小さくはないと思う。
しかし、それにしても、
みんな中上に頼りすぎじゃないだろうか?
僕は中上よりは『月山』の森敦なんかのほうが断然好きだ。
- 月山・鳥海山 (文春文庫 も 2-1)/文藝春秋
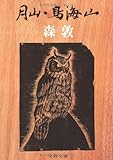
- ¥627
- Amazon.co.jp
中上と森敦を比べるのもおかしな話だろうが、
そこには細部を聞き取ろうとする耳があるように思える。
言い換えれば、僕の中で中上健次という作家は、
大味な印象があるんだろうと思う。
人間中心的と言ってもいいかもしれない。
長々と中上の文句を垂れてきたが、
言いたいことは要はこれだと思う。
中上健次の人間中心性。
紀州という風土を書く以上、そこには人間だけでなく、
もっと紀州の気候や自然、
例えば南方熊楠が研究した粘菌のような自然が、
もっと反映されてしかるべきじゃないかと、
僕なんかは思ってしまうのだ。
僕は原作を読んではいないから、
この映画がどこまで原作を反映してるのかは知らない。
けど、もしこの映画が原作に忠実に作られてるのだとすれば、
まさしくその点は批判されて然るべきじゃないかと思う。
ともあれ映画自体は悪くなかったし、
若松監督がなぜこれを映画にしたかったのか、
という部分でも興味はわいてくる。
そういった部分も、ちょっと考えてみたいとは思う。