えんじゅです。
一昨日は友人2人とカラオケしてきました(*^▽^*)
3人ともCoccoファンで、Coccoさんの歌を歌いまくってきました。
楽しかったなぁ~♪
それはさておき、
最近は山形県出身の文芸評論家、加藤典洋さんの『敗戦後論』を
ぽつぽつと拾い読みしてます。
- 敗戦後論 (ちくま文庫)/筑摩書房

- ¥998
- Amazon.co.jp
高校のときにはじめて読んで目からウロコの思いだった本で、
日本人にとっての「戦後責任」とは何か、
最近の尖閣・竹島問題にも通ずる歴史的政治的な問題について
深く考えさせられますが、
震災後の今、この本を読んでると、
改めてその意義が大きいことを痛切に感じます。
領土をめぐって日中韓の関係がこじれ、
政治がねじれ現象によって迷走、被災地には置き去りの感が広がり、
憤りと諦めが蔓延してる今だからこそ、なお。
この本で加藤さんは、
敗戦を契機に戦前と戦後の間に横たわる「ねじれ」について書き、
日本の戦後政治がこの「ねじれ」を忘却してきたと書きます。
一番わかりやすいのが靖国神社をめぐる評価ですが、
右派はこれを無条件に肯定し、左派は無条件に否定する――
そういった政治的膠着が憲法でも何でも、
50年(この本は97年初刊なので)に亘って続いてきたわけですが、
そういった現象は実は一つの物差しの両端を
別々に指差してるだけに過ぎず、
本当の問題はこの物差自体(「ねじれ」)にあるのではないかといいます
(加藤さんは「ジキル」と「ハイド」の「人格分裂」とも書いてます)。
この指摘は現在の政治社会状況においても指摘しうる、
重要なものだと思います。
現憲法について「押し付け憲法」論というものがありますが、
この憲法が完全にアメリカの占領軍の発意に基づくものではなく、
哲学者で明治期の自由民権運動の研究者でもあった鈴木安蔵らの
「憲法研究会 」による提言を下敷きにしたものであるにせよ、
その成立過程で、ひとつの巨大な軍事力(原爆)を背景に
「押し付けられた」側面があることは否定できませんし、
また震災後顕著になった原発をめぐる議論にしても、
戦後の言論の「伝統」を引きずってるように僕には思えます。
こうした「ねじれ」の感覚に自覚的であったのが、
憲法学者の美濃部達吉や思想史家の津田左右吉、
そして中野重治や太宰治、大岡昇平といった作家たちだったと、
加藤さんは書いています。
戦前戦中は軍国一辺倒だった世相が敗戦とともに掌を返したように
「民主主義」一辺倒になったことに、
彼らはこの「ねじれ」の感覚の下に抗ったといいます。
それはフーコー言うところの「パレーシア」、
つまり自らの生命を賭して(自らの)真理を語る勇気を持つことに
相当するのではなかったかと思います。
翻って震災後の現在の日本を見るとき、
こういった感覚を堅持してる人がいったいどれだけいるのかと、
僕などは思ってしまいます。
震災、原発事故を契機として、
社会は雰囲気的には原発に反対する感じにはなっていますが、
震災前にこのことを真剣に考え、反対していた人たちは、
いったいどれだけいるのでしょうか。
戦後の社会の中で原発がなぜ必要とされてきたのか、
エネルギー政策的な側面だけでなく、経済的、安全保障的な側面から
きちんと考えない限り、原発は永久になくならないでしょう。
そのことを忘れて興味本位で賛成だの反対だのと言う人が、
(ネットなどを見てると特に)多いような気がします。
敗戦によってこの国に「ねじれ」が生じたように、
震災によってもまた、この国は「ねじれ」を背負ったと思います。
戦争も震災関連被害も、
社会の無関心とスノビズム(俗物根性)を糧に肥大してきたという
点では、人災も天災もなく、共通してると思うからです。
津波はたしかに多くのものを流し、
また原発事故は多くのものを福島の人たちから奪っていきました。
しかし、
そのことは被災者や日本人がまっさらな状態になったということでは
決してありません。
日本中でいまだに電気は大量に使われてますし、
被災した人たちは依然として震災前からの連続性、
つまり、地域や経済上のつながり、しがらみのなかで生きています。
そのことを抜きに賛成も反対も、
本来、言えないはずではないでしょうか。
“YES”か“NO”かを問われることは
残酷だという事を知ってほしい。
- 想い事。 (幻冬舎文庫)/幻冬舎
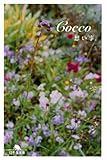
- ¥560
- Amazon.co.jp
このブログでは何度も引用してる、
沖縄の米軍基地に関してのCoccoさんの発言ですが、
基地も原発も、何の根拠もなくそこにあるのではなく、
それらをなくしていくためには、
政治的で不毛な対立とは別の、
また違った総合的な根拠が必要なのではないでしょうか。
その意味で今こそ私たちは戦前/戦後、震災前/後の「ねじれ」に、
きちんと向き合うべきではないかと思います。