えんじゅです。
連日報道されてる尼崎の遺体遺棄事件。
残虐非道な手口や
角田美代子被告や瑠衣被告の生い立ちや犯行にいたる背景など、
少しずつ、いろんな側面から明らかにされてきてると思いますが、
報道を見ていて連想するのは、
60~70年代に相次いで行われた社会心理学上の実験群でしょうか。
どちらも心理学でいう「役割期待」、「規範」への服従を扱った実験で、
ナチスドイツの「ホロコースト」(ユダヤ人大虐殺)を検証する目的で
行われたものです。
ひとつは、スタンレー・ミルグラムによって行われた実験、
通称「アイヒマン実験 」(1961)です。
「アイヒマン」というのはナチスドイツの将校で
ユダヤ人の強制収容所への移送の最高責任者だった
アドルフ・アイヒマンのことで、
戦後アルゼンチンに逃亡していたのを
1960年にイスラエルの諜報機関が連れ戻し、
イスラエルで行われた裁判を経て翌年絞首刑に処されています。
ミルグラムはこの裁判の過程で明らかにされたアイヒマンの行動に
象徴的に見られる、
「ホロコースト」に関わったナチス将校たちの行動の理由を
明らかにするために、
この実験を考えたとされています。
- 現代心理学への招待/ミネルヴァ書房

- ¥3,150
- Amazon.co.jp
- 服従の心理/河出書房新社

- ¥3,360
- Amazon.co.jp
この実験で驚くべきは、被験者40人中の26人までが、
事前に大学生が行った予想(75%が150Vで止めると考えた)に反して、
実験で定められた最大電圧(450V)まで上げたということでしょうか。
ひとつの閉鎖された状況を与えられると、
疑問や責任回避の姿勢は抱きながらも、
人は容易に権威者に従ってしまうということのよい証左でしょう。
もうひとつ連想するのは、このミルグラムの実験を受けて行われた、
フィリップ・ジンバルドーの「スタンフォード監獄実験 」(1971)です。
新聞で募集した被験者十数人を
スタンフォード大学構内に設けた模擬監獄に入れ、
コイン投げによって囚人役と看守役にそれぞれ分け、
2週間にわたってその様子を観察するというものでしたが、
看守役の行動が次第にエスカレートしあろうことかジンバルドー自身も
その状況に心理的に飲みこまれてしまったため、
外部の通報によって実験は中止に追い込まれます。
この実験は映画『es』の元ネタにもなったので
ご覧になった方もいるかと思いますが、
注目すべきはやはり、
状況そのものがその内部にいる人間にそれぞれの役割を期待し、
また状況に拘束された人間(特に看守役と実験者)のほうでも、
期待された役割を積極的に果たして行こうとするメンタリティーを
作り上げてしまうということでしょう。
- es[エス] [DVD]/ポニーキャニオン
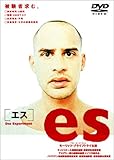
- ¥3,990
- Amazon.co.jp
今回の事件では瑠衣被告を始め角田被告に付き従った人たちが
これらの実験の教師役や看守役を演じた被験者に相当していたと、
おそらく言えるでしょう。
彼女らの取った行為は決して許されるべきではありませんが、
彼女らが犯行に至った背景は理解しないと、
今後もこうした事件は繰り返されるでしょう。
今回の事件とは直接関係ありませんが、
同じようなことは今さかんに糾弾されてる原発の問題や、
過労死や自殺問題とも深く関わる過重労働についても
言えるのではないでしょうか。
戦後60年余りにわたってこの社会は戦前戦中の社会とは
縁を切ったような顔をして過ごしてきましたが、
実際はそうした形で戦前戦中の社会と縁戚関係を持っていると、
僕は思っています。
角田被告の事件や、学校や職場でのいじめといった問題は、
そうした日本社会を縮小再生産してるだけなのではないでしょうか。