えんじゅです。
久しく更新が滞ってましたm(_ _ )m
67回目、そして昨年の原発事故後2度目の広島忌ですね。
だからというわけではありませんが、
野坂昭如さんの『「終戦日記」を読む』を読んでました。
- 「終戦日記」を読む (朝日文庫)/朝日新聞出版
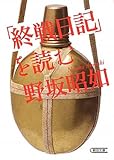
- ¥651
- Amazon.co.jp
広島県立第一高等女学校1年の生徒だった森脇瑤子さんという女性の、
昭和20年8月5日の日記の引用から始まるこの本は、
十年前にNHK人間講座でやっていたシリーズのテキストだったもので、
当時TVで見てましたが、
おしゃれなスーツに身を包んだ野坂さんが、
自身の体験を織り交ぜながら
知識人、文化人、一般の方々の「終戦日記」の記述をたどり、
当時「大人」だった人たちが戦争をどのように受け止めていたのかを、
その中から読み解こうとする試みでした。
本書の「まえがき」で野坂さんはこのように書いてます。
「 空襲で焼け出された六月五日と、玉音放送の八月十五日、今では、自分でもことさらと自覚しつつ、空をみる。昭和二十年六月五日午前七時、神戸市上空高曇り、同年八月十五日正午、日本列島は、晴。この癖は、昭和三十二年あたりからで、それまで、少し大袈裟にいうと、そのゆとりがなかった。また、同じ頃から、戦時中四十代だった方に、いつ頃から日本は負けると感じなさったか、無躾(ぶしつけ)を承知で、誰彼なしに伺い、また戦争に至るまで、戦中、戦後、いろいろな立場で、書いた本を乱読、これは今も続いている。ことさら特別な僕の感慨でもないが、つくづく、日本人は戦争を知らなかったと思う。四面海もて囲まれているお国柄と、国境を接しているヨーロッパじゃまるで違う。知らなかったことは、また、最前線で、銃を手に、敵と対峙した兵士は確かに戦った。内地じゃ、戦争は、空襲の始まるまでよそごと。もちろん、肉親を戦場で失った方々にとって、戦争は悲しくも、切実なことだ、ただ、小説で読むだけだが、遺族の受け止め方が、やはり欧米と違う。どう違うか明確にし得ないが、一言でいってしまうと、日本人は戦争を天災の類いとみなしている。聞きとりにつづいて、これははっきりしているが、昭和四十年五月、京都の古書市で、男山八幡宮神官、京都撞球場支配人の日記を見つけ、求めた。後者は、ぼくが購入したものより前の部分が、庶民の記録として、刊行されている。以後十年間、眼につく限り買い求め、雑誌にこれを公表。それこそふつうの方たちの、長いものは四十一年に及ぶ日記が集まり、時代の第一級資料。主に、聞きとりと同じ目的だった。あの時代、大人は何を考え、戦中、戦後をどうやって生きて来たのか。ほとんどといっていいが、戦争について、切実な文字はない。著名人の、活字となった日記は、さすがに触れている、しかし、国の行く末を憂うのと、子供の受験の心配が、同じ重み、文章すべてにいえるが、行間から伝わるものに配慮しないと、単なる資料。本書を編するに当り、自分なりに、あの時代を伝えるため、ぼくの経験、客観的事実で、かなり補った。「読む」のではなく、ぼくにとって、もう一度、あの時代を生きる、少し辛い作業だった。
日本人は戦争を伝えていない。「しようがなかった」で済ませようとしている、それも良い、しかし体験者は、もはや七十歳以上だが、後世に語りつぐべきだ。まさに死なんとするや、その声は、片寄っていようと、「良し」と考える。
作中、森脇瑤子さんを別に、敬称は略した。瑤子さんだけは、どうしても「さん」付けになってしまう。判って戴きたい。」(全文)
最後の一行が野坂さんらしいと思いますが、
日本人が戦争を、戦時中ですら「よそごと」として捉えてきたというのは、
たとえば、戦時中の庶民の生活を追った
岩瀬彰さんの『「月給百円」サラリーマン』などでも窺えると思います。
- 「月給百円」のサラリーマン―戦前日本の「平和」な生活 (講談社現代新書)/講談社

- ¥777
- Amazon.co.jp
野坂さん自身、14歳のときに神戸大空襲で被災、
その後、妹を連れ遠縁を頼って行った西宮での体験をもとに
名作『火垂るの墓』を書き上げ、
同作と『アメリカひじき』で直木賞にも輝いています。
- アメリカひじき・火垂るの墓 (新潮文庫)/新潮社
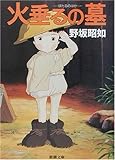
- ¥515
- Amazon.co.jp
- 火垂(ほた)るの墓 [DVD]/ワーナー・ホーム・ビデオ
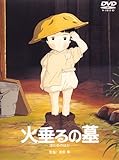
- ¥3,129
- Amazon.co.jp
『火垂るの墓』について、野坂さん自身はこう語っています。
「一年四ヶ月の妹の、母となり父のかわりつとめることは、ぼくにできず、それはたしかに、蚊帳の中に蛍をはなち、他に何も心まぎらわせるもののない妹に、せめてもの思いやりだったし、泣けば、深夜におぶって表を歩き、夜風に当て、汗疹(あせも)と、虱(しらみ)で妹の肌はまだらに色どられ、海で、水浴させたこともある(中略)ぼくはせめて、小説『火垂るの墓』にでてくる兄ほどに、妹をかわいがってやればよかったと、今になって、その無残な骨と皮の死にざまを、くやむ気持ちが強く、小説中の清太に、その思いを託したのだ、ぼくはあんなにやさしくはなかった」(『アメリカひじき・火垂るの墓』解説より)
最後の「ぼくはあんなにやさしくはなかった」という一文を、
僕はどこだったか他のところでも読んだ(見た?)記憶があるのですが、
ずっと、頭のすみに残っています。
取り返しのつかない災厄や喪失にぶつかったときに、
人はえてして後悔に苛まれることが多い(僕もそうです)と思います。
たいていの場合、「しようがなかった」と諦めることで、
その思いを晴らすことが多いかと思いますが、
この戦争や原爆、そして昨年の原発事故のように、
時には諦めてはならないときもあると思いますし、
野坂さんの場合、それが妹さんのことだったのではないかと思います。
以前、全然別の話題で僕のアメンバーさんも書いておられました が、
日本人は伝統的に、
変革や戦争といった政治に起因する出来事ですらも、
一種の天変地異のように捉えているところがあると思います。
今読んでいる宇野邦一さんの『ドゥルーズ 群れと結晶』でも
触れられてますが、
この背景には政治学者の丸山真男の言う「日本化」された仏教の影響、
一種の諦念があるように思います。
- 【現代思想の現在】ドゥルーズ---群れと結晶 (河出ブックス)/河出書房新社

- ¥1,365
- Amazon.co.jp
「諦めないこと」は潜在性の発掘にも繋がることだと思います。
ドゥルーズはこの「潜在性Virtualite」を非常に重視していました。
出来事や自己自身の潜在性を発掘すること、
出来事が「消尽したもの」でなく「疲労したもの」に過ぎない限り、
このことの意義は非常に大きいように思えてなりません。
- 消尽したもの/白水社

- ¥2,100
- Amazon.co.jp
「消尽したもの、それは疲労したものよりずっと遠くにいる。(中略)疲労したものは、ただ実現ということを尽くしてしまったにすぎないが、一方、消尽したものは可能なことのすべてを尽くしてしまう。疲労したものは、もはや何も実現することができないが、消尽したものは、もはや何も可能にすることができないのだ。『人は私に不可能なことを求めるがいい。のぞむところだ。他に何を私に求めることができよう』(サミュエル・ベケット;引用者註)もはや何一つ可能ではない。つまり徹底的スピノザ主義である。彼は自分自身消尽しているから可能なことを消尽するのだろうか。あるいは、可能なことを消尽したからこそ、自分も消尽したのだろうか。彼は可能なことを消尽することによって自分を消尽しているのだが、その逆も言える。可能なことにおいて実現されない(原文傍点あり)ものを、彼は消尽する。あらゆる疲労の彼方で、彼は可能なことと訣別するのだ。『さらに終わるために』。」(『消尽したもの』)
『「終戦日記」を読む』はまだ途中ですので、
最後まで読み終えたら、
またいずれ、感想を書きたいと思います。