えんじゅです。
先日、新聞の雑誌広告欄を見てたら、
英国の女優ティルダ・スウィントンが今週号のAERAの表紙を飾ってて、
なんとなく買ってきてしまいました(^▽^;)
朝日新聞出版/AERA 2011年12月12日号

¥380
楽天
『ナルニア国物語』などにも出演してたので見たことある人も
いるかとは思いますが、
僕は彼女を見ると80年代イギリスを代表する映像作家
デレク・ジャーマンを想い起こします。
同性愛者であることを公言し、The SmithなどのPVを製作する傍ら、
『エドワードⅡ』や『カラヴァッジオ』、『ヴィトゲンシュタイン』といった
史実に基づいたものから、
『ジュビリー』、『ラスト・オブ・イングランド』といった近未来もの、
それに『ザ・ガーデン』や『エンジェリック・カンヴァセーション』、
そして74分間ひたすら青い画面だけが映る、遺作となった『BLUE』など
極私的とも言える、美しい実験的なものまで、
彼の創る映像はどれもある種の美しさに彩られています。
ティルダ・スウィントンはそうした彼の作品の殆んどに出演していました。
ジャーマンの作品ではよく「若者」が描かれます。
ジャーマン自身が同性愛者であることを公言していたため、
彼の映像作品の主題はよく「同性愛」であるかのように解釈されますが、
僕はそうは思いません。
彼の主題は「同性愛者」や「若者」のような、
社会の末端にいるといえるような存在(つまりマイノリティー)と、
彼らを末端に追いやる社会そのもの、
ジャーマン自身が生きた80年代イギリスで言えば、
サッチャー、メージャーと続いた保守党政権とそれを支えた市民社会、
つまりはマジョリティー(多数派)ではなかったでしょうか。
それがよく、より剥き出しの形で表れてるのが、
おそらく『エンジェリック・カンヴァセーション』などを始めとした
実験的な作品群でしょう。
エンジェリック・カンヴァセーション [DVD]/ポール・レイナルド,フィリップ・ウィルアムスン
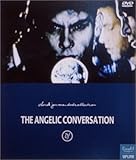
¥4,935
Amazon.co.jp
実際、70年代末期から80年代のイギリスで行われた改革では
多くのマイノリティーたちが窮地に追いやられました。
『トレインスポッティング』という映画がありましたが、
新自由主義と呼ばれる経済改革によって地方経済が疲弊、
医療費の大幅削減によりNHS(国民保健サービス)は機能不全に陥り、
手術ひとつに半年待たなければいけないのが当たり前となり、
また教育改革ではバウチャー制の導入によって教育格差が拡大、
NEETや「パンク Punk」を生み出す背景ともなりました。
トレインスポッティング [DVD]/ユアン・マクレガー,ロバート・カーライル,ユエン・ブレムナー

¥1,890
Amazon.co.jp
ブレア時代のイギリス (岩波新書 新赤版 (979))/山口 二郎
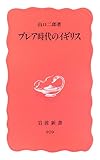
¥735
Amazon.co.jp
ジャーマンの作品ではそうした「時代」に窒息する「若者」たちが
描かれます。
それは自らが同性愛者としてマイノリティーであった
ジャーマン自身の分身であり、自画像だったのでしょう。
晩年、AIDSによる合併症によって視力をほとんど失った中で
『BLUE』を製作し1994年に物故した彼の姿は、
奇しくもその10年前、同じく同性愛者であることを公言し
AIDSによって命を落としたミシェル・フーコーに重なるような気がします。
彼もまた、
「マイノリティー」のことを常に考え続けた哲学者であったからです。
先日、新聞の雑誌広告欄を見てたら、
英国の女優ティルダ・スウィントンが今週号のAERAの表紙を飾ってて、
なんとなく買ってきてしまいました(^▽^;)
朝日新聞出版/AERA 2011年12月12日号

¥380
楽天
『ナルニア国物語』などにも出演してたので見たことある人も
いるかとは思いますが、
僕は彼女を見ると80年代イギリスを代表する映像作家
デレク・ジャーマンを想い起こします。
同性愛者であることを公言し、The SmithなどのPVを製作する傍ら、
『エドワードⅡ』や『カラヴァッジオ』、『ヴィトゲンシュタイン』といった
史実に基づいたものから、
『ジュビリー』、『ラスト・オブ・イングランド』といった近未来もの、
それに『ザ・ガーデン』や『エンジェリック・カンヴァセーション』、
そして74分間ひたすら青い画面だけが映る、遺作となった『BLUE』など
極私的とも言える、美しい実験的なものまで、
彼の創る映像はどれもある種の美しさに彩られています。
ティルダ・スウィントンはそうした彼の作品の殆んどに出演していました。
ジャーマンの作品ではよく「若者」が描かれます。
ジャーマン自身が同性愛者であることを公言していたため、
彼の映像作品の主題はよく「同性愛」であるかのように解釈されますが、
僕はそうは思いません。
彼の主題は「同性愛者」や「若者」のような、
社会の末端にいるといえるような存在(つまりマイノリティー)と、
彼らを末端に追いやる社会そのもの、
ジャーマン自身が生きた80年代イギリスで言えば、
サッチャー、メージャーと続いた保守党政権とそれを支えた市民社会、
つまりはマジョリティー(多数派)ではなかったでしょうか。
それがよく、より剥き出しの形で表れてるのが、
おそらく『エンジェリック・カンヴァセーション』などを始めとした
実験的な作品群でしょう。
エンジェリック・カンヴァセーション [DVD]/ポール・レイナルド,フィリップ・ウィルアムスン
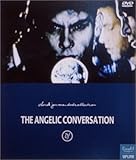
¥4,935
Amazon.co.jp
実際、70年代末期から80年代のイギリスで行われた改革では
多くのマイノリティーたちが窮地に追いやられました。
『トレインスポッティング』という映画がありましたが、
新自由主義と呼ばれる経済改革によって地方経済が疲弊、
医療費の大幅削減によりNHS(国民保健サービス)は機能不全に陥り、
手術ひとつに半年待たなければいけないのが当たり前となり、
また教育改革ではバウチャー制の導入によって教育格差が拡大、
NEETや「パンク Punk」を生み出す背景ともなりました。
トレインスポッティング [DVD]/ユアン・マクレガー,ロバート・カーライル,ユエン・ブレムナー

¥1,890
Amazon.co.jp
ブレア時代のイギリス (岩波新書 新赤版 (979))/山口 二郎
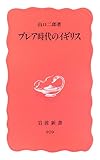
¥735
Amazon.co.jp
ジャーマンの作品ではそうした「時代」に窒息する「若者」たちが
描かれます。
それは自らが同性愛者としてマイノリティーであった
ジャーマン自身の分身であり、自画像だったのでしょう。
晩年、AIDSによる合併症によって視力をほとんど失った中で
『BLUE』を製作し1994年に物故した彼の姿は、
奇しくもその10年前、同じく同性愛者であることを公言し
AIDSによって命を落としたミシェル・フーコーに重なるような気がします。
彼もまた、
「マイノリティー」のことを常に考え続けた哲学者であったからです。