えんじゅです。
水木しげるさんの戦争物長編漫画
『総員玉砕せよ!』を読みました。
- 総員玉砕せよ! (講談社文庫)/水木 しげる
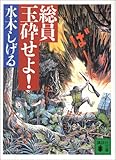
- ¥700
- Amazon.co.jp
07年に香川照之さん主演で『鬼太郎の見た玉砕』として
NHKで放送され、その後再放送もされたので、
ご覧になった方もいるかとは思いますが、
水木さんが激戦地となったニューギニアのラバウルでの
自身の戦争体験を基に、「90パーセントは事実」を描きこんだ、
渾身の戦争漫画です。
玉砕という、あまりにも重いテーマを扱った内容だけに、
読むほうとしてもなかなかすらすらとは読み進めませんでしたが、
リアルな描写と的確な状況認識によって、
主人公・丸山二等兵の所属するバイエン部隊が
なぜ玉砕しなければならなかったかを描き出していると同時に、
「ぼくは戦記物をかくとわけのわからない怒りがこみ上げてきて
仕方がない。」
と語る水木さんの戦争(とそれを遂行した軍上層部)への強い怒りが、
まるで浮かばれない戦死者の亡霊のそれのようにして、
読者に伝わってくるような気がします。
(「私、戦後二十年くらいは他人に同情しなかったんですよ。
戦争で死んだ人間が一番かわいそうだと思ってましたからね。
ワハハ」足立倫行「解説」より)
日本軍が公式に玉砕を認めたのは
1943年5月のアリューシャン列島アッツ島玉砕からとされますが、
以前NHKスペシャル「玉砕 隠された真実」で見たところによると、
実はその前年の12月にニューギニア・ゴナにおいて玉砕があり、
またその直後に同島ブナにおける玉砕があったことが
明らかになってますが、
軍部はこれを隠蔽、1944年になってからようやく公表するとともに、
「玉砕」で生き残った兵士に対しては他の帰還兵と隔離した上で
徹底してかん口令を敷き、24時間憲兵に監視させていたといいます。
http://www.nhk.or.jp/special/onair/100812.html
ちなみにアッツ島玉砕直後に隣のキスカ島で大規模な撤退作戦があり、
映画にもなったようですが、僕の祖父はこの作戦に参加していました。
祖父の生前、僕は再三この話を聞きました(聞かされたのではなく)が、
周囲を米艦船に囲まれ孤立した残留兵たちを霧の中助ける様子を
嬉々として語る祖父を見ながら
「戦争が祖父の青春なんだな」と思うと同時に、
祖父が乗っていた艦船の後ろ半分が魚雷に当たって吹っ飛び、
せっかく助けた兵士たちをむざむざ死なせてしまったことを
悲しそうに語る祖父の様子にはいつも胸が詰まる思いがしました。
アッツ島以降、軍は玉砕を容認、玉砕命令を連発していきますが、
その背景には日本本土までが米軍の空襲範囲に拡大されたこと、
慢性的な食糧不足(南方戦線の死者の多くは餓死だったそうです)、
それに軍内部の官僚的出世主義があったと言われています。
以前の記事 にも書きましたが、
この点についてジャーナリストの岩瀬彰さんは、
旧日本軍と現在の中国政府との類似性を指摘しています。
- 「月給百円」のサラリーマン―戦前日本の「平和」な生活 (講談社現代新書)/岩瀬 彰

- ¥777
- Amazon.co.jp
旧日本軍に限らず、
軍隊機構というのはよく公共事業的な面を持ちます。
それは経済状況が悪いときに特に顕著になりますが、
日本の場合も例外ではなく、
事実、沖縄や中国東北部、南方といった前線では、
当時凶作に喘いでいた東北の農家出身の兵士たちが
多かったといわれます。
そうした兵士たちは軍隊という上下関係の厳しい、
その一方で実力さえあれば誰でも這い上がれる
「公平」なシステムの中でしか、
自らの生活の向上を図るすべを持っていませんでした。
そのため彼らは出世に躍起になりl、出世のためには
どんなことでもやろうとします。
石原莞爾や板垣征四郎といった軍人たちは、
その典型とも言えるでしょう(どちらも東北出身者です)。
ですが、それは逆に言えば、
現実の社会(経済)が極めて不公平だったことの
表れではないでしょうか。
先の岩瀬さんの本によれば、
財閥トップと一般サラリーマンの平均月収の差額は
約4000倍にも上ったと言われますし、
今とは違って中流以上の人がまだまだ少なかった当時、
上流層と最下層との格差は天文学的なものだったと思います。
そうした中でテロや2・26事件のようなクーデターも起き、
また、朝鮮、台湾、満州への移民や出稼ぎ、
果ては満蒙開拓団のような国策移民までが生まれてきました
(アメリカを中心とした移民排斥の影響も確かにありますが)。
それには明らかに、明治以降の技術進歩による、
平均寿命、出生率上昇と人口増加も一役買っていたでしょう。
19世紀の戦争学者クラウゼヴィッツは
「戦争は外交の一形態」と言っていたといいますが、
逆に外交や経済こそが、戦争の一形態なのではないでしょうか。
「戦争」や「玉砕」はその延長線上にあるもののような気がします。
これはフランスの人類学者ピエール・クラストルが提唱していたという、
「国家に抗する社会」という考え方に基づくものですが、
ドゥルーズも、「戦争機械」という言葉で同じようなことを
言い表していたと思います。
『総員玉砕せよ!』では冒頭から玉砕に至る最期まで、
「わたしはなんでこのような つらいつとめをせにゃならぬ」という、
『女郎の歌』(足立氏)が通奏低音として使われています。
それは軍隊、それも旧日本陸軍という、
当時としてもちょっと異常な制度の中でつぶやかれていた、
兵士たちの心の声でしょう。