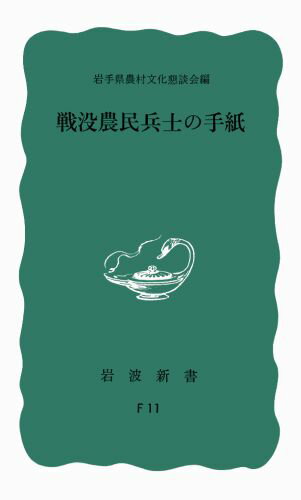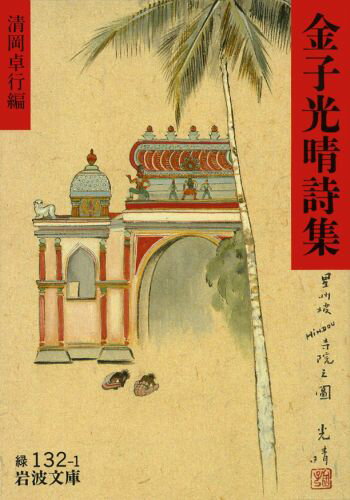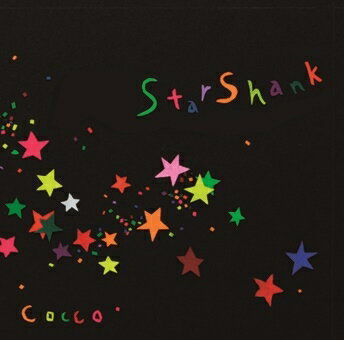掲題の本を読んだ。
内容紹介(「BOOK」データベースより)
ここに収められたものは、野良から、炭焼小屋から、戦場に駆りたてられ、尊い生命を失った農民兵士たちの便りの数々である。「国のため、君のため」というきびしい軍律のかげに、ふるさとをしのび、農作業を心配し、親はらからの身を気づかう真情が綴られたこれらの手紙は、あらためて戦争の悲惨さと恐しさを私たちに訴える。
1937年の日中戦争の勃発から1945年まで続いた戦争で駆り出された戦没農民兵士たちの手紙を、岩手県を中心に全国から集め、懇談会がよりぬいて掲載したもの。
手紙本文の他には、冒頭に送り主(戦没兵士)の名前、出身地、農家としての規模、戦没年月日、戦没地、最終階級だけが付され、余計な解説は一切ない。
それだけに、送り主たる兵士たちの直截的な心情が伝わってくる。
読んでいると、胸が詰まる思いを何度もした。
仏壇の上の鴨居にかけられた、軍装姿も凛々しい兵隊の写真、私たちは農家のあちこちで、何度そうした写真を見かけ、やっぱりこの家にも・・・・・と、何度思わされ、生きて帰れたわが身と思いくらべ、複雑な感情を抱かされて来たことだったろうか。写真が私たちに何かを語りかけている。私たちはその訴えを聞かねばならぬ、何度そのような思いに駆られて来たことだったろうか。
農村文化懇談会の会員というのは、働く農民、それに農協職員、教師、保健婦、その他さまざまの職場で農村問題に関心をもち、農民と親しい接触を保っている人々、したがってそのような写真を見かけている筈の人々でした。それが期せずして提案に対する全員の賛成となってあらわれたのだったと思います。 そして次のような理由で、ただちにこの仕事に着手しようと決めたのでした。