『海洋天堂』という映画がもうすぐ京都に来るようです。
公式サイト: http://kaiyoutendo.com/
少林寺のときから大好きなジェット・リー。
そのジェット・リーがアクションなし……?
でも、すごい見に行きたい。
すごい泣きそうです(予告編ですでに泣いた)けど、見に行きたいな。
『海洋天堂』という映画がもうすぐ京都に来るようです。
公式サイト: http://kaiyoutendo.com/
少林寺のときから大好きなジェット・リー。
そのジェット・リーがアクションなし……?
でも、すごい見に行きたい。
すごい泣きそうです(予告編ですでに泣いた)けど、見に行きたいな。
100000年後の安全を見てきました。(10万年後です。)
監督:マイケル・マドセン
公式サイト:http://www.uplink.co.jp/100000/
フィンランドにある放射性廃棄物処分場についてのドキュメンタリー。
2009年の映画。
フィンランド、オルキルオトに建設中の高レベル放射性廃棄物の最終処分場、「オンカロ」。
完成すれば世界初の高レベル放射性廃棄物の永久地層処分場となる。
最終処分場、というと分解されてばらばらになって無害になりそうな感じがしますが、要するに地中深くに埋め封鎖して、絶対に掘り起こさない、ということでしかない。
そんな危険なものどっさり地中に埋めておいて、遠い未来の人類にどうやって安全を保証すんの?
というのがテーマです。
▲マドセン監督。マッチの火が指につくんじゃないか、熱いんじゃないか、とどうでもいいことが気になった。
フィンランドの地層はとても安定しているから大丈夫、ということで建設が決定され、10万年大丈夫、という設計なのだそうです。
でも、地震が起こる可能性が0というわけではない。
戦争や不況やその他もろもろ起きる可能性もある。
「ここは放射性廃棄物の最終処分場です」ということをどうやって10万年後の未来に伝えるのか。
▲公式サイトにもあるとおり、SF映画みたいな映像がたくさんあって、とてもきれいでした。
それは愉快な美しさではなく、冷たく無機質な美しさです。
建設側の、インタビューされる人たちも、この方法が「今ある中ではベスト」とは思っているけれど、完ぺきではないことはわかっている。
後半から、ここに処分場があるから近づかないように、というメッセージをどう残していくのか、という問題が取り上げられていました。
そこで私が「ふーん」と思ったのは、この人たちは10万年後(あるいはもっと短いスパンで、数百年後)には、全然別の文明があるかもしれない、ということを真面目に考えているんですね。
その未来の人類は、今の言葉を解さないかもしれない。
現代より優れた技術を持っているとは限らない。
そういうふうに想定しています。
これ、当たり前といえば当たり前ですよね。
だって、私たちは1,000年前の人たちと同じようには話していないし、たぶん文章も読めない。
でも、私は人類は直線的に発展していくのかな、と思っていたみたい。
直線的というか、堆積していくその上にできていくというのか。
でも、どっかでぶっちぎれる可能性はありますよね。
国が亡びる可能性だってあるし、言語や文明が失われることだってあるかもしれない。
で、そんなことがあったらどうしよう、興味本位で掘り出しちゃったりしないだろうか、看板立てて「入るな危険」と書いておくほうがいいのか、むしろ何も書かずに放っておいて忘れてもらうのがいいのか…とか考えるわけなのですが、もちろん答えはありません。
そういうことを考えるのはとても大切なのはわかるけれど、なんだかとても滑稽なことのようにも見えました。
とはいえ、同時にすごくえらいと思いましたよ。
10万年後とか、もう誰の子孫もいないかもしれないのに、それでも安全を担保しなきゃって真面目に考えてるんですからね。
日本なんか、子世代にも孫世代にも責任とれないじゃないですか。
ないのが一番いいに決まっている。
でも、もうそれはある。
あるので、どうにかしなければならない。
人間の力には限界があることを知らなければならないです。
私はこれまで原発についてたいして意見を持っておらず、必要なのじゃないかと思っていました。
でも今は、急に全停止は無理でも、違う方法で発電するほうへシフトしていかなきゃいけないと思います。
それと、PCつないでブログ書いといてナンですが、大量消費社会を抜け出さないとですよね。。。
ラストに流れる"Un grand sommeil noir"がとても印象的でした。
お久しぶり。
久しぶりに映画を見てきました。
『ブラック・スワン』です。
◆バレリーナのお話。内気でおとなしい性格のニナは、「白鳥の湖」の女王役に抜擢されます。
白鳥と黒鳥の両方を演じなければならず、純粋可憐な白鳥の演技は問題ないが、妖艶で官能的な黒鳥を演じ切ることができず、ライバルも出現し、プレッシャーに追い詰められていく。
CMを見て、トゥシューズに画びょうが入ってたりするのかと勝手に思っていたのですが(笑)、ある意味少女マンガ的な流れではありました。
自分が持っていないものを持っているライバルが出現して、それが女性としての魅力と関連してくるのであれば、人間としてもつらいから、女の人にはわかりやすいんじゃないかなぁ。
スリラーというよりはホラーっぽい気がしました。効果がワリと派手だったからかな?
結末がどうなるかはなんとなくわかってくるんだけれど、ニナが踊りきれるのかどうか、ドキドキしながら見ていました。
CMで「女は怖い」みたいな感想が流れていましたが、女が怖いんじゃなくて(怖いけど)、至高の美を求めることがどういうものなのか、というのが怖かった気がする。
ナタリー・ポートマンの演技は確かにすばらしかったけれど、「壊れそうにはかない女の子」という感じではなかったです。強そうじゃん。大人の雰囲気だし。黒鳥のほうがずっと似合ってたし(笑)
白鳥の可憐さと比べ黒鳥の妖艶さの印象が強すぎたからか、「白鳥ってどこにいたの? つか、いた?」みたいなことになってしまいましたが、ニナの変化が成長によるものでなく狂気によるものだというところがよかったと思います。
ライバル(?)役のミラ・クニスは確かに魅力的。
ヴァンサン・カッセルは、どこか生臭いのだけれど単なるエロおやじでない感じでよかった。
ちょっと怖いけれど、なかなかよかったのでぜひどうぞ。
リマスター版が出て、日本でリメイクされたというので、『死刑台のエレベーター』が話題になっていますた。
ただいま、京都シネマでルイ・マル特集をしているので行ってきました。
今回見たのは、
『地下鉄のザジ』
『五月のミル』
『さよなら子どもたち』
です。
----------------------------------------
『地下鉄のザジ』
出演:カトリーヌ・ドモンジョ、フィリップ・ノワレ
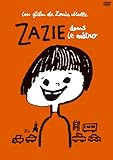
この子↓がカトリーヌ・ドモンジョ。かわいいよー。
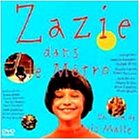
◆お話…みたいなもの◆
パリの叔父さんのところに預けられたザジは、地下鉄に乗りたかったのだがスト中。
ザジはパリを歩き回る。
◆感想◆
ストーリーらしいストーリーはなくて、ザジがパリにやって来て叔父さん夫婦、大家さん、ご近所、警官などなどとひたすらドタバタしている映画です。
ザジがもうむっちゃくちゃかわいくて、言いたい放題やりたい放題やっていて、とても楽しかったです。
これ、原作はレーモン・クノーの同名の小説。
読んだことはないのですが、きっとむちゃくちゃな小説なのだと思います。
(そういう、「小説」が解体されるような時代に書かれた作品だったと思う。)
その雰囲気がきちんと映画に表現されていた気がする。
途中、ちょっと飽きてしまいましたが、ザジと怪しい商売人(後半は警官)がおっかけっこするところなど、とっても楽しかった。
CGとかないから本当にやりたい放題です。
私が12歳ぐらいだった頃、もしかして世界はこのぐらい楽しかったのかな、と思い返してみるけれど、もう全然思い出せない。
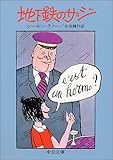
原作、日本語訳もありますね。在庫あるかしら。
----------------------------------------
『五月のミル』
出演:ミッシェル・ピコリ、ミュウ・ミュウ

◆お話◆
五月革命のさなか、ミルの母は突然亡くなってしまう。
訃報にふれて、弟のジョルジュ夫妻、娘のカミーユとその子どもたち、姪のクレールたちが家にやってくる。
遺産の相続・屋敷の売却をめぐって家族はもめるが、革命の影響を受けて葬儀屋がスト、肝心の葬儀が挙げられない。
そんな中、いよいよ革命は激化、ド・ゴールが亡命、ブルジョワは狙われる、家に放火される、などという噂を聞いて家族全員で山に逃げ込む。
◆感想◆
まぁ、逃げ込んですぐに革命が終わったということを使用人が知らせに来て、また家に戻るわけです。
ちょっとリッチな家族のお話で、亡くなったおばあちゃんそっちのけ、革命も結局話題のタネぐらいのもの。
自分たちの欲望やエゴが最優先、というところが、彼らの行動や言動からわかるようになっています。
視点はアイロニカルだけれど、説明的ではないから面白い。
このブルジョワ家族の中に、パリで学生運動に参加している学生の男の子がいて、彼は自分たちの理想を熱心に話すのだけれど、結局その革命に追われて森に逃げ出さなければならないハメになるという、とても皮肉な描かれ方。
逃げていくときも、きれいな服にきれいな靴、よいお肉、パンにバスケット。
苦労をともにしても団結が生まれるわけでもない。
家族といったって、きれいごとばかりではないよね…。
重くはなく、ユーモアがあるけれど、チクリとするものがそこここに仕掛けられています。
五月革命が何なのか、うろ覚えでした。
あと、ド・ゴール(シャルル・ド・ゴール。空港の名前になっていますね)とか、ポンピドゥー(これは、ポンピドゥーセンター)とか、固有名詞が説明なしで出てくるんで(あたりまえですけれど)、予備知識があるほうが楽しめるかも。
----------------------------------------
『さよなら子どもたち』
出演:ガスパール・マネス、ラファエル・フェジト

◆お話◆
1943年、ドイツ軍占領下のフランス。
クリスマスのバカンスが終わり、ジュリアン・カンタンはパリから疎開先の寄宿学校に戻ってくる。
そこへ新入生のジャン・ボネが転入してくるが、優秀で無口でとっつきにくい。
最初は反感を覚えるものの、少しずつ打ち解け仲良くなっていく2人。
ところがあるとき、ジュリアンはジャンの本名がボネではないことを知る。
◆感想◆
ボネではなくてキペルシュタインというのですが、つまりジャンはユダヤ人なのです。
これはルイ・マル監督の自伝的な作品とのことです。
劇的な出来事、派手なアクション、というのは特にありませんし、痛烈な戦争批判というのでもありません。
でも、少年が体験した「戦時」が淡々と描かれていて、とても説得力があると思います。
子どもと大人の境目にいるジュリアンの複雑な思いとか、残酷さとか潔癖さとか、くどくどしくない程度に丁寧に描かれています。
こういう、体験したことのない人間には語れない作品はとても貴重だと思います。
ストーリーもきちんと回収されているし、カンタン兄弟、お母さん、同級生、上級生、先生たちのキャラクターがわかりやすく、私にしては珍しく「え?誰が誰?」みたいなことがなかった。
ラスト、ユダヤ人をかくまっていることを密告され、校長とジャンたちユダヤ系の子どもたちは連行されていきます。そこで校長が「さよなら、子供たち」と言うのがタイトルの由来なんですね。
最後にジュリアンの顔が映って終わるのですが、彼自身のセリフがあるわけではないし(大人になった彼が述べているらしい言葉はかぶさってますが)、ぼろぼろ泣いているわけでもない。ただ自然にじわっと涙があふれてくる、そこで終わってます。
多分、そのときの彼は連行されたジャンがどうなるのか、きちんとはわかっていなかったのでしょうが、もう二度と会えない、という予感がしたのかもしれない。
少なくとも、戦争という状況がどういうものなのか、少しわかったのでしょうね。
そうやって大人になるわけですね。
余談ですが、神父さんがミサのときに、ジャンにはホスチアをあげないシーンがある。かくまうけれど、信者としては認められないわけだ(実際、信者ではありませんが)。ああ、これが一神教の宗教なんだなぁ、と思いました。
----------------------------------------
というわけで、どれもそれぞれ面白い映画でしたが、いちばん楽しかったのが『ザジ』、いちばん皮肉が利いていたのが『ミル』、いちばん泣いたのが『さよなら、子供たち』でした。
DVD全集(?)が出ています。
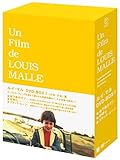

えらい久しぶりになってしまいましたが、ぼちぼち続けていきます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今年最初の映画は、『ブロンド少女は過激に美しく』です。
配給会社がフランスであることがアピールされているような気がしますが、舞台はポルトガル(リスボン)で、みんなポルトガル語をしゃべってます。
監督:マノエル・デ・オリヴェイラ
原題:SINGULARIDADES DE UMA RAPARIGA LOURA
原作:エサ・デ・ケイロス『ブロンド少女の特異さ』(1873)
出演:リカルド・トレパ(マカリオ。監督のお孫さん)、カタリナ・ヴァレンシュタイン(ルイザ)
公式HP:http://www.bowjapan.com/singularidades/
◆おはなし◆
妻にも友にも言えないような話は、見知らぬ人に話すべし・・・
リスボンからアルガルヴへと向かう列車の中、マカリオは隣り合わせた見知らぬ婦人相手に打ち明け話を始める。
マカリオは高級服飾店のオーナーである叔父のもとで会計士として働いていた。
ある日、向かいの家の窓に、扇を手にしたひとりのブロンド少女(ルイザ)が現れ、一目で恋に落ちてしまう。
友人のつてで知り合いになり互いに好意を持つものの、叔父に結婚を大反対されて職を追われるハメに…。
なんとか見つけたカーボヴェルデ(西アフリカのセネガルの西の海の諸島)での仕事で一財産築き、意気揚々とリスボンに戻ってきたマカリオだったが……。
◆感想◆
いやぁ、まず『ブロンド少女は過激に美しく』という邦題ですが、どんなエロ映画なのかと思って観に行ったら期待はずれです(笑)
そういう意味ではあんまりいい邦題ではないような気がしますが、直訳の『ブロンド少女の特異さ』ではピンとこないというのもあると思うし……工夫されたのでしょうね。
映画全体のテンポはとってもゆったりしていて、ときどき眠いぐらい。
そのせいもあってか、映画全体に古さというのかレトロさというのか、そういう雰囲気があり、「いったいいつの時代の話なんだろう?」と思ってしまいました。
ヨーロッパの古い建物のステキなお部屋に、会計士のお仕事用にパソコンが置いてあって、それだけでなんかちょっとおもしろいです。
いわゆるBGMというものがないので、曲で作品に強弱をつけるということはしていません。
その分、往来の音、鐘の音、ハープの演奏、声、そういうものが本当にきれいに聞こえる。
で、肝心のところ。エロさについて。
エロくないかというとそんなことはありません。
過激な露出シーンなどはまったくないのですが、ルイザをじっくり撮る視線がとってもエロいです。でも下品には思わなかった。
ルイザがマカリオのいる店を訪れ、マカリオと出会うとき、彼女の顔がじーっと撮られています。
もう窓から見ているから知っている顔なのだけれど、とても近くでじーっと。
これが男の視線かーーー!と(笑)
ルイザ役のカタリナ・ヴァレンシュタインについては、いわゆる整った顔立ちの方ならほかにもたくさんいると思うのですが、ちょっとタレ目ぎみでぽってりした唇、スキだらけに見えるような誘ってるようにも見えるような、すばらしいロリータフェイス。
ルイザがどんな女の子なのか(どんな考え方、感じ方をしているのか)はほとんど描かれていないのですが、どうでもよくなりました。
彼女がマカリオと再会するシーン(おそらくキスシーン)で、顔は全然映らないのですが、片足をちょっと曲げているところが映ります。
話の筋と全然関係ない! でもそのキュートさときたら。妄想気味なところがとても良い(笑)
そして、最後にどーんと脚開いて座るシーンにびっくり。
100歳恐るべし。
オリヴェイラ監督は、同じ俳優とお仕事をするタイプの監督さんとのことで、そのとおり前に見た(といっても、『カニバイシュ』と『神曲』を見ただけですが)顔がいくつもありました。
私がけっこう好きなのが、長いお顔のディオゴ・ドリア。今回はマカリオの叔父さん役でした。
『カニバイシュ』では色男役でしたけれど、年を経てちゃんとりっぱなおじさま俳優になっているからすごいです。
そして、ルイス=ミゲル・シントラが本人役で登場していました。
この人の朗読は確かによかった。よかったけれど、詩の内容に圧倒されていました。
↓のフェルナンド・ペソアの項に詩の訳が載っているのでご覧になってください。
http://www.bowjapan.com/singularidades/whoswho/
特に↓のところ。ちょっとぞっとするぐらいでした。
世界の不幸は 善意であれ 悪意であれ 他人を思うことから生じる
魂と天と地 それだけで充分だ
それ以上を望めば 魂や天や地を失い 不幸になる
……
神よ 私は善人ではありません
私は花や小川と同じ 自然なエゴイストです
他者のことに構わず ひたすら咲いて ひたすら流れる……
作品自体は「えっ、ここで終わり!?」というところで終わります。
ぽかーんとなったけれど、「金返せ!」とは思いませんでした。
なかなか良い映画体験でした。
オリヴェイラ監督は新作を撮り続けているとのことで、次回作を楽しみにしたいです。