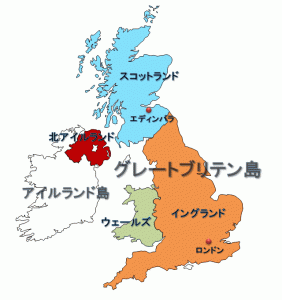三十年戦争の最中、イングランドでは清教徒(ピューリタン)による革命が起こっていた
イングランドでは三十年戦争が終わろうかという1642年、清教徒(ピューリタン)と呼ばれる狂信的なカルバン派が革命を起こして国王を処刑するという暴挙に出て、オリバー・クロムウェルが独裁政治を敷いた。
その後のブリテン島における国教会とピューリタンとカトリックの三つ巴の殺し合いの終結は、40年以上先の1689年の権利章典制まで待たねばならない。
何より、近代化の波が訪れたヨーロッパから逃れ、独自の信仰生活を求めて新大陸アメリカにメイフラワー号が向かったのは、30年戦争初頭の1620年である。カルバン派の信仰に燃える彼らは、善良な現地人を殺戮し植民により土地を奪っていった。そして、キリスト教原理主義の色彩が強く残る国、アメリカ合衆国を建国することになる。
ウェストファリア条約は近代の始点とされるが、この段階で中世宗教法と完全に決別できたわけではない。ただし、条約以降は大きな反動に対して結果的に近代化勢力が勝利した点で重要なのである。
西欧の近代化とは、キリスト教の穏健化による世俗主義の確立である。これは法治主義(英米法では、法の支配と呼ぶ)の原初である。主(God)による支配から、人の定めた法による支配、そしていかなる権力も個人の心の中に介入してはならないとする原則の確立により、文明を築いていくのである。
ちなみに、ウェストファリア体制で確立されていく近代国際法の体系は、戦国時代の日本そのものである。日本人にとっての当たり前が、ヨーロッパ人にとって当たり前ではなかった。この事実に対する無知と無理解こそが、日本人が歴史問題を考えるうえでの障害なのである。
初期の国際法は、ヨーロッパ公法にすぎなかった
ウェストファリア体制は1648年から始まったのが、できあがったわけではない。決して強固なシステムたりえていなかった。宗教としてとりわけキリスト教からの自由という試みは、その後の格闘を経て、最終的には後戻りしなかったと評価すべきである。近代化させまいとする反動は、なお数百年続くのである。
また、ヨーロッパ人はウェストファリア条約により成立した近代国家という「文明」を誇るが、ヨーロッパ人の「文明」は二重基準(類似した状況に対してそれぞれ異なる指針が不公平に適用されること)であり、国際法の実態はヨーロッパ半島の内部で適用される行動規範にすぎなかった。
その証拠に、三十年戦争後の17世紀においても、かつてのポルトガルやスペインがしたのと同じように、オランダやイングランドがアジアを侵略した。植民地化を「文明の恩恵をもたらす」と称して、現地の言語や歴史を奪い、風俗や伝統を作り替えていった。「文明」押しつけである。
17世紀、スペイン、ポルトガル、オランダの覇権に対して挑んだのがイングランドであり、3度の英蘭戦争で一進一退を繰り返しながら、オランダの勢力を奪っていく。オランダは80年に及ぶネーデルランド独立戦争(1568年~1648年)でハプスブルク帝国の支配から逃れようとしたのだが、1648年に正式独立を獲得した時には、すでにイングランドの追い上げを受けていたのだ。
ちなみに、このような大航海時代が開始された原因は、前時代にトルコの脅威に対して、ヨーロッパは全く歯が立たなかったからである。ヨーロッパ人の歴史観では、1571年のレパントの海戦でヨーロッパ連合が勝利したことを強調するが、1538年にプレヴェザの海戦で大敗したことはできるだけ語らない。現にレパント海戦は一時的なまぐれ当たりにすぎず、以後も地中海の覇権はオスマン帝国に握られたままであった。だから大西洋に飛び出して他の場所に判図を求めたのである。
それが17世紀末(1600年代後半)になると、オスマン帝国の力にも陰りが見えてくる。1683年、オスマン帝国がオーストリア・ハプスブルク家の首都ウィーンを包囲すると、ヨーロッパのほとんどの国がウィーンに援軍を出した。オスマン帝国は撃退された。
続くカルロヴィッツ和平条約で、戦勝国となるオーストリアはオスマン帝国領ハンガリーを割譲させる。ヨーロッパが東方のアジアに勝利した瞬間だった。
この勝利に貢献したのがモスクワ大公国である。中央アジアで何度もトルコと角逐しながら勢力を伸ばし、ウィーン包囲作戦を失敗させるのに大きく貢献した。このとき、ハプスブルク家の援軍として活躍したポーランドは、北方の野蛮人としか扱われていなかったモスクワをヨーロッパと認めることを提言し、他の諸国にも受容される。
ヨーロッパはアフリカやアメリカだけでなく、アジアでも勝利する。このようにして18世紀は、ヨーロッパが有色人種に自分の「文明」を押し付けていく時代となるのである。
18世紀、戦争はゲームと化したからこそ悲惨さが影をひそめた
18世紀、戦争は国王たちのゲームであった。だからこそ文明的なのであり、実際に前世紀までのような悲惨は影をひそめた。
東欧では、北方戦争(1700年~1721年)によりモスクワ大公国の覇権が成立する。この戦争は、スウェーデンのカール12世が、デンマーク・ポーランド・モスクワの周辺諸国すべてを敵に回したことで始まった。
カール12世は軍事においては天才的だったが、戦争を楽しむこと自体が目的のような国王だった。やがて周辺諸国すべての反撃により敗れ、スェーデンは大国としての地位を失っていく。
政治指導者の有能さを図る尺度の一つが、最大判図の実現である。しかし、最大判図を実現した指導者が亡国をもたらすこともある。
スウェーデンはカール12世のときに北欧最強の大国の地位を確立するが、カール12世が引き際を誤ったために、凋落の一途を辿る。その前にはデンマークが、三十年戦争初期のヨーロッパを指導したクリスチャン4世のときにこそ大国としての絶頂期を迎えるが、この戦争の敗因が原因で、大国としての地位をスウェーデンに奪われる。
他山の石とすべきは、地球の4分の1に覇を広げ、日本の最大判図を実現した東条英機だったことだろう。
ヨーロッパ中で繰り広げられた国王たちの果し合い
西欧では、常に戦争の渦中にいたのがフランスである。内政は優れていたが、戦争は下手の横好きだったのがルイ14世である。スペイン継承戦争(1701年~1713年)では、オーストリア・イングランド・プロイセンらの対仏大同盟に苦しめられた。外交も横好き(上手でもないのにむやみに好むこと)だった。
この戦争の最中に、いくつかのエポックメイキングな事件が発生する。
スペイン継承戦争の原因は、スペイン・ハプスブルク家の家系が途絶えたのに乗じて、ルイ14世がブルボン家からスペイン国王を送り込んだことによる。フランスとスペインの陸軍力は当時のヨーロッパで1位と2位を誇る。周辺諸国が結束して干渉して抗争したのだった。
フランスは苦戦したものの、王位継承を認めさせる。300年にわたりオーストリアとスペインの両ハプスブルク家の双頭の鷲に苦しめられてきたが、以後永遠に挟み撃ちにされることはなくなる。
代償は、地中海の要衝・ジブラルタルだった。イングランドは、この戦争の最中にジブラルタルを奪い、地中海の出口を抑えることで、ヨーロッパ諸国に対する制海権を主張することになる。
この後250年の歴史で多くの国がイギリスの海洋覇権に挑戦するが、ヨーロッパ北部の港は英国海軍(ロイヤルネイビー)に荒らされるのが常だったし、南回りでブリテン島を目指してもジブラルタルを抜くことができずに、地中海に閉じ込められた。
なお、イングランドはこの戦争の最中にスコットランドを正式併合し、ブリテン島を完全に統一する(以後、イギリスまたは英国と呼ぶ)。
フランスvsオーストリア(ハプスブルク家)・イングランド・プロイセンがスペイン継承戦争(1701年~1713年)で争っていた一方で、北方戦争(1700年~1721年)でスェーデンを叩き潰したのが、モスクワ大公国のピョートル大帝である。大帝は、この戦争の勝利を記念して、国号をロシア帝国と改称する。
また、1730年代のポーランド継承戦争で、ポーランドが大国としての力を失うにつれ、ロシアは東欧唯一の国として、西欧諸国と対峙していくことになる。
このようにヨーロッパでは、東はロシアから西はスペインまで、国王たちは果し合いを楽しんだ。戦争とは、国の衰亡をかけた国王たちのゲームなのである。