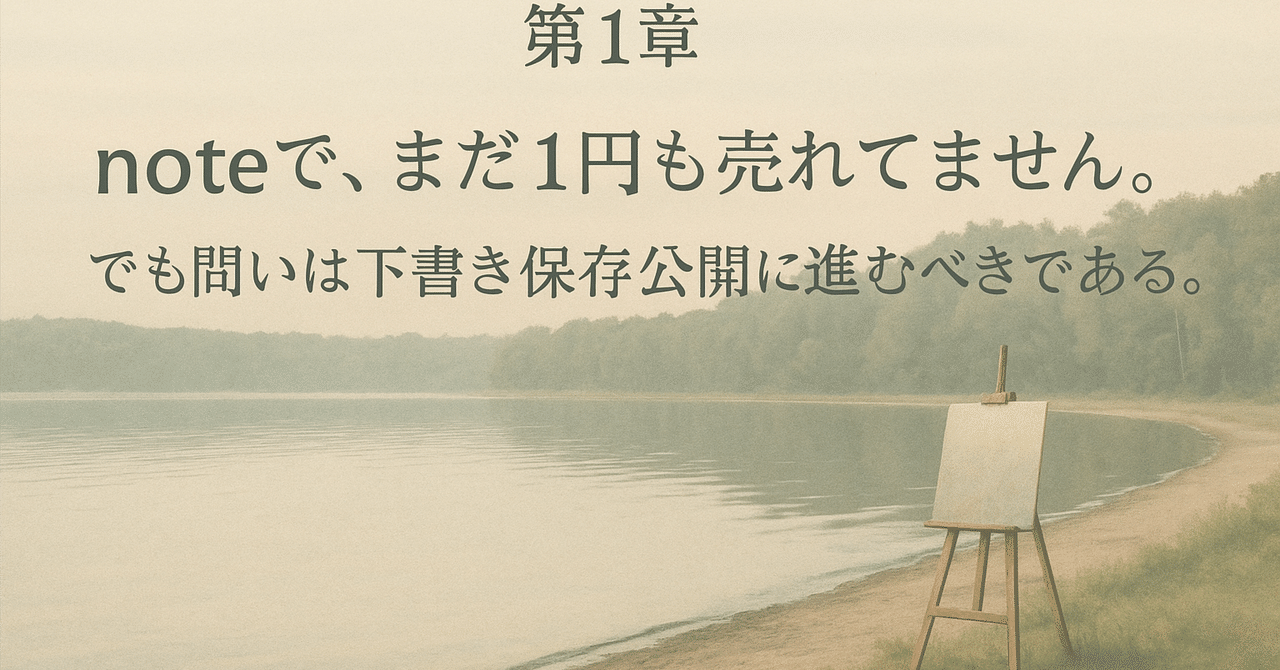🔸第1章|“違和感を覚えた瞬間”からしか、問いは始まらない
「何かがおかしい」と思った瞬間のことを、あなたは覚えているだろうか。
はっきりとした理由があるわけではない。
でも、誰かの発言や場の空気に、ふと違和感を覚える瞬間。
「なぜ?」と声に出せないまま、その感覚だけが残っていく──そんな体験が、きっと誰にでもあるはずだ。
私にとってのそれは、職場の会議だった。
数字の報告が終わり、方針が発表され、上司が「何か質問は?」と問いかける。
けれど、誰も何も言わない。
むしろ、少しでも空気を動かそうとする者を“面倒な存在”として牽制する視線が、空間を支配している。
私はそのとき、自分の中に問いが芽生えたのを感じた。
「この空気、誰が望んでいるんだろう?」
「本当に全員が納得しているのだろうか?」
「“何も言わない”ことが、最善なのか?」
けれどその問いを言葉にすることは、場を乱すことだった。
空気を壊し、議事進行を遅らせ、「自分のために言っている」と誤解されるリスクすらある。
だから、何も言えなかった。
そしてその“言えなさ”こそが、私にとっての本当の違和感だった。
問いは、何かを“知ったとき”ではなく、
“おかしいと感じたとき”に芽生える。
けれど、その芽は大抵の場合、踏みつけられる。
「考えすぎだよ」
「そういうもんだから」
「君がやらなくてもいいよ」
そう言われることで、私たちは自分の違和感を否定し、
「そうかもしれない」と思い込むようになる。
やがて、感じないふりを覚え、
違和感がない人間のように振る舞うようになっていく。
でも、本当は気づいているのだ。
・なんで真面目に働く人が損をしているのか
・なぜ上司の顔色ばかりが重視されるのか
・どうして「何も言わない人」がうまくやっていけるのか
──それらはすべて、偶然ではなく“構造の結果”なのだと。
だから私は、この違和感に蓋をせずにいたいと思った。
面倒でも、不器用でも、
問いを持つことを諦めなかった自分を、
せめて、自分だけは否定しないようにしたかった。
こうして私は、違和感の正体を言葉にするために、
日々の中に埋もれた“構造”を見つめ直しはじめた。
それは大げさな話ではない。
ごく普通の人間が、
ごく普通の場所で、
「自分のままでいたい」と願ったことから始まった、小さな思索の旅だった。
🔸第2章|「空気を読むこと」が正解になってしまった社会
私は昔から、場の空気を読むのが苦手だった。
……いや、読めないわけではない。
むしろ、人一倍、空気の流れや細かな違和感に敏感だったと思う。
だからこそ、読めるのに「従えない」自分に、
どこか後ろめたさのような、罪悪感のような感覚すら持っていた。
たとえば、上司が妙に機嫌が悪い日の朝礼。
発言しなければいけない空気が流れるけれど、
そこには「何を言っても正解にならない」という前提が漂っている。
誰かが空気を壊せば、周囲は見て見ぬふりをするか、
「よく言ったね」などと後から軽く持ち上げる。
でもその場では誰も助けてくれないし、
発言した当人が「空気の読めない人間」として処理されることもある。
私は何度もその構造を見てきた。
誰もが「おかしい」と思っているのに、
誰もそれを言葉にしない。
なぜなら、「空気に従うこと」が一番リスクの少ない行動だからだ。
反論すれば面倒を起こす人扱い。
正論を述べれば「熱量が重い」と煙たがられる。
沈黙すれば、“理解してくれている人”として扱われる。
つまり、空気を読むとは、
「違和感がないふりをすること」になってしまったのだ。
私はそういう現場で、いつも自分を試されていた。
「気づいているけど、言わないのか」
「気づいていないふりをするのか」
「言ってしまって、自分だけ浮くのか」
その三択の中で、私はいつも迷い、
結果的に“沈黙の罪悪感”を引き受ける形で日々を過ごしていた。
でも、あるときこう思った。
「なぜ私は、こんなにも“正しくあろう”としてしまうんだろう?」
「なぜ、自分の中の違和感を大事にしてはいけないのだろう?」
それは、正義感ではなかった。
むしろ、自分が「壊れてしまいそうになる感覚」に耐えられなかったのだ。
周囲に合わせ、何も感じないふりをして生きる。
その方が圧倒的に楽なことも、知っていた。
でも、私はそれをやると“自分を嫌いになる”のだ。
だから私は、空気を読まずに“踏み込む”ことを選ぶことがあった。
その結果、面倒を起こしたと見なされたこともあるし、
何も変わらなかった場面も多い。
でも、問いだけは残った。
「なぜ、誰もが“違和感のないふり”をしているのか」
「その空気は、誰が作ったものなのか」
「本当にこれは、“正解”なのか」
私は、その問いに今も答えられていない。
けれど、問いを持ち続けることで、
少なくとも“自分を壊さずに済んでいる”という実感だけはある。
空気を読むことが正解の社会で、
空気に疑問を持つことが間違いにされる。
その構造の中で、何も言えずに苦しんでいる人がいるのなら、
私はこう言いたい。
「あなたのその違和感は、正しい」
それだけは、誰かに伝えておきたいと思ったのだ。
🔸第3章|“考える人”が疎まれる職場と、その理由
「考えること」は、本来人間の基本的な営みのはずだ。
しかし職場では、それがしばしば“ややこしいこと”として扱われる。
「余計なことを言わない方がいい」
「空気を読め」
「決まったことだから、従えばいい」
そういう言葉を何度聞いてきたことか。
私が初めて「考えすぎるな」と言われたのは、20代の頃だった。
改善提案書をまじめに作った。
業務の無駄に気づき、それを報告した。
同僚の過剰負担に疑問を感じて、相談を持ちかけた。
すべて、“悪意なく”行ったことだった。
だが、返ってきたのはこうだ。
「うちのやり方を乱すな」
「黙ってやってくれる方が助かる」
「考える暇があったら手を動かせ」
そのとき私は理解した。
この職場では、“思考”は求められていないのだと。
考える人は、時間がかかる。
考える人は、質問する。
考える人は、ルールの根拠を問う。
それは、現場にとって“手間”であり、“異物”になる。
だから、考える人は最初こそ評価されるが、
やがて「扱いにくい人」とされてしまう。
それに気づいたとき、私は少しずつ黙るようになった。
表向きは合わせ、違和感は心の中にしまう。
けれど、思考そのものをやめることはできなかった。
私が“思考を手放せない人間”であることは、
ある意味で不器用だったのかもしれない。
でもそれは、ただ「正しくありたい」ということではなかった。
もっと単純に、「納得したい」という思いだった。
誰かに決められた“正解”ではなく、
自分が理解し、咀嚼し、納得できる道を歩みたい。
──その気持ちが、私を黙らせなかったのだ。
考えることが疎まれる職場は、
表面的には安定して見えるかもしれない。
だが、そこにいる人たちは、次第に“自分で考えること”をやめていく。
マニュアル通りに、前例通りに、空気通りに。
それが続けば、個々人の判断力は失われ、
「何も起きない」ことが最上の価値になっていく。
私は、その状態を“職場の死”だと思っている。
思考とは、ノイズでもなければ、無駄でもない。
むしろ、それが失われたときに、
組織は内側から静かに腐っていく。
そしてそれは、個人にも同じことが言える。
考える力を捨てたとき、
私たちは“生きているようで、生きていない”存在になってしまう。
私は、そうなりたくなかった。
たとえ誰にも評価されなくても、
“考えたままでいられる自分”を守りたかったのだ。
🔸第4章|構造は、善意を潰す──だから疲れるのはあなただけじゃない
「ちゃんとやってる人が一番損をする」
そんな言葉を、あなたも聞いたことがあるだろう。
私はその言葉を、何度となく自分自身で実感してきた。
やらなくてもいいことをやる人。
頼まれなくても動いてしまう人。
責任感が強くて、人の分まで背負ってしまう人。
──そういう人が、なぜか潰れていく。
私も何度か、精神的に追い詰められたことがある。
「誰も気にしていないなら、放っておけばいい」
「なぜ自分だけが、こんなにも抱え込んでいるのか」
「“いい人”をやっても、結局は利用されるだけじゃないか」
そう思いながら、それでも放っておけなかった。
それは“性格”の問題だろうか。
確かに、私は不器用で、断るのが下手だった。
でも、それだけではなかった。
もっと根深い「構造」の問題があるのではないか──
そう思うようになったのだ。
善意とは、構造にとって“都合のいい歯車”である。
誰かが穴を埋めれば、システムは回る。
誰かが犠牲になれば、上は評価を保てる。
誰かが無償で動けば、他の誰かは楽ができる。
そうした構造の中では、
“真面目な人ほど使い捨てられる”という現象が起こる。
しかもその使い捨ては、あからさまではなく、
“感謝と賞賛”という形をとって行われることすらある。
「○○さんがやってくれたから助かった」
「さすが、頼りになるね」
「やっぱり○○さんがいないと回らないよ」
──それは誉め言葉だろうか?
それとも、依存の正当化だろうか?
その境界線はとても曖昧で、
だからこそ、真面目な人ほど“断れない”のだ。
善意が、いつの間にか“構造の補助材”になってしまう。
そしてそれが限界に達したとき、
責任を取るのは、いつも“その人自身”なのだ。
私がこのことに気づいたのは、
同僚が倒れたときだった。
彼は何も言わず、黙ってこなしていた。
誰にも頼らず、自分だけで抱えていた。
そして、ある日突然、職場に来なくなった。
そのとき、誰かが言った。
「無理しすぎだよね」
「もっと周りに頼ればよかったのに」
──でも私は、その言葉が許せなかった。
無理をさせたのは、誰だったのか?
誰も気づかなかったのではない。
「気づいても何もしなかった」だけだったのだ。
だから私は、声を大にして言いたい。
疲れているのは、あなたのせいではない。
構造が、そう仕向けているのだ。
善意の人が潰れるように、設計されてしまっているのだ。
だから、疲れるのは“あなた一人ではない”。
そして、その事実に気づくことが、
自分を守るための最初の一歩なのだと思う。
🔸第5章|僕たちは“答え”ではなく“納得”が欲しかった
「昇進すれば楽になるよ」
「もっと給料をもらえるように頑張らないと」
「上に行けば、自由にできるから」
そんな言葉を、働き始めた頃は信じていた。
自分が苦しいのは、まだ結果が出ていないから。
周囲に認められていないから。
もっと頑張れば、もっと評価されれば、きっと……と。
でも、現実は違った。
役職がついても、自由にはならなかった。
給料が上がっても、納得感は増さなかった。
むしろ、「もう戻れない」という焦りと、
「思っていたのと違う」という空虚感だけが大きくなった。
私は何を求めて働いてきたのか。
何を得たくて、理不尽にも耐えてきたのか。
その問いに、答えが出なくなった。
そのとき気づいたのだ。
私たちは“答え”を求めていたのではない。
“納得”がほしかったのだ、と。
誰かに褒められることでも、
制度に評価されることでもない。
自分の中で、「これでよかった」と言える瞬間がほしかった。
でも現実には、
その“納得”のための言語も機会も、
ほとんど与えられてこなかった。
「決まっているからやる」
「そういうものだから我慢する」
「やる気がある人が損をするのは仕方ない」
そうして、自分の感情すら“納得のないまま”処理してきたのだ。
だから私は、問い直すことにした。
「自分は何に納得できないのか」
「それは本当に“自分のせい”なのか」
「誰がそのルールを決めたのか」
すると見えてきたのは、
納得できなかったのは“自分のせい”ではなく、
“構造に声を届ける手段がなかった”からだということだった。
私たちは、無力ではない。
けれど、構造の中にいる限り、
「納得できないことを納得したふりをする」場面が、あまりにも多すぎたのだ。
私は、そういう生き方から、そろそろ降りたいと思った。
それは会社を辞めることではなく、
「誰かの答えに合わせて自分を歪めることをやめる」ということだ。
納得のない働き方に、自分を埋めてはいけない。
そして、もし誰かに「どうしてそんなにこだわるの?」と問われたら、
私はこう答えたい。
「それが、僕にとっての誠実さだから」
🔸第6章|構造を疑う視点こそ、凡人に許された最後の抵抗
私は“特別な人間”ではない。
スキルがあるわけでも、権力があるわけでもない。
人を動かすようなカリスマも、
目を引くような発信力も持っていない。
でも一つだけ、自分の中に守ってきたものがある。
──それは、「問いを持つ視点」だ。
職場では、構造の話をする人は疎まれる。
空気を読まない、めんどくさい人扱いされる。
制度に疑問を持つと、皮肉屋と見なされる。
それでも、私は構造を見つめる視点を捨てたくなかった。
なぜなら、それを手放した瞬間から、
私は“自分で考えない側”に取り込まれてしまうと知っていたからだ。
構造とは、個人の力では変えられないものだと思われがちだ。
確かに、一人の声では制度は変わらないし、
ピラミッドの中では、意見よりも従順さが求められる。
でも、「構造を見抜く視点」だけは、
誰にも奪われない。
上司にも、同調圧力にも、空気にも、
この視点だけは明け渡すわけにはいかない。
私は思う。
構造に気づくことは、怒ることでも、戦うことでもない。
ただ、自分の中に「これはおかしい」と思える感覚を残しておくこと。
その“知性”と“誠実さ”の種火を消さないこと。
それが、凡人に許された最後の“抵抗”なのだと。
人は構造の中で生きている。
家庭にも、職場にも、学校にも。
だがそれは、構造に“呑まれる”ことと同義ではない。
思考を保つことは、
「自分の意志で立っている」ということだ。
周囲が沈黙していても、
空気が“無難”を求めていても、
自分だけは「納得できるか?」と問い続ける。
その姿勢こそが、
構造に押し流されないための、ただ一つの“武器”なのだ。
私はこの視点を、誰かに押しつけたいとは思わない。
ただ、自分がここまで壊れずに来られたのは、
この視点を手放さなかったからだと、本気で思っている。
そして、同じように感じている誰かが、
この文章にたどり着いたのなら──
「あなたのその視点は、間違っていない」と、
私は小さく、でも確かに伝えたい。
🔸第7章|問いがある限り、誠実さは死なない
私はこれまで、問いを持つことで、
何度も損をしてきた。
発言して空気を悪くした。
指摘して敵を作った。
沈黙できずに、立場を悪くした。
そしてそのたびに、こう言われた。
「考えすぎなんだよ」
「もう少し気楽にやれよ」
「自分を守ることも覚えなきゃ」
──正論だった。
私も内心では、もっと楽に生きられたらいいのにと思っていた。
でも、問いを捨てることだけは、できなかった。
問いがある限り、人は「自分でいられる」
誰かの意見に流されそうになったとき、
空気に飲み込まれそうになったとき、
「本当にこれは自分が納得できることか?」と立ち止まれる。
それは、時に孤独な営みだ。
けれどその問いが、誠実さの背骨になる。
私は、「正しさ」には執着していない。
誰かを論破したいわけでもないし、
制度をひっくり返したいわけでもない。
ただ、「自分の中で嘘をつきたくない」と思っている。
誰にも気づかれなくても、評価されなくても、
自分だけは、自分の思考から逃げたくない。
それだけが、私にとっての誠実さだった。
思考を続けるというのは、苦しい。
問いを持ち続けるというのは、しんどい。
けれど私は、それが人間の尊厳の源だと信じている。
どれだけ日々が淡々と過ぎても、
どれだけ仕事に追われていても、
「なぜ?」と立ち止まれる人間でいたい。
それができる限り、
人は“自分の人生”を生きていけるのだと思う。
だから、問いがある限り、誠実さは死なない。
たとえ言葉にならなくても、
その違和感は“あなたがあなたである証拠”だ。
他人に届かなくても、社会が変わらなくても、
あなたの中のその問いは、意味がある。
私は、その思いだけを携えて、今日も働いている。
🔸第8章|もしあなたにも“違和感”があるなら──noteで少し深く話したい
この文章を書きながら、何度も思った。
「こんなことを書いて、何になるのか」
「誰かに届くのか」
「どうせ、何も変わらないのではないか」
でもそれでも、私は書きたかった。
なぜなら、
“書くこと”が、私にとっては「問いを形にする行為」だからだ。
もしあなたが今、
・うまくいっているようで、どこか空虚さを感じている
・頑張っているのに、報われない現場に疲れている
・何が正解かわからず、自分の感覚が鈍くなっている
──そんな違和感を抱えているのなら、
あなたはもう、“問いの入口”に立っている。
そして、その感覚は、けっして間違っていない。
それは「弱さ」ではなく、「誠実さ」の証だ。
このアメブロでは、比較的日常に近い文脈で綴っているが、
実は、より深く構造や思考を掘り下げる場所を、別に持っている。
それが、noteだ。
noteでは、より長く、より静かに、
私自身の問いや哲学、構造に対する違和感を掘り下げている。
このアメブロが“入口”なら、
noteは“内省の書斎”のようなものかもしれない。
誰かの答えになりたいのではない。
ただ、誰かの問いと、どこかで交差したい。
もし、あなたの中に言葉にならない何かがあるのなら──
その“何か”を持ったまま、そっとnoteを覗いてみてほしい。
▶︎ noteはこちらから
問いがある限り、人は変われる。
そして、それはいつでも「違和感」に気づいたその瞬間から始まる。
私はその変化を、信じている。
たとえ、凡人でも。
最後に
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
これは、一人の会社員としての思考の記録です。
何かを変える力も、声を上げる勇気もないまま、
それでも「問いを持ち続けたい」と願う、ただの凡人の言葉です。
社会に呑まれそうな日々の中で、
私たちはつい、“違和感”に蓋をしてしまいます。
でも、問いがある限り、人は流されずに生きられる。
だから私は今日も問い続けます。
問いが、自分を守ってくれると信じているからです。
■noteでは、より深く“構造と思索”について掘り下げています。
よろしければ、あなたの中の問いと交差できる機会があれば嬉しいです。
▶︎
PARKのご案内
■また、近いうちに**PARK(パーク)**という新しい場でも発信を始めます。
“問いを共有するための場所”として、小さな広場をつくれたらと思っています。
PARKのリンク⇒ https://park.jp/?outer_ref=INV-N1YKVT
▶︎ 私のPARKも準備中です。開設時にはお知らせいたします。
誰かの答えではなく、
誰かの問いと、どこかで静かに交差できるような文章を。
これからも、そんな思いで綴っていきます。
また、お会いしましょう。