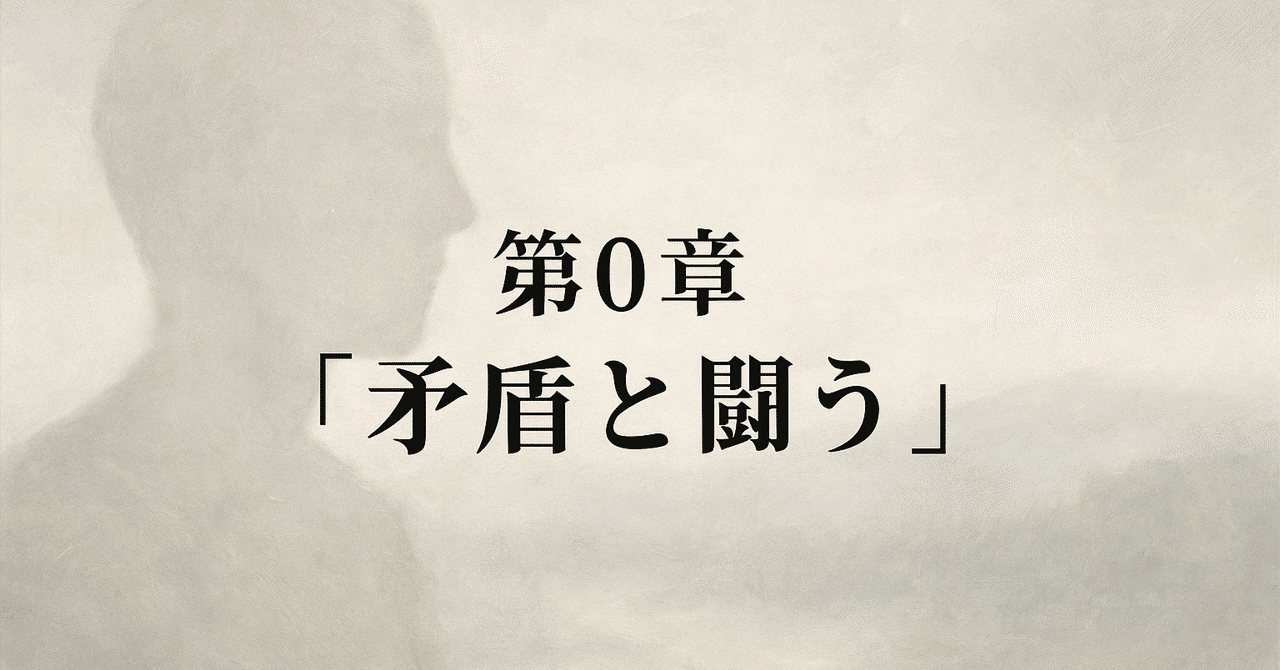はじめまして。
会社員歴29年、小売現場でただ働き続けてきた一人の凡人です。
このnoteでは、長年私が現場で感じてきた「違和感」を起点に、
なぜ働くほどに心が削られ、
なぜ努力が報われず、
なぜ“正しいこと”が通らないのかを、構造の視点から考えていきます。
派手な成功談はありません。
誰かを救える言葉も書けません。
でも、ひとつだけ約束できるのは、
ここにあるのは「誰かの答え」ではなく、
「あなた自身の問い」と重なり得る言葉たちです。
「なぜ、ここまで疲れるのだろう」
気がつけば、週明けの朝が怖くなっていた。
何か大きな出来事があったわけじゃない。
誰かに明確に傷つけられたわけでもない。
ただ、少しずつ、何かに削られている気がしていた。
会社では、気を使いながらも黙って働き、
上司の顔をうかがい、後輩の尻拭いをし、
「よくやってるな」と言われても、
どこかで「これが報われる日なんて来るのか?」と自分に問いかけていた。
誰かに愚痴をこぼせば「そんなもんだよ」「我慢しなきゃね」と言われ、
自分でも「そうだよな」と頷いていたはずなのに、
なぜか納得できない。
なぜか、息苦しい。
その理由を、私はずっと知りたかったのだと思う。
🔷第1章|なぜ、働くほどに心が削られるのか
「おつかれさまです」と言いながら、
心のどこかで「もう疲れきっている」と思っている自分がいた。
体力の問題ではない。
やる気がないわけでもない。
誰かに理不尽な目にあったわけでもない。
──それなのに、心がじわじわと削れていく。
その理由を、私は長らく“自分の問題”だと思っていた。
気の持ちようだろう。
もっとポジティブに考えないと。
仕事はそんなもんだ。
誰もが頑張ってる。
──そう言い聞かせて、29年。
私は「言い訳しない自分」を続けてきた。
でもある日、ふと気づいてしまったのだ。
削られていたのは、能力でも気力でもなく、
「問いを持つ力」そのものだったのではないかと。
どうしてこうなっているんだろう?
この仕事の意味は何だろう?
この組織の仕組みは正しいのか?
自分がここにいる理由は?
本来なら、働くことで“強くなる”はずだった自分のはずが、
働くことで“問いを失う”人間になっていた。
そして、それは私だけではなかった。
会社の中には、何年も何十年も、
疑問を飲み込みながら働いてきた人が、無数にいた。
そして、あるときから黙りはじめ、
いつしか「問いすら持たない顔」になっていた。
それが、「働くことの正体」なのだろうか。
いや、違う。
そう信じたい。
私は、自分の人生をかけてそう言い続けたいのだ。
働くことで“壊れる”人がいるなら、
それは個人の弱さではなく、
社会の“構造”に問題があるのではないか。
この問いを、ここから始めたい。
🔷第2章|29年間の現場──賞賛されず、昇進せず、ただ疲弊してきた記録
私は、29年間ずっと現場にいた。
転職もしていないし、昇進もしていない。
いわゆる“平社員”のまま、日々を積み重ねてきた。
出世欲がなかったわけではない。
ただ、望んだところで評価は得られなかった。
なぜか?
答えは簡単だった。
「動く人」が損をする構造だったからだ。
例えばある日、繁忙期に人が足りなくなったとき、
私はシフトを入れ替え、若手の代わりに出た。
「助かります」「ありがとうございます」と何度も言われた。
けれどその3ヶ月後、昇進したのは、その若手だった。
彼は、自分の評価面談でこう言ったらしい。
「自分は自己管理を徹底し、無理な稼働は避けてきました。周囲に頼れる体制も整えました」
──確かに、間違ってはいない。
でも、その“周囲”の中には、黙って補填した私がいた。
別の日、クレーム対応で店が大混乱したとき。
私は矢面に立ち、夜9時までお詫びに回った。
上司には「ありがとう、任せてよかった」と言われた。
でも、その場にいなかった課長が、翌日の朝礼でこう言った。
「トラブル時に出ていかなかった判断も、管理職としての落ち着きです」
──なるほど、そうなるのか。
誤解してほしくない。
私は見返りが欲しくて動いていたわけではない
でも、何かが“奪われていく感覚”は確かにあった。
それは、評価でもなく、地位でもない。
“存在の意味”だった。
やがて私は気づく。
この構造では、「誠実に動く人間」が摩耗するようにできている。
・指示された以上のことをしても、それは「当然」と扱われる
・余計なことをせずにルールを守る者が「安定している」と評価される
・誰かの尻拭いをしても、評価表には載らない
・頑張っても、目立てなければ意味がない
気づけば、私は“便利な補助輪”になっていた。
そして、ある瞬間から考えるようになった。
「これは、自分の努力不足なのか?
それとも、努力を報われないものにしている“構造”の問題なのか?」
会社という組織は、本当に「頑張る人」を見ているのか?
公平に評価しているのか?
──そんな問いを持ったとき、私は決して“冷笑”ではなく、
“構造を見つめる視線”を持ち始めたのだと思う。
私の29年間は、ただの経験ではない。
この社会にある“歪み”を、地面すれすれの目線で見てきた時間だった。
そして今、ようやくそれを言語化する覚悟ができた。
🔷第3章|組織とは「逆三角形」でなければならない──多数決と責任構造の矛盾
会社はよく「ピラミッド型組織」だと言われる。
上に行くほど権限が集中し、下に行くほど人数が増える。
トップが意思決定し、ミドルが伝達し、現場が実行する。
──一見、効率的に見えるこの構造が、現場の疲弊と「問いの喪失」を生んでいるとは、あまり語られない。
なぜなら、この構造では「意思決定者」が現場から最も遠い位置にいるからだ。
現場で何が起きているかを肌で感じていない人間が、数字だけを見て判断する。
その判断が間違っていたとしても、責任は分散される。
下にいる人間は、ただ「方針に従う」ことを求められ、自分の判断を放棄するようになる。
そして、その状態が続くと、人は考えなくなる。
現場には知恵がある。
日々お客さんと接し、トラブルに対応し、状況に応じて柔軟に動いている。
それでも、上が決めたルールが優先される。
「本部からの通達です」──この一言で、現場の声はかき消される。
あるとき私はこう思った。
「この会社の構造は、逆三角形でなければならないのではないか?」
現場こそが最上部であり、
そこからの声や経験が、組織全体を支える構造。
上に行くほど、現場を支えるために責任を引き受け、
最も重い判断をする覚悟を持つ人間が配置されるべきだと。
だが現実にはどうか。
上に行けば行くほど、「自分の責任を減らす技術」に長けた人間が増えていく。
部下に任せる。数字を出させる。報告書を書かせる。
そして何かが起きたときは、「なぜもっと早く相談しなかったのか」と言う。
構造として責任が逆流しているのだ。
これが、「ピラミッド型組織」の最大の矛盾だと思う。
そして、この構造は会社だけにとどまらない。
国家も、教育も、家庭も、似たような逆流構造を内包している。
多数決は、形式上の平等を装うが、実態は「声の大きい人」が支配する構造である。
責任は薄まり、意思は曖昧になり、現場だけが消耗していく。
そんな構造の中で、問いを持つことすら「余計なこと」とされる。
でも私は、逆を言いたい。
問いを持たなくなったときこそ、人は“構造に組み込まれる側”になるのだと。
🔷第4章|「頑張る人」が潰され、「動かない人」が守られる構造の正体とは
「やる人が損をする」
職場でたびたび聞くこの言葉が、冗談ではなく“前提”として共有されている場面がある。
そこでは、「動ける人」が多くの仕事を引き受け、「目立たない人」が長く残る。
それは個人の性格や能力の問題ではない。
そうした現象を“合理的に生み出す構造”が、静かに職場に根づいている。
まず、会社の評価制度を思い出してほしい。
多くの場合、上司が評価者となり、部下の働きを点数化する。
だが、上司自身が現場の実態を把握していない場合、評価基準はどうなるか?
「報告がうまいかどうか」
「目に見える成果があるかどうか」
「トラブルなくやっているように“見える”か」
つまり、「伝え方」と「目立ち方」が重視される。
そしてその逆である“地味な下支え”は、「あって当たり前」とされて評価されない。
私はこれまで、困っている同僚のフォローに何度も入ってきた。
欠員が出た時、クレームがあった時、トラブルで現場が止まりそうな時──
とっさの判断で動き、対応し、なんとか持ち直す。
でも、その動きは上層部に報告されない限り「なかったこと」になる。
報告すれば自己アピールになる。しなければ“空気”になる。
一方、常に一定距離を置いて動かない人が「安定している」と評価される現実も見てきた。
やがて、現場にはこういう空気が生まれる。
「下手に動くと損するよ」
「黙ってやると潰れるよ」
「見てる人だけが得するよ」
──それが、構造である。
さらに厄介なのは、“真面目な人ほど潰れる”という事実だ。
・責任感が強い
・人に迷惑をかけたくない
・不備に気づいたら黙っていられない
そんな人間ほど、「やってくれる人」になり、
気づけば「頼られすぎて動けなくなる人」になっていく。
しかも、その過程で一度も「ちゃんと評価された」という実感を持てないまま、
心が磨耗していく。
この構造において、「動かない人」は叩かれない。
失敗もしないし、責任も取らない。
だから長く生き残る。
一方で、「頑張る人」は期待値が上がり、
失敗すれば「なぜできなかったのか」と責められ、
成功しても「次も当然やってくれるよね」と扱われる。
これが、“努力がコストになる構造”の正体だ。
だから私は、こう言いたい。
「頑張れ」という言葉が、構造を無視して使われるとき、
それは暴力になる。
人は怠けているのではない。
構造によって、「頑張ったら壊れるように」配置されているのだ。
だからこそ、個人の努力ではなく、
“構造そのもの”を問い直すことが必要なのだ。
🔷第5章|私はなぜ、この状況で“誠実さ”を捨てなかったのか──問いの芽生え
構造に逆らわず、空気を読み、動かずにやり過ごす。
そうすれば、疲弊せずに生きられる──それは分かっていた。
なのに、私はなぜ、それができなかったのだろう。
振り返れば、何度も「やらなきゃよかった」と思った場面があった。
言われてもいないタスクを拾い、
面倒な仕事を請け負い、
後輩のフォローにまわり、
他部署のミスの尻拭いまでしてきた。
どれも、しなくても責められなかった。
むしろ、やらない方が“無難”だった。
けれど、どうしても見過ごせなかった。
困っている人がいるとき、
ルールの裏で誰かが傷ついているとき、
私は「黙っている方が後味が悪い」と思ってしまった。
それは、正義感ではない。
称賛されたいわけでもなかった。
ただ、自分の中の“線”が引かれていたのだと思う。
「ここを超えたら、自分を嫌いになる」
そんな直感的な境界線。
誠実さ、という言葉はきれいすぎるかもしれない。
でも私にとってそれは、理念ではなく“体感”だった。
誠実であることが、結果として自分を保つための唯一の手段だったのだ。
しかし、それは決して“強さ”ではなかった。
たびたび後悔し、損をし、孤独を感じた。
「あんなことしなきゃよかった」と思う夜もあった。
それでも、なぜ捨てきれなかったのか。
今になって思うのは、問いを持ち続けていたからだ。
「これは本当に正しいのか?」
「誰もが黙っているけど、私は納得していない」
「このまま流されたら、自分が壊れる」
その問いがあったから、私は自分に踏みとどまることができた。
誠実さとは、「他人に対して誠実であること」ではない。
むしろそれは、“自分の問い”に対して誠実であることだ。
それを捨てたとき、人は楽になる。
だが同時に、何か大切なものを失ってしまう。
私が29年間、どれだけ評価されなくても、
昇進しなくても、
言葉にされなくても、
「問いを持つ自分」であれたことだけは、誇りに思っている。
なぜならその問いは、私が社会に呑まれず、
“考える存在”として生きている証だったからだ。
🔷第6章|民主主義と資本主義──“平等の仮面を被った差別構造”への批判
「平等です」
「みんなにチャンスがあります」
「努力は報われます」
そんな言葉を、何度聞いてきただろうか。
学校でも会社でも、政治の場でも──
この社会は「公正」であることを前提に動いている。
少なくとも、そう“装って”いる。
でも、本当にそうだろうか?
資本主義は、競争を前提とする。
商品も、人材も、資源も、すべては「より効率的に動かす」ために仕組まれている。
その過程で利益が生まれ、評価が生まれ、格差が生まれる。
一方、民主主義は「一人ひとりの意見が等しく尊重される」という建前の上に成り立っている。
投票は平等。発言権は自由。立場に関係なく、意見は届けられる。
──はずだった。
だが現実には、資本主義の構造が民主主義を飲み込んでいる。
「声の大きい者」が目立ち、「金のある者」が決定権を持つ。
「時間を持つ者」が発信し、「立場のある者」が正論になる。
そして、多くの人はその構造に抗えない。
たとえば会社。
働く者の声はある。けれど、意思決定は上層が握っている。
「提案は自由」と言いながら、現場の声は“調整案件”として処理され、
経営層の判断が優先される。
これは、資本主義の論理だ。
「効率」と「収益」が絶対基準になり、個人の感情や思考は「非合理」として切り捨てられる。
一方、会社は「公正な評価制度」を掲げている。
これが、民主主義の顔だ。
誰にでもチャンスがあり、誰でも昇進できる。
だが、その“評価”が何によって決まるかは、
ほとんどの社員が知らされていない。
見えない基準、属人的な判断、上司の印象──
それは「平等の仮面を被った差別構造」に他ならない。
社会も同じだ。
政策は「国民の声を反映している」と言うが、
実際には情報を持つ者、発信できる者、組織票を動かせる者の意見が通る。
それは、制度が壊れているのではない。
構造が、“そういう仕組み”で設計されているからだ。
私は、こうした構造の中で生きる自分を、長年“責める側”に置いてきた。
「努力が足りないのではないか」
「自分がもっと合理的になればいいのではないか」
「空気を読めないのは自分の側ではないか」
でも、違った。
私が苦しかったのは、怠けていたからではない。
“問いを持つ人間”としてこの構造に適応できなかったからだ。
だから今、私は声にする。
この社会は、形式としての平等をうたう一方で、
中身としての“不平等”を温存している。
それを“差別”と言わずして、何と言えばいいのか。
そして、その中で思考しようとする者が、
「ややこしい人」「空気を読まない人」として扱われるとき、
私はそれに対して静かに異を唱え続けたいと思う。
🔷第7章|承認・成果・昇進──本当にほしかったものは“納得”だった
長く働いていると、ある段階で自分に問いかける瞬間がくる。
「自分は、何がほしくてここまで頑張ってきたんだろう?」
若い頃は、評価が欲しかった。
頑張れば認められると思っていたし、数字を出せば正当に扱われると思っていた。
でも現実は違った。
承認は“関係性”によって左右され、
成果は“演出”によって塗り替えられ、
昇進は“空気”と“順番”で決まっていく。
そして気づいたときには、すべてが“期待するほどのものではなかった”と知る。
ある時期から、昇進の話がまわってこなくなった。
私は、地味な存在になっていた。
できるけど面倒を起こさない人間。
黙々と穴を埋めてくれる人間。
要するに、「便利な歯車」として最適化された存在だった。
最初は悔しかった。
でも、あるとき気づいた。
私は本当に「昇進したい」と思っていたのか?
肩書きが欲しかったのか?
もっと給料が欲しかったのか?
──違った。
私は、ただ「納得したかった」のだ。
自分のやってきたことに。
自分の決断に。
自分の誠実さに。
それを、他人に承認されなくてもいい。
ただ、自分で「これでよかった」と言える日が欲しかった。
でも構造は、それを許さなかった。
納得できない状況が繰り返され、
言い訳も、自己正当化も尽き果て、
ただ疲労感だけが残る日々。
そんな日々の中で、「自分を納得させる理由」が見つからないというのは、
精神的には想像以上に重い。
だから私は、「何を得たか」よりも「何を失わなかったか」に目を向けるようになった。
私はまだ、自分の問いを捨てていない。
流されながらも、問い直すことをやめていない。
何度も疑い、何度も揺れ、それでも「自分のままでいたい」と思っている。
それが、私にとっての“納得”なのだと、今なら言える。
たとえ、昇進しなくても。
評価されなくても。
誰にも届かなくても。
自分にだけは、嘘をつかずにいられた。
──それが、私が働きながら守り抜いた、たった一つの誇りだった。
🔷第8章|構造の外側に、自分の人生を設計することはできるか
私はこれまで、会社という構造の中で生きてきた。
評価も、給料も、立場も、全部“枠の中”で決まる世界だ。
そこにはルールがある。
暗黙の了解もある。
勝ち負けも、順番も、空気もある。
気づけば、その構造の中で「どう立ち回るか」を考えるようになっていた。
でもあるとき、ふと立ち止まった。
──そもそも、なぜこの枠の中にいなければならないのか?
社会には構造がある。
それは避けられない。
どこへ行っても、何をしても、
人が集まり、ルールができ、構造が生まれる。
だけど、「すべてを構造の中で決めなければならない」という前提は、
本当に必要なのだろうか。
組織にいながらも、自分の生き方は自分で決められないか。
会社にいながらも、自分の思考と問いは手放さずに済まないか。
他人の評価軸ではなく、“自分の納得軸”で生きる道はないか。
そんな問いを、自分に返すようになった。
構造の中にいながら、構造の外側を思考する。
そのためには、物理的な脱出ではなく、
思考の自立が必要なのだと思う。
誰が何を言っても、自分で考える。
組織がどんな決定をしても、背景を読み解く。
多数派が正しそうでも、自分の問いを保留しない。
それが、“構造に呑まれない生き方”の第一歩なのだと思う。
私は会社を辞めたわけではない。
出世したわけでもない。
フリーランスになったわけでもない。
でも、私は今、
「自分の人生を自分で設計する」という意思を持って生きている。
それは、肩書きや制度では測れない“在り方”の話だ。
構造の外側に、自分の人生を設計する──
それはきっと、社会と距離をとることではない。
社会に飲まれながらも、自分の重心をずらすということだ。
自分の問いと、自分の誠実さの上に、
人生を組み立て直していくということだ。
🔷第9章|それでも問い続ける理由──凡人の哲学にできる唯一の反撃とは
私たちは、問いを忘れるように設計された社会に生きている。
マニュアルがあり、正解があり、
「とりあえず従う」ことが楽であるように仕組まれている。
そうすれば、摩擦が減る。
誰かに嫌われることもない。
目立たずに、順調にやっていける。
でもその代わり、
“考える力”が、静かに削られていく。
私は、問いを持ち続けてきた。
それが正解だったとは思わない。
むしろ、それによって苦しんできたことの方が多かった。
浮く。
煙たがられる。
何を言っても「面倒な人」にされる。
それでも私は、問いを捨てられなかった。
なぜなら、問いこそが“自分であること”の最後の砦だったからだ。
問いを持つことは、面倒なことだ。
でも同時に、
問いを持つことは、社会の構造に対して「考える人間」としての立場を持つことでもある。
凡人にできる反撃は、そこにしかない。
構造を責めるのではなく、
他人を糾弾するのでもなく、
ただ、自分の思考と誠実さを手放さないこと。
それが、私の選んだ生き方だ。
会社というピラミッドの中で、
理不尽に押しつぶされそうになりながらも、
私は今日も問いを持って働いている。
「なぜ自分は、ここにいるのか」
「なぜこれは正しいとされているのか」
「自分にとって、本当に大切なものは何なのか」
問いがある限り、私は“自分のまま”でいられる。
問いがある限り、私は社会に対して考える余地を持ち続けられる。
問いがある限り、私はまだ変われるし、変えられる。
これが、私の小さな哲学だ。
誰かの答えにはなれないかもしれない。
でも、誰かの問いと交差できるなら──
そのとき、私の問いにも意味が生まれる。
そしてそれこそが、凡人の哲学にできる、最も誠実な反撃なのだと思う。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
これは、ただの会社員の思考記録です。
何かを変えられるわけでも、
誰かを救えるわけでもありません。
でも、こうして書き残すことで、
「問いを持って生きる」ということが、
決して無意味ではなかったと思える気がしています。
世の中は、いつも効率と結果で動いています。
それに抗うように問いを持つことは、
しばしば“損”に見えるかもしれません。
けれど私は、思うのです。
問いがあるから、立ち止まれる。
問いがあるから、自分で選べる。
問いがあるから、他人に巻き込まれずに済む。
だから、どうかあなたの中の“問い”も、
見失わないでいてください。
たとえ今は言語にならなくても、
その違和感こそが、誠実さの証です。
誰かの答えではなく、
誰かの問いと交差できる言葉を。
そんな思いで、これからも発信を続けていきます。
よろしければ、noteでも関連する記事を更新しています。
より深く、一緒に考えてみたい方は、ぜひそちらもご覧ください。
▶︎ noteはこちら
🏞PARK(パーク)という場所について
PARKは、クリエイターのための**「思想や世界観を共有する場」**をつくるために生まれた、新しい形の発信プラットフォームです。
noteやアメブロが“読みもの”としての文章を届けるのに対し、
PARKでは、より**密度の高い「つながり」や「対話」**を前提とした空間が設計されています。
たとえば──
-
単なるフォローではなく、「共鳴」や「継続参加」が重視される
-
コメント欄ではなく、「問いかけ」や「対話型の投稿」が主役
-
収益化ではなく、「思想の共有」による関係性の構築が中心
つまり、PARKはSNSでもなく、ブログでもなく、
“誰かの答えに向かうのではなく、問いを持ち寄るための場”なのです。
■ PARK公式サイト → https://park.to(外部リンク)
準備が整い次第、私のPARKも開設予定です。
気になる方は、ぜひ公式サイトを覗いてみてください。