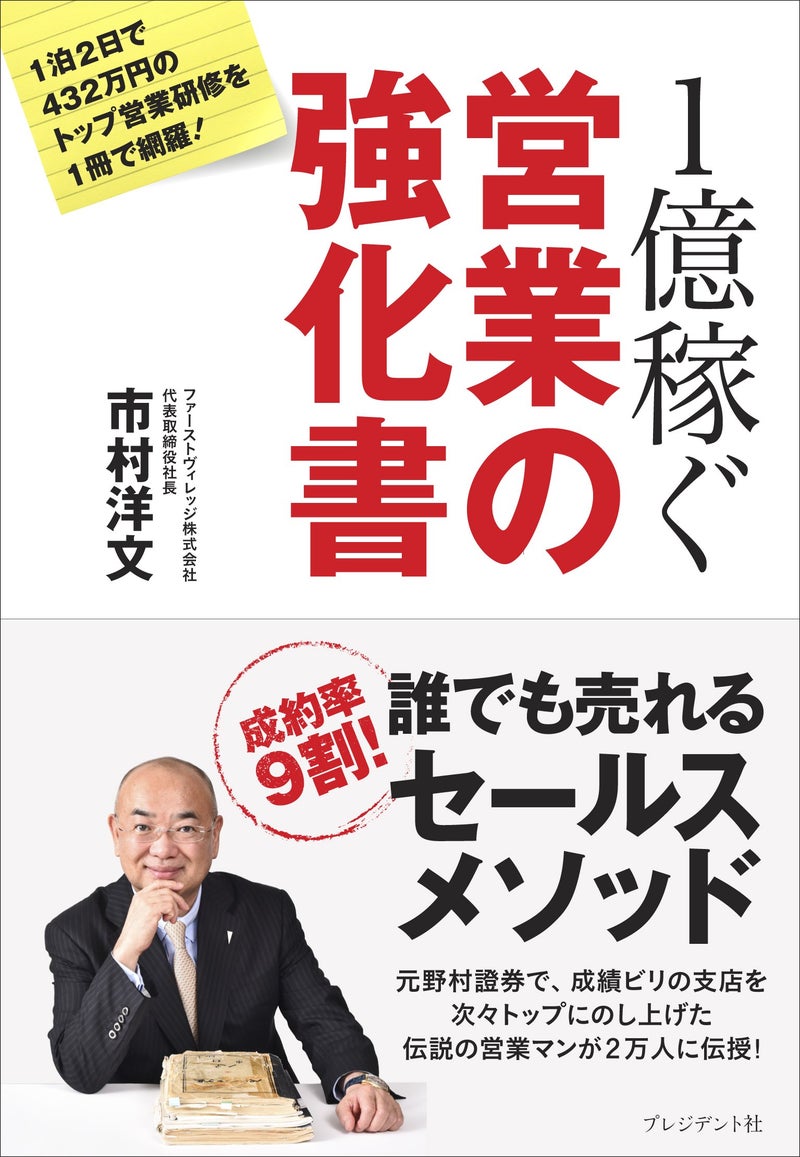不確かな壁
日本では4月11日、作家・村上春樹氏の6年ぶりの新作長編小説『街とその不確かな壁』をいち早く手に入れようと、多くのファンが深夜から書店に並んだそうだ。
黒い表紙にゴールドの帯。
600 ページ超の大作である。村上ワールドとはいかに。
村上氏はこの新作小説を、新型コロナウイルスのパンデミック中に「ほとんど外出することもなく」執筆したのだという。
作品では、主人公が高い壁に囲まれた街へ旅をする。
661ページにわたる物語は3部に分かれ、主人公は10代から中年へと変遷するが、さて、「不確かな壁」とは何だろう。
コロナ禍やウクライナの戦争のことか。
こちらとあちらを隔てる「壁」を意識せざるを得ない昨今の時代状況を映したものだろうか。
これまでも、私が知る限りでは村上氏の作品の多くは、1980年代から90年代にかけての日本経済の低迷を背景にしていると読み取れる。
だからといってそれは、他の文化圏の読者の理解を妨げるものではない。
作品のほとんどが日本を舞台にし、いかにも『日本的な』社会構造を語っているにも関わらず、50以上の言語に翻訳されているほど広く読者を得ていることに驚く。今回の本はまだ感想はわからない。
それにしてもどこの書店も本をタワー状に積み上げた華やかなディスプレーが目を引いた。
世界的人気作家の話題作で店を活気づけようと、並々ならぬ意欲が伝わる。
そのような中、市営書店も登場した話しを東奥日報「天地人」で読んだ。
人口減少に加えネット通販、電子書籍の普及を背景に、街の本屋さんが苦戦していると伝えられる。
出版文化産業振興財団の昨年9月時点の調査によると、書店のない市町村が全国で 26%に上る。
全国の書店数はこの10年で3割減少した。
一方で新しい動きも目につく。最近の地方では大手コンビニのローソンが書店を併設した店舗をオープン。
本好きが高じて20代の店主が開業した青森市のブックカフェ&バーも話題を呼んだ。
八戸ブックセンターは、本で町を盛り上げようと開設された全国でも珍しい市営書店として注目されている。
本との出合いの場は、既成概念の「壁」を越えながら多様化しているようだ。
進化の過程にあるといえるのかもしれない。
![]() 7冊目となる新著「ヤバい!準備力」
7冊目となる新著「ヤバい!準備力」![]()
書店・Amazonにて絶賛発売中!
![]() おかげさまで7刷り御礼!
おかげさまで7刷り御礼!![]()
![]() 『1億稼ぐ営業の強化書』
『1億稼ぐ営業の強化書』![]()