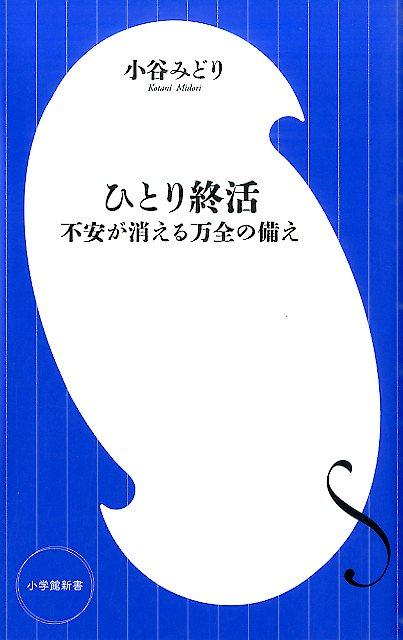故夫の人生は、波乱万丈であった。
「島医者の独り言」
は、ほんの一部でもある。
自分の人生を書き下ろし、本を出したい。
何度もその言葉を聞いてきたが、それも実現できずに若くして天国へ旅ってしまった。
ブログ始めた頃に「島医者の独り言」を書き写したが、ここで再度書き写してみようと思います。
島医者のひとりごと
K病院
院長
◯◯ ◯◯
第一章
「ある日の事、ある学生が、遠路わざわざK島まで訪れた」
ある日の事、ある医学生が、遠路わざわざK島まで訪れてこられた。離島実習とかいっていた。
好奇なその瞳氏は、こう問われた。
「先生は、どうして、そんなに長く、このような離島で医療をされているのですか?何か良いことがあるのですか
?釣りがお好きなのですか?ダイビングでも?何か良いことが一つでもあるのでしょう?それとも都会が合わないのですか?」
「え??」私は、その矢継ぎ早の質問に上手に答えることができずに、目を伏せてしまった。
暫くして、彼は少し不満げに「大変そうですね」とため息をついた。
そういえば、医師として、この地、〇〇島に赴任して、はや3年数カ月の月日が流れた。
その前は?五島列島のU島(U町)いう所にいたっけ。
すでに4年間も、こういった環境に身を投じて来たことになる。
よほど好きなのね、と人は思うかも知れないが、特に島を志したわけでもなければ、とくに、思い入れが強かったわけでもない。
気が付けば、そこにいたと言ったほうが、何だか合っているようだ。
ただ一つ、思い当たる事といえば、大学入試の面接試験のこと、面接官「君は、どうして医師を目指そうと思ったの?」
受験生(私)「離島医療に尽くしたいと思ったからです」と、心にもないことを言って、面接官の心証を良くしようとした、立派?な受験生の過去は、あった。
そして月日が経ち、いつしか、立派?な島医者となっていたのである。
「U島の頃」
4年前の初夏、夕刻、懐かしい声の便りが届いた。
親友F先生からである。
「〇ちゃん(私)、元気?久しぶり・・・」
のやり取りのあと、あまりにも唐突なお誘いにおもわず息をのんだ。
「〇ちゃん、五島列島へ行かないか? 五島の診療所の医者が、急にやめることになって、とても困っているらしい」
「え??」「・・・?」「・・・?」
1か月後、私ら家族は、五島列島U島への船の中にいた。
船は、佐世保から出航する。高速船とフェリーである。
週のうち3日は直行便となり比較的短時間で着くとのこと。
それでも、各々2時間半と4時間半の航海である。
当日の五島の海は、ことのほか、穏やかで美しかった。
初夏のブルーと大小さまざまな島々なコントラスが眩しい光の中で耀きながら、私達の脳裏に焼きついた。
U島(U町)は、ほぼ円形のこじんまりとした島であった。
ただ、海岸線のえぐられた岩肌や断崖は、自然の厳しさを感じるほどのまさに絶景であった。
人口約4千人、平の某(なにがし)、のゆかりの地らしく、人々は自負と力強さを、どこかしらに、漂わせていた。
港に並ぶ漁船は、皆みごとで誇らしげに、色とりどりの旗をなびかせて、出港の時を今は遅しと待っていた。
一隻で、家1~2軒は、平気で建つと案内してくれた診療所の事務長は、誇らしげに語っていた。
港を中心とした街は人々で賑わい、あわび、うになどの豊かな海産物の恵みをうけた、裕福さが伺われた。
実は、この家二軒分おn豪華な代物が、以後の私の欠くことのできない右腕となるとは、このときは、想像だにしてなかった。
U町国保診療所は、本院(CT、内視鏡、エコー等設置(19床)と分院(無床)の2院で運営されていた。
引継ぎの際、本院には、前院長を含め2名の医師が勤務していたが、故あって2名とも退職することとなり、本院勤務は、結局私1人であることを知った。
分院には、高齢の外科医が働いていた。
以後、U町4000人は、2名の医師でみるはめとなった。
診療所勤務は、それなりに忙しかった。
日中外来は100人を超えることも少なからずあったし、夜間といえども、毎日数人の外来患者があるため、まる一日束縛される日が続くこともあった。
月に最低10回程度は、救急隊員と対面するため、19床はほとんど満床か超過状態であった。
他にも訪問診療、老人ホームの嘱託医、検診、予防接種の業務もこなさなければならなかった。
「患者搬送のこと」
離島医療にとって搬送業務は、重要課題である。
U町での生活に暫く慣れた頃、夜中の2時を少しまわっていたであろうか。
降ってきそうな勢いの満天の星と手を伸ばせば届きそうな満月が我々を包みこんでいた夜、この静寂を一掃するかの如く、突然けたたましいサイレンの音がわれわれの眠りをさまたげた。
60歳男性、夜中トイレで倒れている所を家人に発見されたとのこと。
手慣れた隊員は、気道確保、心マッサージを施行しながら、その男性を搬送してきた。
JCS(300)、脈触れず、自発呼吸はし。DOA、CPR開始。
約1時間の悪戦苦闘の末、血圧、呼吸再開も不安定。
レベル変わらず、深昏睡。
縮瞳したまま。
既往歴特に無し。
Brain、CY,ECG、一般採血、検尿、特に著変なし、代謝性アシドーシス、何らかの中毒を疑わすが・・・こういう時にはこう考えているところでへたに時間を費やしてはいけない。柮速が一番と考えている。
とにかく早急に高次医療機関へVitalが安定している内に送り届けなければならない。
私はすぐにヘリによる患者搬送を要請した。
搬送先は、国立N中央病院とのこと。約束の時間がきても、一向にヘリの音すらしない。
こちらはVaitalを維持するのにハラハラしているというのに。
実はヘリは、強風で飛べず、風待ちだという連絡。
約束の2時間後、ようやく、私は肩の荷をおろすことができたのである。
その方は、後日亡くなられたのであるが、返書には、脳炎疑い(原因不明)、と書かれていた。
以後、数回、ヘリ搬送要請をした記憶があるが、その内半分ほどは悪天候で飛べないとの理由で断られた。
以後1カ月に、平均として10名程度は佐世保へ救急搬送したが、威力を発揮したのは、ヘリではなく、実は前述の、家二軒分の高速漁船なのである。
片道2時間、片道搬送運賃10万円(町もち)随伴看護師つき。
波が極端に高くないかぎり、彼らは私達の要望に答えてくれた。
どんなに助けられたことか。
どんなに患者さんが救われたことか。
「予期せぬ出来事」
8月も終わりの頃と思う。
五島にも、〇〇〇島と同じく台風はやってくる。
ニュースでは、その日の深夜から、明け方に五島直撃といっていた。
970ヘクトパスカル。
なんだ大きくないじゃん。
私はその小さな嵐を甘くみていた。
ニュースの予報のごとく、夕刻から風が徐々に強くなってきた。
各漁船は頑固なロープで港に繋がれ、万全の準備を整えていた。
海上はすでに、5メートルを越す大しけとなっていた。
深夜私に緊急のコールが鳴った。
「先生、お産です」「何?」
「陣痛が始まりました。」
実は臨月に近いその妊婦は、出産前の定例?の墓参りに島に帰省していたのである。
(何もこんな時に、帰省しなくても)私は少し苛立ちながら、診療所に向かった。
25歳経産婦。
私と対面したその気丈な婦人は、少し不安な表情に中にも、この際ここで産んでやるといった強い意志をにじませていた。
38週。陣痛感覚10分、破水なし。
こともあろうに、1年前に第1子を帝王切開にて出産しているというではないか。
その下腹にはまだ新しさを窺わす切跡が鮮やかに残っていた。
CPDは?前置胎盤は?
早剥は?
子宮切開部は大丈夫だろうか?
いろいろな不安が脳裏に出没した。
今なら搬送できるかもしれない。
搬送できるならそうしたい。
漁船なら出てくれるかも。
手を尽くしお願いしたが、この嵐の中、あえて自分の命を危険にさらす人はいない。
付き添う看護師も危険だ。
ヘリはもちろん飛ばない。
そうこうしている内、一人の小柄な老女が訪ねてこられた。
妊婦の母親である。
私は、事の経緯を説明した。
陣痛が始まったこと。台風で搬送できないため、ここで出産するしかないのだが、帝王切開既往で、経腟分娩の際、リスクが高いかも知れないこと。
緊急帝王切開の可能性。
最後に、私が「内科医」であるということ。
彼女は、私の弁解にも近いムンテラを静かに聞いた後、少しため息まじりにこう言った。
「仕方ありませんね。」「すべて、先生におまかせします。」
深々と頭を下げられた。
私は、この小さな母の物腰に感動した。
いざという時の腹の決め方の潔さは、この厳しい環境に耐え続け培われた賜物なのか?
私の腹も決まった。
とにかく最善を尽くそう。
外では、風雨がさらにその力を増していた。
DOUBLE sat up(軽膣分娩中も、帝切の可能性を考慮し、両方の準備を調える)を指示した。
残念ながら、分院の外科医の先生に協力をお願いしたが、帝切の経験がないとの事で断られた。
以後の10数時間は、本当に大変だった。
忘れもしない。手持ちの産科、小児科の本をかたっぱしから読み漁り、一方では患者さんと児の経時的状態の把握に努めた。
カイザーに関しては、余り気のきいた内容ではなかった。
第一後頭位。2800g。 Apgarスコア10点。
元気に泣くその女児をこの手に抱いた時、私の目には涙が滲んでいた。
何とか無事に終わった。
寸暇を惜しまず、最後まで助けてくれた看護師さん達、本当にありがとう。
そして私は神様に感謝した。
すでに嵐は通り過ぎていた。
「最後に」
人には、それぞれのいろいろな場面で、潮時というものがある。
U町での生活もそろそろ潮時かなと、考えてた時、思いもよらぬ方からの声の便りがあった。
T病院(グループ病院)の理事長からであった。
以来、K病院に来て既に3年余が過ぎた。
この窓からいったいどれくらい、潮の満ち干を見てきただろう。
潮時という言葉がふと胸をよぎる。
K島の医療に関しては、この場で言及することは避けようと思う。
ただ、どこの離島(僻地)医療でも同じであろうが、数多の人々の苦難と希望の末に、成り立って来たということである。
K島も例外ではない。
これに関しては、故田畑福栄氏監修(K島、無医地区からの脱却)をご一読下さればと考えている。
先日、とうとうパソコンを購入した。
それは良いが一向に上達しない。
何とかインターネットが開けるが、身内との電子メールのやりとりができるようになった程度である。
それにしても便利な世の中になったものだと思う。
世間ではIT革命などと盛んに叫ばれ幾多の情報や経済取引に至るまで、気が向けば瞬時に我が手元に届けてられる。
今や、意思(意志)に時間的隔たりは無くなってきたと言うことであろうか。
例外に漏れず、離島である、この地K島でもインターネットぐらいはできるのである。
そういえば、前院長も嵌まってたっけ。
一方、相変わらず物理的隔たりは、未だ厳然としてある。
我々は依然としてこの隔たりに毎日翻弄されている。
人間はEメールでは運べない。
いかに情報が瞬く間に行き交おうと、悲しいかな、やっぱりここは離れた島なのである。
最後に、不平不満の多くも言わず、わりと黙ってついて来てくれた嫁さん、子供達に。
私の理不尽とも思える指示にも淡々と協力してくれているK診療所のスタッフの皆さん。
行き届かぬ診療を甘んじて受け入れてくださる患者さん達に。感謝の気持ちを込めながらこの文章を終わらせていただきます。