1 「自分を生きる」という最大の自由
肉体があることで自由を失うように思いますが、この現実世界そのものを楽しむと決めて、肉体と魂を固定させることで、「自分を生きる」という最大の自由を得ることができます。生きていていいのです。
肉体はいずれ土に還るので、この与えられた肉体で地上を堪能できる時間は限られています。だから身体感覚を敏感にして肉体の声に耳をかし、エネルギーを「生きる」ことだけに向けます。
その為には理想論や精神論を語るだけでなく、現実に対処していくことです。始めなければ何も変わりません。
理想を現実的な方法で叶えていく為に今を大切にすること、自分や大切な人を大切にしていくこと、今できる事をするだけです。
今を生きるエネルギーは、確実に成果を上げることを目的にしているので、努力することの大切さを知っています。つまり、現実という物質世界を努力で改善していきます。

2 病気は自己表現
病気とは自己表現であり、病気は自分の内側を映す鏡にもなります。
本来の痛みや苦痛は身体の変化の動きの指標として大切であり、それ以上に身体に負担をかけ過ぎないようにするための信号です「痛みや苦痛を感じたら。それ以上無理をしない」というのが生き物としての原則です。
病気をネガティブなものと決めつけていないで、病気や身体の不調にはまだ発見されていない才能かもと考えてみましょう。
感情と思考と行動の掛け算が人生を作っています。そこから病気は潜在意識を具現化して、大切なことを教えてくれています。
さらに潜在多岐な欲求を心の成長として転換できたなら、そこにはきっと眠れる才能が待っています。
そのヒントが「痛い」です。痛いのは身体なのか、感情なのか、今の自分自身なのか、今の生き方なのか、仕事、人間関係が嫌なのか、それを痛いと教えてくれています。

3 病気は、探し続けた自分らしく生きる答え
病気やコンプレックスこそが、自分の追い求めていた生きるための答えになります。
さらに、人生で受け取るものの量と質は、あなたの「ありがたい」という気持ちに比例しています。だからこそ、身体を「ありがたい」と思いながら、癒しや運動をしていきましょう。
・筋肉は心なので、「ありがたい」を感じながら病気や痛みを解除します。
・骨は自分自身なので、自分を受け入れる器や精神的な器を固定させ土台をつくり、自分を受け入れ本来の自分になります。
・内臓は魂なので、夢を叶えるためだけに生き、生きていることを五臓六腑に染み渡らせます・

4 さあ、お薬体操をはじめよう
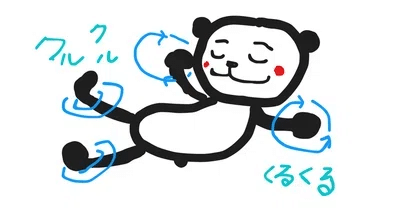
腰痛・背痛
主な原因は脊椎の変位、筋肉の病気、内蔵の異常や癌による腰背痛もあり、腰痛原因は多数あります。一般的な腰・背痛は、主に歪みを直し正しい姿勢を整えます。体操と一緒に呼吸法で腹圧を高めたり内蔵を強化して、便秘や内蔵下垂をなくすようにしましょう。
腰痛は、腰が疲労するところから始まります。腰が疲れ、周辺の筋肉に弾力がなくなると「重い」という感覚がでてきます。そこで腰のバランスをとるために、体重を支えている足首や首に負担がかかり、緊張が増えます。
さらに足首や首の筋肉の弾力がなくなると、肺や後頭部に負担がかかります。そして、集中力が目に見えてなくなり始めます。
また、ストレスと上手に解消し、内蔵に負担をかけないようにしましょう。腰が痛いときは、お腹にもトラブルが出てきます。
◆ぎっくり腰のお薬体操
身体に痛みがあるとき眼球が敏感に反応してかたくなっているかもしれませんので、眼を包むように目を温めて神経の興奮がおさめます。お腹を温めることで、内蔵の働きが高まり痛みが和らくかもしれません。
痛い場所を中心に温め、痛みがひいて足の指が動かせるようになったら、つま先を前後、左右に動かしてみましょう。腰に痛みが出るとわき腹の方まで硬直させ天然のギブスを作るといわれていますので、深い呼吸を繰り返しながら側腹を緩めていきましょう。
◆座骨神経痛のお薬体操
痛くない方に30回膝を倒します。運動不足や睡眠不足、特に、冷えに気をつけましょう。
◆椎間板ヘルニア
腰が捻れをとるように、前後屈運動、体を左右に捻る運動をしましょう。
胸椎が原因の場合もあるので、胸を動かすことを意識しなら運動をしてみましょう。
◆腰の上の方が痛い時のお薬体操
お尻の真中、腰の下のほうが痛くなる症状です。膝が内側または外側に向いているために、仙腸関節に負担がかかって痛みます。脚の動かし方や歩き方が原因かもしれません。
膝の開閉運動、強制呼気、膝を交互に引き付ける、股関節回しをしましょう。
◆腰の下の平らな部分が痛い時のお薬体操
腰のやや上、腰あたりが痛いタイプは、同じ姿勢が長く続いたり、後ろに振り返りづらい人、床に座ると脚を伸ばして座るのがつらい方などに多く見られます。また、ウエストが太いのが気になる方や、腰椎の湾曲が減少している方、背中が痛いのか、腰が痛いのか分からない方もいます。
腰と肋骨をつなぐ「腰方形筋」が縮んでいるかもしれません。腰方形筋は骨盤の安定と、身体を横に倒す時に使われる筋肉です。コアがうまく働いていないことが多いです。
肋骨と骨盤の間に指が3~4本入らない場合は、コアが弱くなり、腰方形筋が硬くなっているかもしれません。膝を内側に倒す体操、お尻の引き締め体操をしましょう。
◆腰の奥が痛い時のお薬体操
大腰筋と腸骨筋からなる「腸腰筋」の緊張があるかもしれません。腸腰筋は脚を持ち上げる時に使う筋肉で、特に大腰筋が弱いと姿勢が崩れて歩行がうまくいかないといわれています。
大腰筋を鍛えるという考え方もあるのですが、実は大腰筋が緊張しているために、股関節の緊張しているのだ、股関節の動きが悪くなり、腰痛をひきおこしている場合が多いのです。
脚をトントン・クルクル体操、かかとユラユラ体操をしましょう。
◆ストレスによる腰痛の時のお薬体操
後頭部のマッサージ、お尻や太ももの裏を伸ばします
肩こり
肩がこると首がかたくなり、うっ血し、頭部に充分血液が行きわたらなくなり、心理的にも影響します。目・耳・鼻・脳などに異常が生じ、首を通る自律神経と内蔵の関係もトラブルが生じているかもしれません。
肩、首そのものを柔軟にする動作と、お腹に力を入れる動作をメインとし、肩の力が抜けるように、両手を真っすぐ伸ばして捻ります。
首と、手・足首は関係しあっているので、手・足首の柔軟性も重要です。足首のトラブルが出ると、丹田から力が抜け、肩に力が入り、顎がでたり、首が曲がったりするので、常に足の親指に力をこめ、アキレス腱を伸ばして足首を正常に保つことが重要になります。
首の曲がりを正すため、首と胸の筋肉の萎縮をとり、柔軟にさせましょう。頭骨の下垂からくる首の曲がりを正すため、縫合部を絞める刺激を与えます。
一般的な肩こりは、腕を身体の前で常に使い、肩回りが緊張することからおこります。肩こりは腰の力が弱くて肩や手首に力が入っていることもあります。
前屈や身体のねじれ、内蔵のトラブルがある人は肩こりが起こりやすいかもしれません。不安やイライラによる緊張でもおこります。
◆肩こりお薬体操
ヨーガの、アーチのポーズ、ねじりのポーズ、回旋運動をしましょう。
◆肩の位置、胸椎のゆがみによる肩こりお薬体操
肩甲骨寄せストレッチ、背中や二の腕を伸ばす、ヨーガのスキのポーズをしましょう。
◆肩甲骨の間が痛い時のお薬体操
背中も一緒に痛くなるタイプの肩こりです。
背中が疲れると、呼吸も回復しません。呼吸運動が苦手で、肩甲骨の間の筋肉が弱いために、腕を動かす際に肩を持ち上げてしまう動作をしてしまい背中の上部の筋肉を緊張させています。
また、腕の動きにつられて、肩甲骨は外側に離れがちになります。
肩甲骨を背中に安定させる筋肉が硬くなりますが、この筋肉は胸にあり小胸筋が胸を硬くします。小胸筋をマッサージ、ひじの引き寄せの体操をしましょう。
◆腕が上がらない時のお薬体操
硬くなった筋肉は、靭帯までも緊張させ、腕を動かさなくします。
鎖骨、液化リンパ節のマッサージ、肘下を回す体操をしましょう。
◆痛みのある肩こり時ののお薬体操
首の付け根がこっているので、肩を上げたり、首をすくめたりする肩甲挙筋が硬くなります。肩全面が凝っている方は筋肉を支える筋肉が硬くなっているかもしれません。
肩甲骨が定位置に維持できないと、バランスを取るために腸骨が下がり骨盤が開くようになることもありますし、また逆もあります。
肺の弾力があると肩甲骨は元にもどり、呼吸も深く、精神状態も安定します。
鎖骨下のマッサージ、僧帽筋を押しながら肩を回す、脇を伸ばしましょう。
◆内蔵が原因の肩こりのお薬体操
ヨーガによる、さか立ちのポーズや逆さかだちのポーズをしましょう。
◆食べすぎによる肩こりのお薬体操
食べすぎが続くと左の筋肉が緊張し、右の僧帽筋が引っ張られるため右の肩こりとして現れる場合が多くあります。
内臓のマッサージ体操、肩甲骨の開閉体操、肩に蒸しタオルをしましょう。
◆注意する肩こり
左肩に偏って肩凝りがあり、締め付けるような胸の痛みがあるとき・・心筋梗塞、狭心症のことがあります。
右肩に偏って肩こりがあり、みぞおちや背中に強い痛みを感じる時・・・胆石症、胸膜炎、食道炎のことがあります。
肩こりと同時に痛みがあり、咳をするとその痛みが激しくなるとき・・進行した肺炎などの呼吸器の重い病気の場合があります。
首コリ
◆首のこりのお薬体操
首の歪みをとるストレッチと、アキレス腱を伸ばしましょう。
頭の過敏の状態で心理的な要因、身体の部分的な疲労、腕の使いすぎ、腰の疲労などから、腹部や腰背部の弾力がなくなると首に負担がきます。
首-首の関係として、腰首-首-手首-足首があります。
肺に長期にわたり負担がかかると、バランスが崩れ少しの労働でも首がはります。肩こり体操、手と手首の体操、胸骨体操(腸骨に力を集め、肩から首の緊張をゆるめる。)
◆首が回らない時のお薬体操
首を両手で包み、首を横や立てに動かす。さらに顎を上げて首の前側を伸ばしていきましょう。
◆首から背中のこりの時のお薬体操
背骨が捻れているのが原因かもしれません。腰をたたきながら、前屈をしていきます。
◆疲労からくる首こりの時のお薬体操
胸鎖乳突筋が疲労すると呼吸がうまくいかなくて、酸素の供給が減り、横隔膜の動きが悪くなり、疲労がとれにいのかもしれません。
胸鎖乳突筋のマッサージ、腹横筋の呼吸トレーニングをしましょう。
◆頭痛を伴う首こりのお薬体操
うつぶせから、頭を持ち上げて元に戻す体操をしましょう。
膝痛
◆膝の関節が痛む時の体操
腰で体身体を捻れなくなり無意識に膝を捻る為、膝は捻るように作られていないので関節が痛んでいるのかもしれません。
また、ストレス、過食、腎臓機能の低下などが原因として痛む部分をお風呂で動かします。
膝の痛みは交感神経を緊張させるため、痛む膝を同じ側の眼球が固くなっていることも多いので、目を温めてみましょう。
力を抜くことができず、筋肉が硬直を起こし変形を起こしている場合は、脚の裏の筋肉を伸ばす、脊椎を緩める体操をしましょう。
◆膝のお皿の周りが痛い時のお薬体操
慢性的に膝が痛いときは、膝のお皿が変形している場合が多いようです。お皿の変形は、クッションの役割をする軟骨がすり減っておこります。
一部の筋肉だけを酷使する癖が積み重ねられ、変形が招いた可能性があります。筋肉を使えるようになると、変形の改善はできませんが、痛みがなくなるという機能の改善が多くみられます。
膝の裏のマッサージ、腰骨・膝・足の人差し指が一直線になるように膝を曲げ伸ばし体操をしましょう。
◆膝の裏が痛い時の体操
膝裏のツッパリ感、曲げにくさ、伸ばした時の痛みは、立ち仕事の肩や歩くのが少ない、足首をうまく使えずに歩く方に多くみられます。
膝裏のしっかリンパ節の下肢の老廃物がたまって、ふくらはぎやももの裏が硬くなっていかもしれません。
足首にストレッチ、ふくらはぎと膝裏のリンパ流す、指先の上げ下げ体操をしましょう。
◆膝がうまく伸びない時の体操
歩く時や立っている時、常に膝が曲がっているかもしれません。曲がっているというより、ゆるんでいる感じ、足首をうまく使えていないかもしれません。
また、膝に障害をもつ多くは、膝の使い方の癖が多いようです。
特に女性は筋肉が弱くなりがちで、ももの前側と後ろのアンバランスが膝に影響を及ぼします。
昔は、正座や和式の便器で膝に負担をかけすぎていたことが原因でしたが、今は歩かなくなったことが原因と考えられます。
太ももの裏のマッサージ、ストレートカーフレイズをしましょう。
股関節
◆股関節が痛い時のお薬体操
骨盤が下がると踵の重心が、瞬発力があると体重が前にかかります。
足の親指は頭の急所で、頭の緊張が続くと親指に余分な力が入り、つまづきやすくなります。
二点、一点しか力がはいらなく、趾骨や趾骨間に問題を抱えていて、歩けない、走れない、踵をひきずってあるくので、やがて踵に痛くなります。
これは骨盤が下がっているためにおこり、長時間立てないので、すぐに横になったり、座ります。
脊椎を緩める体操、お尻歩き、股関節回しをしましょう。
肘
◆肘が痛い時のお薬体操
糸まきまき体操をして、腕をブラブラする体操をしましょう。
肘には主か吸収に関わる経絡が通っているので、肘が痛むときは体の不調が隠れていることがあります。
右肘は、肝臓の不調や痔
左肘の痛みは、膵臓の疲れや食べすぎのサインかもしれません。
手首
◆手首が痛い時のお薬体操
手首をくるくる回し、手をブラブラする体操をしましょう。
頭痛・偏頭痛
脳内に異常(脳腫瘍等)がある以外は、首の凝りや、内蔵の異常、体の歪みや頭蓋骨下垂等が原因かもしれません。
直接的には脳内血管の異常緊張が痛みを起こすのがほとんどです。(大半は血管痛であり、頭皮がたるみ、首がこわばり、頭蓋骨の縫合部がゆるんでいる可能性があります。)朝起きた時に、頭が痛いなら、肝臓が疲れている可能性もあります。
片頭痛は、頭の血管の拡張が原因でおこります。こめかみや目の周りが痛くなり、ズキンズキン、ガンガンと脈打つように感じます。
光や音に敏感に反応し、頭を動かすと痛んだり、嘔吐をともなうこともあります
。
群発性頭痛は片頭痛によく似ていますが、片目の奥がえぐられるように痛く、吐き気はなく、季節の変わり目にあらわれるのが特徴です。
緊張性頭痛は、後頭部から首筋にかけて痛みます。肩こり、姿勢不良など筋肉の緊張で血液循環が悪くなって起こります。
温めると楽になるのが特徴です。
◆頭痛のお薬体操
頭痛予防のため呼吸は、吐く時に、ゆっくりと力まずに息を吐きます。首周りの筋肉のマッサージ。
◆片頭痛のお薬体操
身体の歪み、また痛む部分との関連した内蔵の異常が関連している可能性もあります。関連した部分を良くすることも大切です。
脳と腹部の関連は、
前頭部は、胃、肝臓、心臓と関係します。
頂頭部は、肛門、生殖器と関連します。
側頭部は腸と関連します。
後頭部は、腎臓と関連します。
肩や首の凝りをとり、頭蓋骨の弛みを締めて下垂を正す方法を中心にした、ヨーガのさか立ちや逆さかだちの体操をしてみましょう。
◆頭の疲れた時のお薬体操
ヨーガの逆立ち、胸を張って手を組んで手のひらを外に向けながら伸ばす体操、アキレス腱を伸ばしたり、足首を回します。
耳の後ろの骨の内側を押して血流をよくします。
耳と鼻
◆耳・鼻のトラブルのお薬体操
耳と鼻に異常がある人の共通している体型は、重心がかかと、小指側にかかり、足に長短があり、足首関節も固く、腰に力なく捻れていることです。
また骨盤開閉力に左右差があり、恥骨と顎が前に出て、猫背で肩が凝りやすい特徴もあります。
◆鼻の異常がある時のお薬体操
首が捻れ鼻の血行が悪く、粘膜に炎症を起こして化膿していて体が左右アンバランスかもしれません。恥骨を下げる動きと、首の捻れをとる動きを中心に体操を行いましょう。
◆鼻がつまった時のお薬体操
恥骨が前に飛び出し、踵に重心がかかり、側腹部がかたいかもしれません。前後屈、左右に体を倒すなどの運動をしましょう。
婦人科トラブル
腰の捻れ、骨盤の歪みや開閉のアンバランス、冷えなどが原因かもしれません。
下肢部のうっ血や便秘、臀部のたるみをとりましょう。
腹部の力がない人が多いので、足腰を鍛えることも大切です。
感情の不安感や混乱も大きく影響するので、心の安定も必要です。
◆生殖器に異常がある時のお薬体操
流産しやすい人、月経痛の人は腰が捻れているかもしれません。
つわりのひどい人、不感症、早漏の人は捻れとともに、骨盤の開閉力が弱く、腰と臀部の力が抜けている可能性があります。
ヨーガの、ねじりのポーズ、弓のポーズ、アーチのポーズ、バッタのポーズ、前屈のポーズをしましょう。
◆月経異常の時のお薬体操
腰が捻れている場合が多いので、前後屈運動、体を左右に捻る運動をしましょう。
◆生理痛、PMSの時のお薬体操
生理時の骨盤の開閉をスムーズに調える為に、うつぶせで寝て両足の裏を合わせたら上半身を起こす体操をしましょう。
足首や腰椎の緊張を調える為に、立ったまま足首を回していきます。
◆生理不順のお薬体操
仰向けに寝て、下腹に両手を置いたまま深呼吸をしましょう。
◆生理中の胸の張り
骨盤の開きすぎを改善し、子宮の緊張を和らげるように、大の字で寝て身体を伸ばす体操をしましょう。
風邪
◆風邪を引きやすい時のお薬体操
風邪ひきの原因のひとつに、筋肉の凝りと脊髄関節の縮みもあります。
身体の捻れや前屈の人がかかりやすいかもしれません。
ヨーガで、捻るポーズポーズ、アーチのポーズ、前屈のポーズをしましょう。
◆セキのでやすい人のお薬体操
手、足、肩、胸が萎縮しているかもしれません。
または、腰から下に力が入っていないのかもしれません。
ヨーガのネコ、弓、バッタ、コブラのポーズをしましょう。
◆セキこんで困るときのお薬体操
胸、肩、首が張り、胸がうっ血しているかもしれません。
胸を張っての後屈、肩や首をまわす運動をしましょう。
◆免疫力が弱く風邪をひきやすい時のお薬体操
免疫力を高めるために、仰向けに寝て身体を左右に捻じる体操をしましょう。
◆風邪のひきはじめ
肩甲骨の間をカイロなどで温めましょう。
◆せきの時のお薬体操
足湯をしたり、小食、甘いものを控えましょう。
◆くしゃみ、鼻づまりの時のお薬体操
特につまっている鼻と同じ側の足で、お尻をトントン叩く体操をします。
◆喉が痛い時のお薬体操
風邪をひくと喉が腫れたり、痛んだりしや場合は粘膜の働きをよくするため、仰向けで胸を張り、肘で床を押さえる体操をします。
さらに内くるぶし周辺をじっくりマッサージします。扁桃腺は腫れている時は、手首を回したり動かして、手首のバランスを調整します。
睡眠
◆睡眠障害のお薬体操
眠れないのは、身体・心・生活の中に邪魔する刺激があるからかもしれません。
早く良く、深く眠るためには、筋肉がゆるみ呼吸が静かになり、副交感神経が優位になっている状態が必要大切です。
肩、首、上背部、胸の緊張をほぐし、骨盤をゆるめましょう。
◆いびきのお薬体操
首と腰が捻れて、首の筋肉がこわばりすぎるか、たるみすぎているかもしれません。
ヨーガのねじりのポーズ、ネコのポーズをしましょう。
◆寝不足を感じる時のお薬体操
後頭部を上に向けてたたき、膝を左右に開く屈伸運動をしましょう。
◆眠りにくい時のお薬体操
胸から上の力が抜けずに手足の血行が悪いかもしれません。
深呼吸とか後屈運動をしましょう。
◆不眠のお薬体操
自立神経を整えるように、骨盤グーパー体操をしましょう。
自転車こぎで、下半身の血行をよくして、体の冷えを解消しましょう。
◆寝つきが悪い時のお薬体操
頭の疲れをとって、眠りに入りやすくするようにアキレス腱を伸ばしましょう。
◆眠りが浅い時のお薬体操
仰 向けで寝て片足の腿の前を伸ばすように膝をまげ、足を曲げているほうに首を向けましょう。
◆昼間に眠たくなる時のお薬体操
昼間に眠たくなる時は骨盤が後ろに傾いて、猫背になっていることが多いようです。
頭を軽くトントン叩いて血行をよくしましょう。
◆朝、起きられない時のお薬体操
腕を上げて胸を開きながら、股関節を回しましょう。
足
◆足がしびれたり、つりやすい人のお薬体操
こむら返りを起こしやすい人は腸骨が捻れているかもしれません。
足のしびれやすい人は、捻れと同時に、腰の力がなく、足首がかたくアキレス腱が縮んでいるかもしれません。
ヨーガのツイストのポーズ、アーチのポーズ、弓のポーズ、魚のポーズをしましょう。
足がつりやすい人は、心臓が弱っている可能性もあるので、気をつけましょう。
◆足がだるいのお薬体操
腰腹の力がなく骨盤が開き、体重を踵にかけているので足首が開きアキレス腱が縮んでで血行が悪くなっているかもしれません。
ヨーガの前屈のポーズ、バッタのポーズ、アーチのポーズをしましょう。
◆足のむくむ時の薬体操
内蔵の低下してきたのが原因かもしれません。内蔵の働きを活発にして、水分の代謝をスムーズにするように、足のマッサージで老廃物を排泄しやすくしましょう。
◆外反母趾時のお薬体操
内転筋を伸ばすようにマッサージ。足の指を広げてマッサージ。股関節や脊椎を緩める体操
捻挫
◆捻挫のお薬体操
足を捻挫した時は、体も捻じれているかもしれません。右脚を捻挫した時は、体が右に、左足は左に捻れているかもしれません。
仰向けに寝て膝を曲げ、股関節内外旋の運動。アキレス腱を伸ばす体操。
視力異常 疲れ目、近視、乱視、老眼の改善
眼の異常はたんに眼だけではなく、内蔵、筋肉、血液、呼吸のトラブル、心の緊張など心身生活全体のトラブルと関係しています。
慢性病の一つなので、眼だけではなく、心をリラックスすることが大切です。
手や肩・首に力が入ると眼にうっ血が生じ疲れやすいので、特に手・肩・首の力を抜く体操をしましょう。
視力異常の原因は直接的には肉体的こり及び精神的緊張による眼球および関連筋肉の萎縮効果による変形とうっ血からおこっているのかもしれません。
近視には軸性(うっ血性)と屈折性(硬化性)の二種類があります。
軸性は血液の酸性化とうっ血、屈折性は毛様筋の効果が原因かもしれません。
◆視力異常 疲れ目、近視、乱視、老眼のお薬体操
斜視の場合は、首の捻れ、皮膚のたるみ、肩甲骨の高低を改善しましょう。
乱視の場合は肩の高さ、腕の強弱を改善しましょう。
老眼は老化現象がなので、老化を防ぐ体操をしましょう。
◆目がチカチカする時のお薬体操
まぶたマッサージと、肋骨を温めるようにマッサージしましょう。
◆まぶたが痙攣する時のお薬体操
首のストレッチと、こめかみに圧をかけるマッサージ、へその下を温めるようにマッサージすることで、自立神経の中枢となる太陽神経ソウがり、温めることで交換神経の興奮が収まり、緊張がほぐれ痙攣をおさえます。
◆まぶたの下垂の時のお薬体操
首の付け根をトントンマッサージと、ウエストを押さえながら腰振り体操をしましょう。
胃
◆胃が弱い時のお薬体操
上がった肩は下げ、下がった方の肩は上げるようにしましょう。首筋の筋肉を柔らげるようにマッサージしましょう。
◆食欲不振や食べすぎの時のお薬体操
身体を後ろにそると胃が働きだすようです。
また額を押すか、軽くたたくと胃の働きを抑制できます。
◆食欲がない時のお薬体操
短い時間でも身体を動かしましょう。
寝るときには、右脚を上にして休むと、胃の緊張がとれて、食欲が回復します。
◆胃もたれする時のお薬体操
両手をバンザイして、椅子にもたれて腰を伸ばす運動で、胃の位置が正しい位置に戻り、消化をよくしていきましょう。
◆胃・十二指腸潰瘍の時のお薬体操
頭の疲れやストレスを取り除くことが一番大切です。
みぞおちを押さえながら身体を捻ります。
◆腹痛時のお薬体操
強く深く息を吐き出しながら、できるだけ前屈します。しばらくその状態で体を止めたのち、息を吸いながら体を後屈することを数回繰り返します。片 方の足が短くなっていたら、その方の足を伸ばす運動をしましょう。
◆内蔵下垂のお薬体操
胃や腸、腎臓などの内蔵が下垂している人は、猫背で腹の力が抜けた体型になっているのかもしれません。運動不足や神経疲労の場合も、内蔵下垂になりやすく、またこの体型が精神的に無気力にする可能性があります。
下垂体質の人は、腹力・腕力が弱く足の裏の筋肉が縮み体重が外側、特にかかとに体重がかかっているかもしれません。
腰腹部の筋力を高め、内蔵の血行を良くしましょう。肩首の力を抜き、内蔵の位置を正しい位置に保つようにします。
冷え
◆手足が冷える時のお薬体操
指立ち体操で足の筋肉を高め、血液をすみずみまで押し出すポンプ機能を高めましょう。
肩甲骨回しで血流をよくします。
◆お腹が冷える時のお薬体操
肘立て腹筋で腹直筋を鍛えましょう。V字腹筋で手を上げ下げして、胃を強化しましょう。
◆足先が冷える時のお薬体操
カーフレイズでふくらはぎの筋肉をつけましょう。
鼠径部を刺激しながらスクワットをしましょう。
◆腰と背中が冷える時のお薬体操
腰を持ち上げ体操で、背中全体を刺激します。
肩甲骨を寄せてゆがみを調整する体操をしましょう。
◆お尻が冷える時のお薬体操
立ったまま、踵でお尻をトントンたたく体操をしましょう。長座前屈のストレッチ。
◆太もも、足が冷える時のお薬体操
腿上げ筋肉トレーニング、肩ブリッチで太ももを伸ばすストレッチをしましょう。
◆耳や顔が冷える時のお薬体操
ツイスト腹筋運動、逆腕立て腹筋をしましょう。
◆肩や腕が冷える時のお薬体操
腕ふり体操、合掌で腕のストレッチをしましょう。
◆のぼせ、ほてり
東洋医学では、のぼせやほてりは本来は丹田にあるべき気が上がった状態と考えます。
足首回しで頭に上がった気を下げましょう。
◆寒冷じんましんの時のお薬体操
体に捻れがあると寒冷じんましんが出やすいようですので、ツイスト運動をしましょう。
自律神経を安定させるように、へそをマッサージします。
便トラブル
便秘とは、腸の異常から起こるものと、肝臓や胃などの腸以外の異常からくるものもあります。
また、便秘が他の異常を引き起こし、悪循環になっている場合があります。
便秘は万病のもとといえるので、全体的観点かその原因や処理法などを見なくてはいけません。
◆便秘の時のお薬体操
手の親指の付け根をもんだり、頭頂を軽くたたいたり、腰を左右に激しく捻る運動。ケンケンの体操をしましょう。
◆下痢、軟便の時のお薬体操
腸のぜん動運動が盛んになりすぎて、腸の粘膜から十分に水分を吸収できないかもしれません。仰向けに寝て両足を持ち上げ、両脚をポットンと落とす体操をしましょう。
下痢は体内の毒素を排出する働きもあるので、肛門がしみるような感じの下痢は薬で止めないようにしましょう。
◆緊張してお腹が痛くなった時のお薬体操
足の指の屈伸運動。親指を上下に動かす運動。
アキレス腱をしっかり伸ばしましょう。
その他
◆頻尿の時のお薬体操
腎機能を整えるように、長座ですわり両手を伸ばし左右に捻じりましょう。
左内ももの筋肉(内転筋)をリズミカルに揉み解すと、間接的に腎臓が刺激され、尿の出が安定します。
◆膀胱炎になりやすい時のお薬体操
腰が捻れて泌尿器の働きが低下しているかもしれません。
腎臓の働きをスムーズにするように、腰振り体操をしましょう。
◆乗り物酔いの時のお薬体操
身体が捻れ、左右の耳の高さが違っているかもしれません。
立ったままの捻り体操、耳が下がっている方の側頭部をやさしくなでおろすと、筋肉の緊張がとれて、左右のバランスがよくなります。
◆動機、息切れの時のお薬体操
肺や心臓の機能向上をするために、スクワットをしましょう。
◆血圧を安定させるお薬体操
足の裏を揉み解したり、両足の股関節をよく回す運動をしましょう。
◆体温が低い時のお薬体操
足腰を強くして代謝をよくするように、四股踏み体操をしましょう。
◆体力をつけたい時のお薬体操
腕上げスクワットをしましょう。
◆冷房が苦手な時のお薬体操
発汗の中枢で、体温調整できるように、四股踏み、腕上げスクワットをしましょう。
◆高血圧・脳卒中予防のお薬体操
首のストレッチ丁寧におこないましょう。
◆動脈硬化の時のお薬体操
首の付け根をトントンしながら、マッサージしましょう。左の肩甲骨を中心に肩甲骨ストレッチをしましょう。
◆アレルギー体質の時のお薬体操
皮膚に疾患がなければ、乾布摩擦で皮膚の表面を鍛えると、肺などの呼吸器が強くなり、体質改善に効果的です。
美容
◆シェイプアップをしたい時のお薬体操
ツイスト腹筋、うつ伏せで踵で骨盤トントン叩きましょう。
◆ウエストのくびれをつくるお薬体操
足を伸ばして、手を左右に振りながらお尻歩きをしましょう。
◆垂れ気味のお尻改善するお薬体操
骨盤が後傾すると、お尻が垂れて、猫背、ウエストも締りがなくなるので、足を前後に大きく振り動かしましょう。
◆バストUPのお薬体操
バストを両サイドから手でよせ、ぐっと持ち上げて深呼吸をします。壁についた腕立て伏せ。肝臓の機能を整えるために、右の肋骨を温めましょう。
◆太ももを引き攻めるお薬体操
骨盤トントン叩きます。前後のランジ運動をします。
◆ふくらはぎ、足首を引き締めるお薬体操
踵上げ下げ運動、アキレス腱のストレッチ体操をしましょう。
◆O脚を改善するお薬体操
骨盤の開きすぎと関係がある為、骨盤が開きすぎると、股関節も外に開きO脚になるかもしれません。
床にすわり、床から浮かないように膝を曲げる体操をしましょう。
◆ぽっちゃり顔を改善するお薬体操
骨盤を顔にみたてると、腸骨が頬、恥骨が喉や首の部分と考えます。骨盤のグーパー体操、頬上げマッサージをしてみましょう。
◆唇のゆがみを改善するお薬体操
恥骨と喉や唇と関係がふかく、恥骨が歪むと唇がゆがみ、声もはりがなくなるかもしれません。恥骨ほぐしのマッサージ。バランスの悪い方の手の中指をマッサージしましょう。
◆まぶたのむくみの時のお薬体操
仙骨をなでるマッサージ、肘回し運動をしましょう。
◆肌あれを改善するお薬体操
仙骨、首の後ろ、肝臓を温めましょう。
◆老け顔を改善するお薬体操
目をくるくる動かします。肌の老化には合谷を押して、表情筋を鍛えましょう。
◆肌のしわ改善のお薬体操
耳の周りのマッサージしながら、口を開けたり閉じたりしてみましょう。
◆肌の乾燥、たるみ改善のお薬体操
仙骨を温めたり、なでたりしましょう。
◆肌のしみ改善のお薬体操
左側の肋骨を温めましょう。
◆白髪、薄毛が気になる時のお薬体操
腎臓が元気にするように、体側のストレッチと腰振り体操をしましょう。
◆顔がむくむ時のお薬体操
顔がむくみがちな人は、腰が捻れていることも多いかもしれません。腰の捻れをとるように、ツイスト運動をしましょう。手の甲や手首を回す運動をします。
◆猫背のお薬体操
胸脊髄神経全般を活性化して、背中の歪み改善するように背中ほぐす。仰向けに寝て、膝を胸のほうに寄せて、腹圧をかける。
感情のお薬体操

◆プチうつのお薬体操
身体の固い所をほぐしたり身体を動かすと元気がわき、やる気がでてきます。
◆ヒステリーの時のお薬体操
ヒステリーの時は、骨盤がしまっていて開きにくく、みぞおちと首が硬くなっている可能性があります。
さらに前屈姿勢、肩の上がった姿勢などが加わると、つらい症状が出やすいかっもしれません。
あおむけに寝て、足の裏を合わせて胸を張り、足をできるだけ尻の下に近づけます。
ヨーガではスキのポーズや、逆立ちのポーズなどで首の筋肉をやわらげます。骨盤が締まりきりになっている可能性があるので、膝を左右に開く運動や胸を張る運動をします。
◆落ち着きがない時のお薬体操
肩、手、首に力が入っていて、足や腰の力が抜けているからもしれません。
四股踏み、座ったままで足をあげ、そのままじっとする体操をしてみましょう。足に力をこめて深呼吸しても落ちつきます。
◆不愉快なとき、怒りたいときのお薬体操
みぞおちと首、胸の筋肉が硬く、背中が凝っているのかもしれません。
前屈の姿勢になっているかもしれませんので、身体を前後、左右に体を倒す運動をしてから、深呼吸をします。
◆元気のでない時のお薬体操
腰がかたくなっていて、首に力がなく顎がでているかもしれません。
胸を張って顎をひきます。背中を伸ばして力のこもった呼吸を繰り返します。
◆イライラするときの体操
身体が硬直しているかもしれません。どんな体操でもいいので、身体を1分激しく動かします。その後で、左右に身体を倒しながら静かに呼吸をします。
女性の、生理前や更年期のホルモンバランスの崩れによるものは、仙骨をやさしくさすりましょう。
◆くつろいだ気分になりたい時のお薬体操
胸を張って体を揺さぶりましょう。筋肉が柔くなる身体も心も和らぎます。
◆雑念妄想が起こって困る時のお薬体操
胸を張って、首を後ろに倒しましょう。
◆陰気な気分で何もする気が起こらないときのお薬体操
アキレス腱が縮んでいるかもしれません。足を前後に開き、アキレス腱を伸ばす運動をしましょう。
◆決断がつかずうろついている時のお薬体操
足と腰に意識的に力を入れましょう。
◆悲観的なときのお薬体操
胸の力の抜けたネコ背をしているからもしれません。胸を張って肩を下げ、腰と腹に力を入れる体操をしましょう。
◆こわい時のお薬体操
胸を張って、股を大きく開き、膝と足の親指に力を入れましょう。
◆不快な気分が続く時のお薬体操
副腎ホルモンが出すぎて他のホルモンの働きがにぶっているかもしれません。
立ったままで、両手を後方にまわし、片方の足をあげてその足首をもち、腰が反るように力を入れましょう。
◆不安な気分が続く時のお薬体操
腎臓の働きがにぶっているかもしれません。後屈運動をしましょう。不安や心配は、腰を意識した腰振り運動をしましょう。
◆自律神経失調症のお薬体操
自立神経を整える為に、仰向けで寝て身体を捻じる体操と、へそを回して熟睡で疲れをとりやすくします。
◆パニック障害のお薬体操
仰向けで膝を曲げて足首をもち、頭をあげていきます。
◆呼吸障害のお薬体操
呼吸筋群の収縮力を高めて肺に入る空気力を増やし、肺内部の喚起効率を高めて、肺胞がより新鮮な空気をいつも接することができるよう、胸腹部の呼吸筋をマッサージして萎縮をとり、血行を良くしましょう。
◆仕事を始めるとすぐに疲れる時のお薬体操(首コリうつ)
首が捻れて硬くなっているかもしれないので、首を反対方向に捻じります。首のマッサージ、前後屈運動をしましょう。
