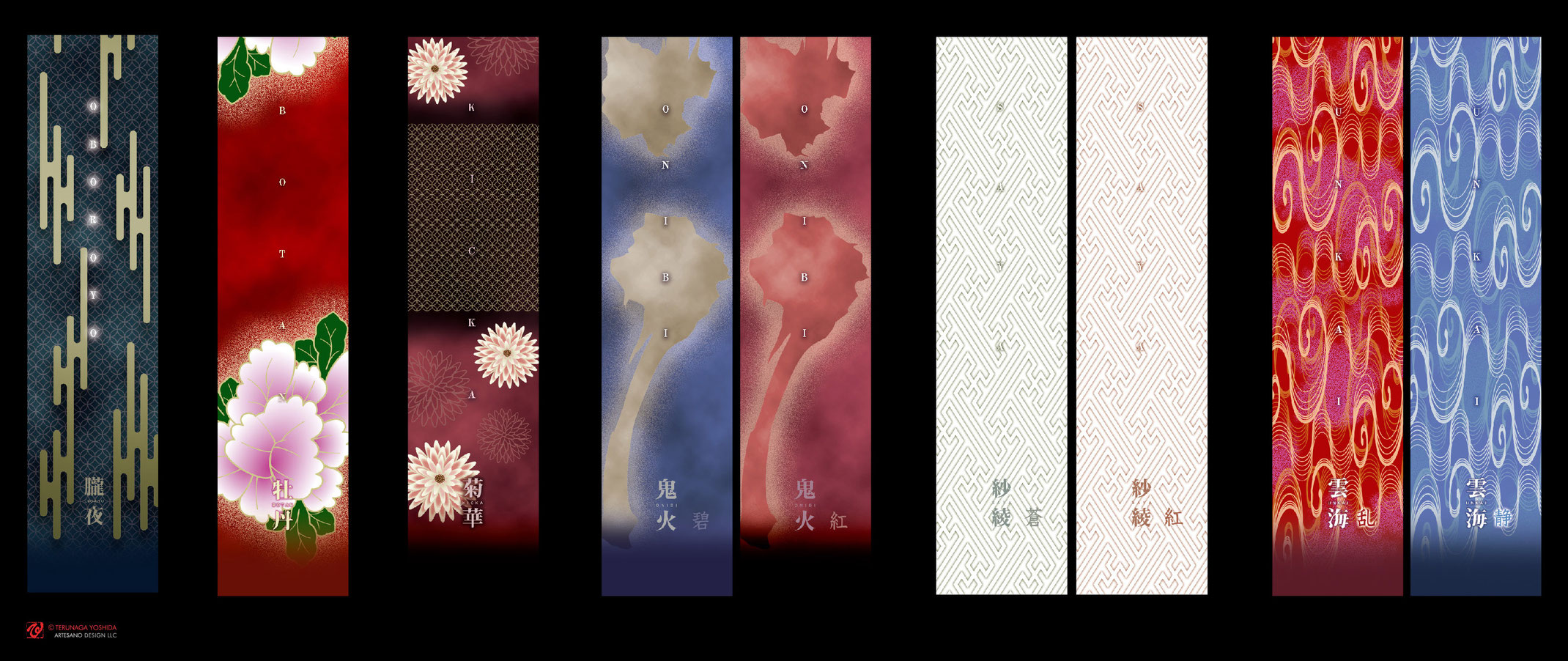
薫陶を受ける出会いに
皆様、こんにちは。
秋の訪れを感じるこの時期、風に舞い踊るススキの姿に、季節の移ろいを感じます。
先日、とある素敵なお誘いが舞い込み、期待に胸を膨らませてその場へ足を運びました。会場には、多くの方々が集まっており、彼らの持つ独特の空気感、熱意や情熱に私は圧倒されました。
中でも印象的だったのは、書道家の深見紅雨先生との出会い。彼女の人徳や魅力から、自然と人々は引き寄せられるようでした。薫陶とは、まさにそのような人から感じ取る、育まれる心の影響を言います。
紅雨先生は気さくに話しかけてくださり、多くの興味深い話をしてくれました。彼女の話し方や考え方、そして書の技法についての深い愛情と熱意。それらは私にとって、新たな視点や考え方を提供してくれました。
日本の書道、それは単なる文字を書く技法を超え、日本の歴史や文化、そして隣国である中国との交流を物語るアートとも言えるでしょう。
古の時代、中国の大陸よりさまざまな文化や知識が我が国へと渡来しました。その中には、文字や書の技法も含まれていました。仏教の教えや官の制度、そして文字そのものが5~6世紀にわたって日本に流入。奈良時代、我が国には「金銀泥経」のような美しい書物が生まれました。
そして、日本の文化は独自の道を歩み始めます。奈良時代には、日本独自の文字である仮名が生まれました。この仮名を駆使して生み出された「万葉集」は、日本人の心や風土を感じさせる一冊となっています。
平安時代に突入すると、女性たちが中心となり、平仮名を使用した独特の文学、女房文学が栄えました。「源氏物語」や「枕草子」は、その時代の情熱や思いを今に伝えています。
中世、禅宗の風が日本にも吹き込みました。その風に乗って、新しい書の流派や技法が次々と誕生。そして、近世に入ると、町人文化が花開き、書道はもはや貴族や寺院のものではなく、庶民の手にも落ち着きました。
近現代、伝統と革新が融合する中、書道は新たな境地を追求し続けています。古代から現代にかけて、日本の書道はその歴史の中で絶えず進化し、変化してきました。それは、我々日本人の心や文化の移り変わりを、深く反映しているのかもしれません。
私たちが出会う人や経験が、どれもが私たちを形成していく要素となる。紅雨先生との出会いも、私にとって大切なひとつの瞬間となりました。
この秋、ススキのように風に舞う心で、新しい出会いや経験を楽しみたいと思います。
