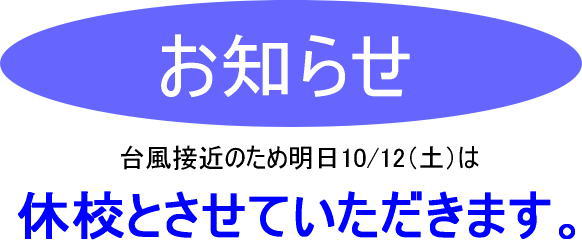- 前ページ
- 次ページ
10月30日(水)~11月4日の休校・開校日について以下の通りお知らせします。
【英駿個別進学セミナー】
10月30日(水)~11月4日(月)は休校です。11月5日(火)~開校。
【そろばん塾ピコ】
◆石山・中庄・一里山 10月31日(木)は休校です。 11月5日(火)~開校。
◆瀬田 10月30日(水)・11月1日(金)は休校です。11月6日(水)~開校
◆膳所 10月30日(水)・11月1日(金)は休校です。11/2は開校します。11月4日(月)は休校。11月6日(水)~開校。
◆山科 10月30日(水)・11月1日(金)とも開校します。
◆柳が崎 10月31日(木)は9/12の振替日として開校します。
以上、よろしくお願いいたします。
現在、台風21号が強い勢力で近畿地方に向かってきており、
【そろばん塾ピコ石山校・中庄校・一里山校・柳が崎校】
・終日休校
【英駿個別進学セミナー】
・終日休校
以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。