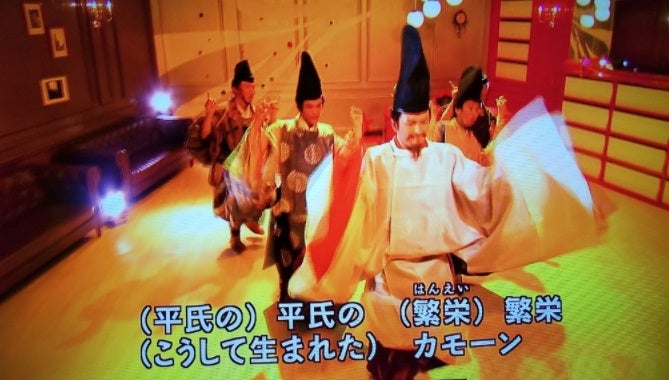史記とか三國志とかを題材にしたドラマや漫画を見ると、よーくわかりますが。
中国の王朝交代というのは、たいてい、草莽から英雄が出てきて、旧王朝の支配者層を皆殺しにして、新王朝を打ち立てる、みたいな豪快というか乱暴な形になります。
こういう新国家には、新体制を整えるため、皇帝に直属する有能な官僚を大急ぎで育成する必要があるわけで、ならばオープン試験である「科挙」をやろうじゃないか、となります。
たとえば大化改新とか大層なことを言っても、あれは蘇我本宗家に反発する豪族たちが集まっただけで、入鹿を倒してできた新政権(大化改新政府)の実態は旧体制の支配者たちの寄せ集め、そもそもその中の最大勢力は蘇我倉山田石川麻呂の一族で、のちに天智天皇がクーデターぎみに実権を握るのも妻の実家の蘇我氏の勢力が背景にあったからです。とてもじゃあないけど、科挙を導入して旧来の支配層の権益を否定する、なんてできっこないんです。
日本史は一事が万事、こうしたカンジで進んでいきます。旧支配層の過半数が賛同しなければ新政権はできない。天武天皇も平清盛も源頼朝も後醍醐天皇も足利尊氏も、豊臣秀吉も徳川家康も。みんな旧体制との妥協で新政権を作ったんです。
日本史に本来の意味での革命が起きたことは一度もありません、だから「科挙」もなかったんです。
なので日本史では、「それなりの家格の者の中から、なんとなく互選で、それなりの能力がありそうな者を選ぶ」という、かなりぬるっとした方法で、政治担当者・官僚が選ばれるのが普通です。
誤解されがちですが、摂関政治時代から江戸幕府に至るまで、(限られたメンバー内にしても)常に熾烈な権力闘争があり、すごい天才改革者は出ない代わりに、そうそう無能な奴は政権にはつけない、官僚が全員馬鹿ばかりということにはならない、ように出来ています。
親の権力が自動的に息子に引き継がれるような地位は、すぐにお飾りの象徴君主になります。江戸幕府の将軍なんて、家康と吉宗と慶喜以外は全員お飾りです。そのかわり、老中だの奉行だのに就任するためには、それなりに熾烈な競争があったんです。