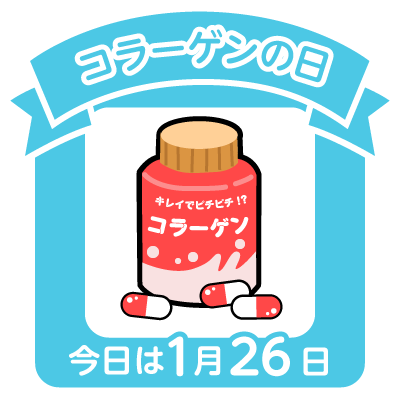次の次の大河ドラマで、小栗旬が北条義時をやると。三谷幸喜脚本「鎌倉殿の13人」。
私、むかし北条義時の役をやったことがあるんすよ、人前で。なので、物凄く思い入れがあるんです、鎌倉幕府にも北条氏にも。
「鎌倉殿」というのは将軍のこと。「の13人」というのは、その家来たちって意味。
義時は、「執権」という、事実上は鎌倉幕府の最高権力者になったけど、自分が将軍にはならなかった、わけです。
ということで、「源氏の将軍が三代でいなくなったあと、なんで北条義時は自分で将軍にならなかったのか」という話ですけど。
なんでか。
ひとことでいえば、将軍というのは「鎌倉のミニ天皇」だからです。
なぜなら将軍というのは象徴君主であり、京都生まれの「貴種」でなければならないんです。征夷大将軍というのは、「鎌倉幕府(と後世呼ばれるようになる組織)が成立するために必要な装置」のひとつであるにすぎません。そして、それは原理上、関東地生えの武士ではイケナイ、ということです。
鎌倉幕府といのは、いわば「関東武士の独立自治政府」です。「いわば」ですよ、あくまでモノの喩えですけど、つまり、いくら努力して農場経営しても、名目上の土地所有者である京都の大貴族に支配され「年貢とられ放題、上前はねられ放題」だった関東武士たちが、「自分の土地で稼いだものは、自分のものだ、って保障してくれる、オレたちの自治政府が欲しい」という根源的要求から生まれたのが、のちに「鎌倉幕府」と呼ばれるようになる、協同組合です。
そこで、彼らは自分たちの中から「王」を選ぶことをせずに、京都生まれの貴種に「王」の役をやってもらうことにしたのです。たまたま関東にいた源頼朝を担ぎ、「われわれは、この頼朝公の家来です、朝廷に叛旗を翻したわけではありません、今後ともよろしく」という体裁を整えたのです。
つまり、将軍というのは、最初から表看板であり、御神輿なんです。
御神輿というのが聞こえが悪ければ「代議士」とでも言い換えてもいいです。あるいは「外部招聘社長」(カルロス・ゴーンみたいなもの)です。オーナー社長ではなく、経営手腕を買われて迎えられた存在なんです。
源頼朝は、単に「誰かの子供」「血筋がいい」という存在ではないんです。子供の頃に(母親のコネで)後白河法皇の姉のもとに出仕して、その聡明さでものすごく可愛がられていた、正真正銘の貴族です。この「京都朝廷にいた経験が、実際にある」という実績が強みです。流人になったとはいえ、現在でも京都に「昔の人脈」があります。そのうえで、長く関東で暮らしていて、武士たちのニーズが骨身に滲みるほど分かっている。政治家として京都と交渉してもらうには、これ以上ない、うってつけの人材だったのです。
頼朝は、自分が関東武士団の利益代表の仕事をする「雇われ社長」であることを認識していました。だから、その役を完璧にこなすことができたのです。
だから、二人とも殺されたのです。これは鎌倉御家人全体の意志です。北条氏だけの陰謀ではありません。
関東地生えの者がトップになってはいけません。そうなれば、関東政府を目の敵にしている京都朝廷から「ほらみろ、うまいこと言ってたくせに、やっぱりヤツラ、地方の叛乱勢力じゃないか」と言われかねないのです。
せっかく、みんなで考えた「上手いことやっていくカタチ」を、台無しにしてしまうんです。
あくまで京都とうまくやっていくためには、京都から、子供でも何でもいいから、身分の高い「征夷大将軍」を派遣してもらわなきゃいけないんです。
その看板がないと、自分達が「夷」になっちゃうわけです。
源氏が三代で滅びたので代わりに、北条氏が「執権」になって権力を握った、というのは、違います。源氏の将軍がいなくなったあとも、幕府は京都からエライひとを呼んできて「将軍」に立て、みんなその家来ですよ、という体裁を整えて政治運営をしていたのです。
つまり、源氏将軍がいた時もいなくなった後も、やってることは全く同じなんです。
もし「北条氏が、陰謀で源氏を滅ぼして、権力を奪った」みたいな言い方をするヒトがいたら、それはキッパリと誤りです。
征夷大将軍は源氏しかなれない、というはなしを信じている人は多いですが、これは正しくありません。鎌倉幕府がこのあと京都から連れてきた将軍は藤原氏と皇族です。このひとたちは皆、頼朝の同母妹「坊門姫」の子孫です(女系ですけど)。
つまり、将軍は「都の貴種で、頼朝の縁続き」でなきゃいけない。関東武士とは人種が違う人じゃなきゃ駄目なんです。
北条は平氏だから将軍になれなかったわけじゃない。
源氏だろうと平氏だろうと、関東地生えの武士は、征夷大将軍にはなれないんです。
「執権」という言葉は、「家来のなかで第一の者、主人のかわりに家のなかのすべてを宰領する者のこと」を指す言葉です。つまり「執事」のことです。
鎌倉幕府においては、鎌倉殿(将軍)がご主人様であり、御家人たちが家来です。この御家人たちの代表、という意味で、いわば「筆頭執事」とでもいう意味です。
「執権」という単語を、現代風に「独裁者」と解釈すると、誤りです。「権力を執行する者」という意味ではありません。「権」という漢字の元の意味は「仮」という意味です。つまり「代理」「代行」です。(たとえば、水戸黄門は権中納言、ごんちゅうなごん、です、これは中納言と同じ職務をすることができる地位、ということです)。
「鎌倉殿のまつりごとを代行する者」というのが、本来の執権の意味です。あくまで家来の代表者であり、御家人が合議制で物事を決めるときの座長、というくらいの意味です。
初代「執権」は北条時政ですが、彼は「将軍実朝の祖父であり後見人である」という立場から、御家人代表になったのであり、あくまで「家来」だから、こういう名前になったのです。文字面から「ああ、これで北条氏が独裁権力を握った、ということね」と現代風に解釈するのは、ちょっと間違いです。
鎌倉幕府を運営する関東武士たちは、あくまで「自分たちは、京都から派遣されてきた将軍の、家来をやっております」という看板を、表向きだけですけど、掲げ続けた、つまりそれが「執権政治」ということなんです。
だから、北条氏は自分が将軍になってはいけなし、そもそもなれないんです。
そのうち鎌倉幕府は、京都から子供の親王(天皇の息子)を貰ってきて将軍に立て、大人になって自分の意志を持ち出すと京都に送り返して、また新しい親王を貰う、っていう、後世から見ると「なにやってんだ」ってことをするようになりますけど。「征夷大将軍」というのが、もともとは京都から派遣された期限つきの遠征将軍である、ということから見れば、このほうが当たりまえ、といえます。幕府の「看板」は京都生まれのほうがいいし、新しいほうがいいんです。
承久の乱に勝ったんだから、もう遠慮なんかする必要はないだろう、看板かけ変えりゃいいじゃん、って思うかも知れませんが、そういう傲慢なことをすると必ず内外から反発を食います。日本では、たいていそうなります。せっかく上手く行っていた組織を無用にがたつかせることはありません。
京都からきた将軍なんて、単なる象徴だから、もう要らないといえば要らない、でも、なくさないんです。このへんが「日本人の知恵」とでもいうところで、「われわれは独立する~! 京都の朝廷とは縁を切って、武士による武士のための武士の政治をする~!」みたいなキッパリとした宣言をしたりは、しないんです、絶対に。
そういう「曖昧な存在のしかた」のほうが、なにかと上手くいくのです。
どうして? というと、それが「日本人のやり方」だから、です。。