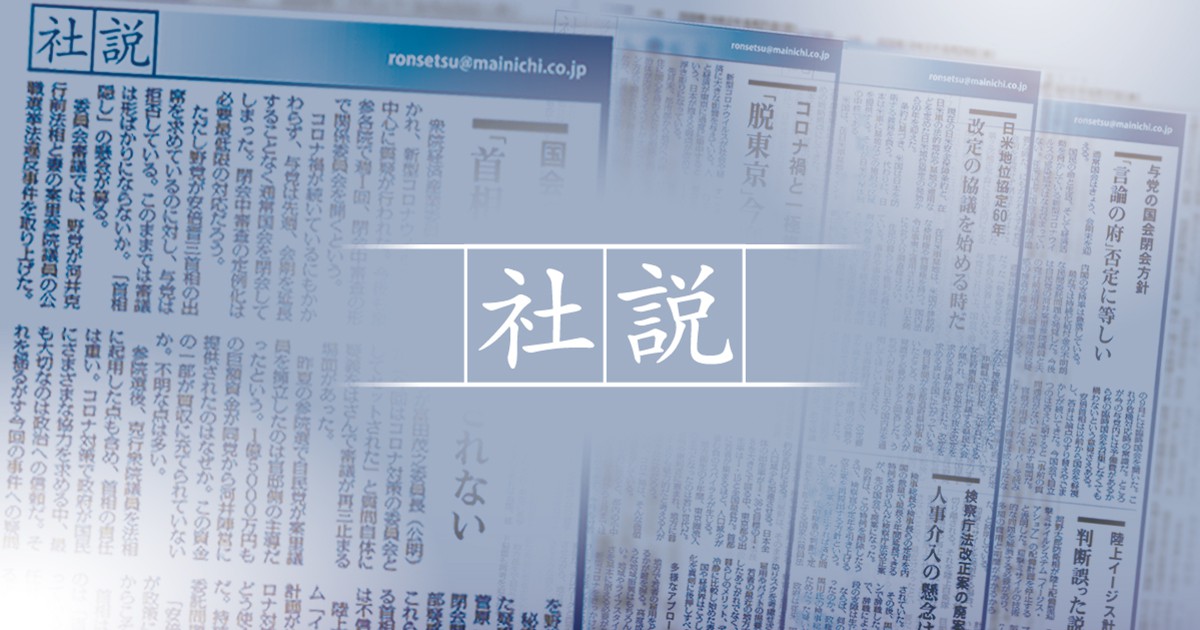消費税の「インボイス」制度が来月1日から始まる。公平な納税を確保するためだが、負担が増す小規模事業者からは不安の声が上がっている。
税の一部が国に納められずに事業者の手元に残る「益税」の問題を解消する効果もある。軽減税率が普及する欧州各国では広く定着している。
(9月21日毎日新聞から一部引用)
ずっと先のことだと思っていましたが,インボイス制度の開始がもう目前に迫ってきました。
インボイス、開始まで1年 対象300万事業者、準備に遅れ | 弁護士江木大輔のブログ (ameblo.jp)
これまで消費税が免税となっていた売り上げ規模が1000万円以下の中小事業者への影響が取りざたされる一方で,今まで(消費者が払った)消費税を納めないで懐に入れていたのだから課税されるようになって当然だという言説もあります。
しかし,この「消費者が払った消費税」という点については明確な誤りであり,裁判所の判決でも「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない。」と明確に述べたものがあります(東京地裁平成2年3月26日判決)。
どういうことかといえば,消費税に相当する部分は物やサービスの代金(価格)の一部でしかないということです。
代金が1100円の物(サービス)があったとすると,1000円が代金(価格)であって100円部分は消費税と理解しがちですが,あくまでも1100円全体が代金(価格)であるということになります。
そうすると,免税事業者が,消費税率が10パーセントとなったのを契機にして,それまで1000円であった物(サービス)を1100円にして売ったとしても,それは単なる「値上げ」に過ぎず,消費者から100円の消費税を預かったということはならないことになります。
そのため,先ほど触れた「今まで(消費者が払った)消費税を納めないで懐に入れていた」という免税事業者に対する批判の前提自体が崩れるということになります。
もっとも,免税事業者は消費税を納めないでよいのに値上げするのはおかしいではないかという批判もありそうですが,単なる「値上げ」である以上とやかく言われる筋合いはないものですし(そのような値上げをしたとしても売り上げが1000万円以下の中小事業者ということになります),免税事業者であっても仕入れのために消費税相当額を含んだ支払はするので,「値上げ」すること自体にも合理性があるということもできます。
物(サービス)の代金(対価)の一定部分を消費税として課税しているのに,その部分を支払わなくてよいというのはおかしいという批判もありそうですが,中小零細事業の負担に鑑みて免税とするという政策的な配慮をすること自体は,消費税の免税事業者に限った話でもありません。事業の公益性に鑑みて社会福祉法人などに対して固定資産税を免除するとかと言ったことと同じことであるともいえます。
今回,インボイス制度の導入に合わせて,段階的に,そのような中小事業者に対する政策的配慮を止めていくということになるわけですので,実質的にみれば,中小事業者に対する増税に他ならないということになります。
勿論,インボイス登録するかどうかは選択に任せられていますので,インボイス登録しないという選択をした売上1000万円以下の中小事業者については,引き続き,課税がされないということになりますが,インボイス登録をしていないと取引先から取引を打ち切られる可能性がある事業をしている中小事業者にとっては増税か取引解消(されるかもしれない)の選択を迫られるというシビアな状況であるということになります。
勿論消費税相当額を価格転嫁できればよいのですが,先ほど述べた通り,消費税相当額を上乗せするかどうかというのは要するに代金(対価)をどのように設定するのかという単なる「値決め」の問題に過ぎません。
大企業と中小企業,フリーランスの力関係から,力の弱い側が価格決定権を行使できるかということになれば,それは簡単ではないということは容易に想像がつくことかと思います。
この点に今回の根深い問題があるということがいえます。