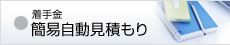判例時報2257号で紹介された事例です(東京地裁平成26年10月30日判決)。
特殊鋼の販売を行う会社(ユーザー)が、ベンダーとの間で、販売管理システムの開発等を目的とする契約を締結し、ベンダーがシステムを完成させたが、ユーザーが
・開発を依頼したシステムのソフトウェァは、ユーザーが既に使用していた現行システムの仕様をすべて備えていることが必要との合意をしたのに、それが満たされていなかった
・開発されたシステムには多数のバグがある
といった理由で検収を拒んだため、ベンダーが、ユーザーの債務不履行を理由として損害賠償請求したというものです。また、ユーザーからは、開発を依頼したシステムのソフトウェアの完成に至らなかったということで反訴も提起されています。
まず、裁判所は、ソフトウェア開発の手順等について、次のような一般論を展開します。
・ソフトウェア開発においては、当初の契約時には概括的にしか定まっていないシステムの仕様について、ユーザーとベンダーの共同作業により、仕様を確定させる作業が必要となる。
・仕様の確定に当たっては、ITの専門家であるベンダーの適切な助言が必要とされる一方で、ユーザーの独自の業務慣行などユーザー側で表明しなければベンダーには認識できないものもある。
・開発工程を区切って各フェーズを順次実行して開発を行うウォーターフォール型開発においては、その工程は①要件定義②基本設計③構築④運用の各段階に分けられ、仕様確定作業は①と②の段階で完了することになる。
・①要件定義の段階では、ユーザーが主体となって時者の業務を明確にし、それをベンダーが開発できるような形で取りまとめた要件定義書を作成する(ユーザー自身が作成する場合もある)。
・②設定の段階では、ベンダーが、要件定義書を基に、ユーザーからさらにヒアリングを行い、業務で使用する画面や帳簿等の仕様の詳細を決定し、基本設計書を作成して、ベンダーの検収を受ける。
・仕様確定後に仕様の変更が合意される場合もあるが、ソフトウェア開発においては複数のプログラムが連動して全体として機能するため、一般的には仕様確定後の仕様変更は例外的とされ、本来的には想定されていないものである。
・システム開発の手法としては、すべてを最初から構築するスクラッチ開発と既存のパッケージをユーザー向けにカスタマイズする方法がある。後者においては、パッケージソフトの機能とユーザーが希望する機能とを比較し(フィットギャップ分析)、カスタマイズの内容を決定することとなるが、一般的にはカスタマイズは最小限度に留めることが原則とされている。
その上で、本件は、ウォーターフォール型の開発手法で、、ベンダーのパッケージソフトをカスタマイズするという方法で開発が行われることとされており、ベンダーはユーザーからのヒアリング、フィットギャップ分析を経て、要件定義書及び基本設計書(両者合わせて「本件仕様書等」)を作成し、ユーザーによる検収も受けていました。
要件定義書と基本設計書まの作成・検収が行われている以上、ソフトウェア開発の流れ上は、後戻りができなくなることが原則とされていることから、本件仕様書に記載がない事項については、特別の事情がない限りは、その仕様に従うという合意が両者の間でされていたものとみるべきだとされました。
ユーザーは、現行システムの機能をすべて満たすことが合意されていたと主張したわけですが、本件仕様書にはそのような記載がないことに加えて、仕様を確定させていく作業の中で、現行システムの機能がすべて満たされ眼わけではないことについて両者が協議し、ユーザー側が了解したととれる打ち合わせもあったことなどから、現行システムの機能をすべて満たすような仕様とすることという合意があったとは認められないとされました。
また、ユーザーが主張したバグの点について、ソフトウェア開発においては、初期の段階で軽微なバグが発生することは技術的に不可避であり、実務的にも納品後のバグ対応も織り込み済みであることから、バグが発生したとしても順次解消可能な程度のものであれば、債務不履行とはならないと考えるべきだとされました。
こうしたことから、本件においては、ベンダーがシステムを開発し完成させたのに、ユーザーがそれを検収しなかったとされ、ユーザーに債務不履行があったものとされています。
その上で、契約がそのまま成就していたら手にしていたであろう利益が損害として認められ、ユーザーに対して約2500万円の損害賠償が命じられました(なお、ユーザー側の反訴は棄却)。
なお、ベンダーは、ユーザーの求めに応じて追加対応した分の費用も請求しましたが、これについては、契約においては再見積もりの上契約金額を変更することとされていたことや(実際に追加カスタマイズ分については別途契約書面゛取り交わされていたものもあった)、商人間の取引については書面による合意を尊重すべきであることなどから、この部分についての請求までは認められませんでした。
本件は控訴されているということです。
本件は、両者のシステムのソフトウェア開発の契約や打ち合わせがされたのが平成14、15年ころのことで、ベンダーによる提訴が平成23年、判決が平成26年のことですので、訴外の係争も訴訟になってからの期間もロングランとなつています。
ソフトウェア開発を巡るトラブルでは、専門的な知見が必要になることも多く、本件ではどうであったかは分かりませんが、民訴法上、専門委員制度といって、その道の専門家が裁判所の理解を助けるために参加するという制度もあります。
■ランキングに参加中です。
■着手金の簡易見積フォーム
(弁護士江木大輔の法務ページに移動します。)