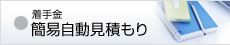判例タイムズ1404号などで紹介された最高裁判決です(平成26年6月5日決定)。
民事再生手続、特に企業のそれでは、再生債務者と抵当権などの担保権利者との間で別除権協定というものが締結されることが珍しくありません。
再生債務者の資産から優先的に回収できるものとして設定されている抵当権などは別除権と呼ばれ、民事再生手続きが開始されたとしても、それとは別に別除権者は回収換価の手段を取ることができます。不動産であれば抵当権に基づく競売の申し立てができてしまうわけです。
しかし、再生しようとしている再生債務者にとって必要不可欠な資産、例えば、工場などの不動産やリース物件などが、回収されたり換価されたりしてしまうと再生することができなくなってしまうので、裁判所の許可を得た上で別除権協定というものを締結します。
これは、別除権者には、本来再生手続き中は弁済が禁止されているところ、分割弁済をしていくことで担保権の実行をしないことを約束してもらうというものです。
ただ、分割弁済の対象となるのは、あくまでも担保物件の価値相当額であり、それを超える部分は不足見込み額として、優先弁済の対象ではなく、あくまでも再生手続きにおける債権カットの対象となります。
本件でも、一般的な書式例に従って、「再生計画認決定の効力が生じないことが確定すること再生計画不認可の決定が確定すること、再生手続廃止の決定が確定すること」を解除条件(これらの条件が発生した場合には協定が失効すること)として、別除権協定が締結され、その後、分割弁済を内容とする再生計画案が認可決定されました。
しかし、再生計画に従って分割弁済を履行してから約3年後に、経営は再び頓挫し、裁判所による破産手続き開始決定が下されてしまいました。
抵当権を有していた別除権者は担保権の実行に基づく競売開始を申立てをしましたが、その手続きの中で問題となったのが別除権協定の効力でした。
例えば、本来1000万円を被担保債権とする抵当権を有していたものの、別除権協定を締結して、時価である800万円を優先弁済の対象とし、残額200万円は一般の再生債権として取り扱うとした場合において、競売によって800万円を超えるだけの回収が見込まれるということになった場合に、別除権協定によって200万円分はその担保から回収できないものとして合意している以上、優先回収できないと考えるのかどうかということです。
競売を担当する裁判所が、1000万円を基準とした配当表を作成したところ、債務者の破産管財人が異議を唱えたというのが本件です。200万円分は担保からの優先回収から外れるとすれば、200万円は管財人が財団に組み入れて、その分一般債権者に対する配当に回すことができます。
高裁では、解除条件として示された条件の中に破産手続き開始決定がされたことは含まれていないという文言解釈を行いましたが、最高裁では、実質的に考えて破産手続き開始された場合にも解除条件は成就されたものと考えるのが当事者の意思として合理的であるとして、高裁の決定を破棄しました。
■ランキングに参加中です。
■着手金の簡易見積フォーム
(弁護士江木大輔の法務ページに移動します。)