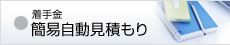平成17年1月に刊行された判例タイムズの臨時増刊号「東京家裁後見センターにおける成年後見制度運用の状況と課題」(旧版)が,平成25年3月についに改訂されました。
いつか出すいつか出すと言われ続けていましたが,家事事件手続法の施行も伴って,ようやく発刊となりました。
中身としては,個別のQA方式に改められており,より利用しやすくなったと思います。
私としては,診断書が取得できない場合についてが気になっていたところですが,旧版では,「診断書は申立後の手続を進行させ,あるいは鑑定の要否を判断する資料としての意味を有すると解される」(26ページ)とのみ記載され,家族の囲い込みなどによって診断書が取れなかった場合の対応について曖昧でした(旧版38ページ)。
「手続を進行させ」とありますので,逆読みすれば,診断書がないと手続が進行しないという扱いになっているということも事実としてはあったと思います。
今回発刊された「後見の実務」によると,少し踏み込んだ表現になっていて,「診断書は後見開始の審判をするに当たっての必須の資料というわけではなく,診断書が準備できないとしても,後見開始の申立を行うことは可能です」と記載されています(26ページ)。
そして,「今後の進行の参考とするため診断書を取得できない事情について説明していただく必要があります」と記載があり,「本人や親族の協力が得られず鑑定が実施できない場合には」却下もあり得るとされています。
また,診断書が提出されない場合,通常は鑑定を実施するとも記載されていますので(23ページ),診断書が提出されなくても,調査官の調査や鑑定といった手続に進んでくれることが期待できそうです。
これまでの感覚からすると,診断書が取れないと,その後の手続に進んでゆけないというイメージがありました。
もっとも,引き続き,診断書が「申立後の手続を進行させ,あるいは鑑定の要否を判断する資料としての意味を有する」という基本的な考え方については変更はないものと考えられ,診断書を取得することについては強く求められるのではないかと思います。
診断書を取得できない理由や診断書が取得できないまでも本人の精神的な状況について何らかの資料(ケアネマやヘルパーからの聞き取りとか診断書は書いてくれないまでも診察した医師からの聞き取りなど)の提出は求められるでしょうから,進行としては遅くなるということはいえると思います。
本人が鑑定を明確に拒否している事案では少しお手上げですが,家族の囲い込みなどがされている事案では,家裁の調査官などが説得することで,家族が鑑定に協力してくれるということはあり得ることですから,天下の東京家裁が出した書籍中で,診断書が後見申立てに当たっての必須の資料ではないということを明記してくれたことは良かったなと思います。
■ランキングに参加中です。
■着手金の簡易見積フォーム
(弁護士江木大輔の法務ページに移動します。)