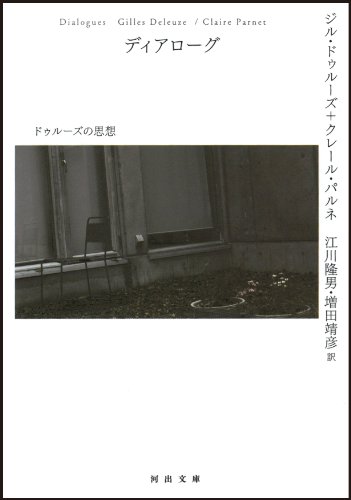「Xの」という変数Xにカタカナ名が入る限り(さらに限定はあるにしても)
つまるところ「哲学史」に回付されますよっていう標識でもある。
で、哲学史といえば基本、西洋史に包摂される。
「日本の哲学史」という表現はありえても、
それは厳密には存在しない。
さらに、で、この「哲学史」というもの、
ドゥルーズにかぎったことではない、デリダにせよ、
フーコーにせよ(この人にはまだ節度があるが)、
とくにフランス90年代までの思想/哲学には、そこから抜けたくても抜けられない、
沼袋(地名ではない)のようにあり続けたものだ。
「戦争から解放されても、奇妙なことに哲学史に足が嵌まったままだった(ドゥルーズ)」
要するにシツコイ二日酔いのようにそこにハマり、
なんとかしてえ!状態だったのだ。こんなことはアジア日本列島ではなかなか起こりにくい。
さらに、で、ドゥルーズなどは、「読み」の戦略にまでいっちゃった。
自らの標識を逆手にとって、ありゃりゃっ?ってなるテキストを書いた。
結論からいう。それは、
二日酔いに対する処方箋であり、ブルーリボン(いまもあるかなあ、よく効いた二日酔いの薬)
だったのだ。昨日の記事で「酒も呑んでないのに、二日酔いの薬、飲む人はいない」と書いたのは、この意味だった。
「中間」はそもそもわが足下にある。和辻はこれを「風土」と仮称してみたりもしたが。
スキゾは、発症することもなく、今なんちゃら大学院院長様である。
はっきり言ってこれは個人攻撃だが(爆)、事はそんなとこに収めていいようなもんではない。
日本の哲学がもしあるとすれば、僕は明治の廃仏毀釈などをハサミながら、
仏教を哲学的に基礎づけようとしたあたりから始まり、そして途絶えた。その先にあると思う。
そんなことには不感無覚の「教授」らによる言説垂れ流しが溢れ出し、
どんだけ時代は時を浪費してしまったことか。
だから、僕らは、二日酔いで青息吐息の彼ら(ドゥルーズたち)を介抱するような手つきで読んであげることこそが、読みの倫理であったはずだし、闘争のエチカ(プッ)であったはずだった。
まだ、間に合うと思う。
PS.
作動配列が現実に作動した出来事は、あれら言説ではむろんなく、
ドゥルーズのハードカバーが2011年に〈文庫化〉されたことだった。
ディアローグ---ドゥルーズの思想 (河出文庫)
posted with amazlet at 13.06.01
ジル ドゥルーズ クレール パルネ
河出書房新社
売り上げランキング: 313,064
河出書房新社
売り上げランキング: 313,064