ライト・ビジネス書って、カタカナにするとなんかカッコよく見えたりしますが、
たんに中身が「軽い」って意味です(爆)
「軽薄」の「軽」だったりもする。
ただ「軽くて薄い本」が、必ずしも「中身が薄い」とも限らない。
アインシュタインが相対性理論を発表したE=mc2(2乗)の論文は、A4ペラ1枚でした。
(これ、本とは言わないけど)。
ハードとしての本、冊子が「軽くて薄い」のは、満員電車のなかでも読めるという一大メリットがあるわけで。
だから、そういう話じゃなくて。
ハードカバーのやたらすごいことが書いてありそうな本に見えて、実はくだらないidiot本だったりすることもある。
「価値」というのは、金塊と違って、「重さ」や寸法じゃ測れないわけです。
高校のころ初めて買った岩波文庫が1冊50円(★1つ50円)なのに、びっくりしたのは昔懐かしい話です。
(古本ではありません。新刊本の話です)。
本の価値というのは、単純な物差しでは測れません。
でもです。
どう考えても中身のない、アメリカンよりも薄い本が、出まくって来たのも事実。
その起源が、このへんにあるんじゃないのって話を、先日先輩としてきました。
The Complete Idiot's Guide
ってシリーズ本です。
直訳すると、「完璧な馬鹿者のガイド」。
日本でも、「サルでもわかる・・・」ってタイトルの本が一時期流行りましたが、そのもとになったのはこのシリーズらしい。
ただし、このシリーズ、ペーパーバックで400ページ以上あったりします(笑)
完璧なidiotには、読めたものではありません。いわんやサルには読めません。
で、けっこう売れてるのもあって、翻訳も出ています。
翻訳本は、たとえばこれ、
- 世界一わかりやすいプロジェクト・マネジメント/サニー ベーカー

- ¥2,940
- Amazon.co.jp
原書は、
- The Complete Idiot’s Guide to Project Managemen.../PMP, G. Michael Campbell
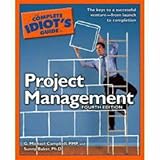
- ¥1,870
- Amazon.co.jp
日本語タイトル、なんというかとってもわかやすい(爆)
わかりやすすぎて、idiotよりもidiot?と思えるのはわたしだけでしょうか?
ただし、これも中身とは関係がない。
ウィットとしては、原題のほうが優れている。
メインのテーマとの掛け合わせの効果もある。
これがダイエットだったりしたら、たぶん効果は半減するでしょう。
シリーズのなかでも、ちょっと変わり者の一冊を選んでしまったかもしれないですが、
シリーズタイトルとメインタイトルの落差が激しいほど、実は効果が出る。
書き手としては、挑戦的な仕事になるので、わたしだって腕が鳴ります(笑)
「サルでもわかる相対性理論」とかね。
とにかくこのウィットが、いろいろ変調して、ほんものの軽薄本が登場する流れを作っていったのかも知れません。
同じことは、ハックhack、ライフハックものにも言えます。
ビジネス書とハウトゥーものは、微妙に違うはずなんですが、
二つが混ざりあっていく流れ、と言ってもいいかもしれません。
要するに、「なぜ?」と問うことが、失われていった流れです。