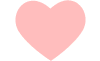数学者のピーター・フランクルさんが、漢字を書けることと、数学のセンスはとても近いものがあると語ったのを聞いたことがあります。
寿司屋さんの湯呑みに絵付けされている、魚の漢字を取り上げていました。
鰯とか鯖とか鮪とか。で,確か因数分解の能力と、漢字の作字力を結びつけてしゃべっていたと記憶します。
ほかに、「百」という漢字一つから、いくつもの音が引きだされること。組み合わせによって、読みが変わることなどに注目するという話だったと思います。
百舌(もず)、百々(どど)めきなど、複数の音が「連想的」に引きだされる。
視覚的にも、
偏(へん):左側に位置する。
旁(つくり):右側に位置する。
冠(かんむり):上側に位置する。
脚(あし):下側に位置する。
構(かまえ):外側に囲む ように位置する。
垂(たれ):上部から左側を覆うように位置する。
繞(にょう):左側から下側をとりまいて位置する。
これだけの要素(構造と運動)を持って、一字が構成される。
この漢字の世界に、極値集合論を得意とする数学者、フランクルさんが、大々注目しているわけです。
部分と全体を、行き来するセンスも、漢字を書く過程で、実は養われているかも知れないと、わたしなど思います。
まあ、漢字はそれだけで、一枚の地図と言ってもいいくらいです。
シンプルマッピングしていると、ときどき書(しょ)を思い出すのは、わたしだけではないはずです。