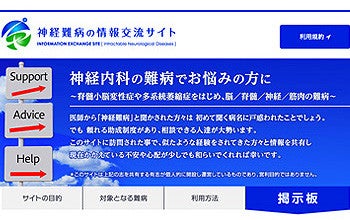私の現在の主治医は、某大学病院の神経内科の教授。
- 愛想が良いなんて決して言えない。
- 患者に寄り添うという雰囲気でもない。
- 構音障害のある私の言うことはほとんど聞き取れない、と言うか聞き取る意思があるとは思えない。加えて、症状が候補に上がっている病気の典型例でないことも有り、症状を正確に把握しているとは思えない。
一方で、
- 無愛想や安易に患者に寄り添わない姿勢は、医者として正直で、患者に下手な希望を抱かせないため(性格も有るとは思うが)とも取れる。
- 病名が確定していない時点で、最も確率の高そうな病名をつけて、今後治療が高額になる可能性があるからと、難病申請を勧めてくれた(それが数々の福祉制度を知る切っ掛けとなった)。
- こちらが提案した治療法を(渋々ながら)受け入れてくれる。恐らく治療方法を提案できないどころか、未だに病名すら確定できない中で病気だけは確実に進行していることへの後ろめたさ、と患者サイドからの提案(病院側はNo Risk)で実験ができる、と言う理由からだと思うが、結構無茶な提案を受けてくれる。
だから及第点。
患者に寄り添う点と日々の症状の変化については、神経内科専門のかかりつけ医(優しくて素敵な女医さんで、後に私が卒業した高校の後輩であることが判明)と、訪問看護師さん、PTさん、OTさんが十分に担ってくれている。
その女医さんが紹介してくれた別の大学病院の神経内科の先生にも、適宜診察を受けて意見を聞くことが出来る。
閑話休題。
主治医の話。
先日、珍しく主治医の意見と自分の体感が一致した。
それは、前回、偶然抗癌剤治療の結果体感した病状の改善が、今回はごく僅かにしか現れなかったことに対する見解。
- 病気には原疾患(私の場合は神経疾患で、悪性リンパ腫が神経疾患の原因ではないと言われている)と、それとは別に炎症を起こしている部分があって、その病気に関係がないと思われる治療によって、原疾患は治らなくても炎症が抑えられたために、原疾患の病状が多少でも改善したと実感することが有る。
- その治療はその炎症にしか効かないから、その炎症が治まっている間は再度その治療をしても効果がない。
- 原疾患と炎症との比率は殆ど一定だから、仮にその炎症が再発していたとしても、その治療による改善は原疾患の進行に伴って漸減していく。
前回の治療は悪性リンパ腫の治療のためだったので、今回はその治療をそのまま再現した訳ではないことは理解した上でのダメ元治療だった。
僅かでも改善が有ったと思うのも錯覚の可能性は高いが、継続的に体調を見てくれている人達が口を揃えて多少でも改善が有ったと言ってくれた(慰めでないことを祈る)。
仮に効果があったのだとしても、私の場合は原疾患の進行がかなり進んでおり、その治療の効果もかなり限定的と言う説明が腑に落ちた。
これが正しいとすると、この治療を繰り返しても効果はどんどん限定的になっていって、そのうちに全く効かなくなるのだろう。
と言うか、そもそもこの危険を伴う治療が、何度も繰り返す度に効果があるかは疑問なのだが、当面はこれが私に残された「藁」だ。
あ、オチがない。