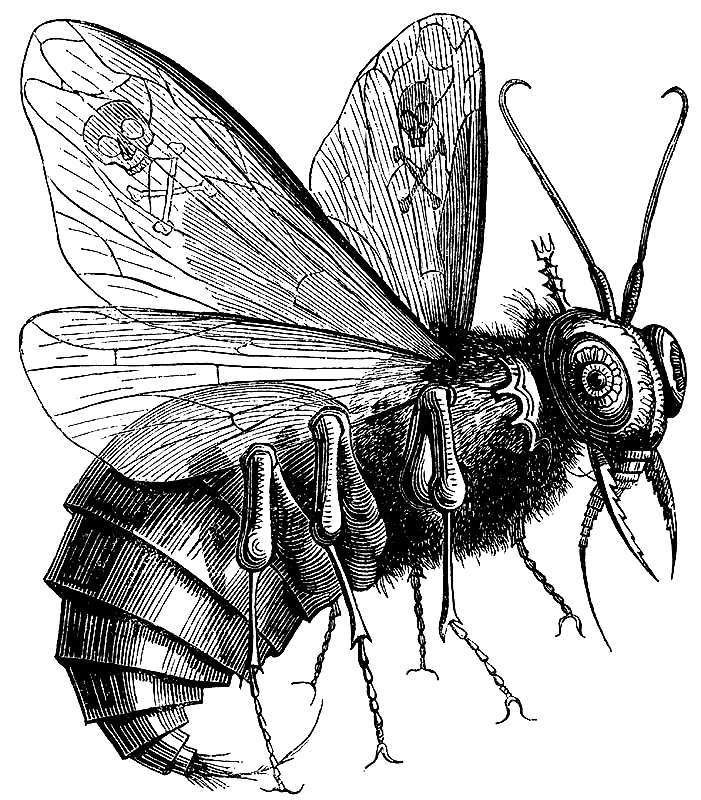うーん、このお題でどんなことが書けますかねえ・・・
虫といっても、昆虫以外のクモとかヒルとかゴカイとかも入れて、
小動物ということで考えていきましょう。まず最初に言えるのは、
生理的嫌悪感のあるものが多いということですね。
例えば、廃屋を歩いていると、天井が急に破れて、
大量のウジが頭の上に降ってくる・・・これはたしかに怖いですけど、
生理的嫌悪感のみで話を成り立たせるのは、ちょっと反則のような
気がします。それだけでは底の浅いものになってしまうというか、

もう一つ、プラスアルファの部分がほしいところです。
虫に対する恐怖症を持っている人は多いと思われますが、その中でも
クモ恐怖症は特に、「アラクノフォビア」という名前までついてます。
この語源になったアラクネというのはギリシア神話の登場人物で、
女神アテナと機織の勝負をしてクモに変えられてしまった人間の女性です。
「クモが怖い」と言うと、「クモは蚊やハエなどを食べてくれる
益虫なんだよ」と返されることもありますが、そうは言っても、
なかなか理屈で恐怖症が改善することはないですよね。

「虫のホラー」で最初に思い浮かぶのは、やっぱりカフカの『変身』
なんですが、これも毒虫になってしまった主人公への家族の嫌悪感が、
物語の構造上、大きな部分を占めています。
もしこれが かわいい子犬とかに変身したのなら、
まったく違ったファンタジー系の話になったかもしれません。
ホラー小説だと、スティーブン・キングの次男であるジョー・ヒルが、
『蝗の歌を聞くがよい』という短編を書いています。
ある朝、いじめられっ子の主人公は大きな蝗に変身していて・・・
ここまではカフカ作品へのオマージュなんですが、
その後は一転してスプラッタアクション系の展開になっていきます。
あと、オーガスト・ダーレスが、『シデムシの歌』というのを書いていて、
シデムシは漢字で死出虫と書く、動物の死骸を食べる虫のことです。
雰囲気で読ませる作品なので粗筋を紹介するのはやめておきますが、
これはなかなかの佳作ですね。作者のダーレスは、

H・P・ラブクラフトの死後、作品を整理してクトゥルー神話の体系を
つくりあげた人で、自身もたくさんホラー短編を書いていますが、
これとあと、『淋しい場所』というのが有名です。
日本のだと、どちらも長編ですが、坂東眞砂子氏の『蟲』とか、
田中啓文氏の『蝿の王』がそれ系ですかね。田中作品はもちろん、
ウィリアム・ゴールディングの同名の傑作『蝿の王』へのオマージュ作品です。
ちなみにゴールディング作品の蝿の王とは、蝿が群がった
豚の頭を意味するとともに、悪魔ベルゼブブも指しています。

さて、映画だと虫系ホラーはいろいろありますが、大別して2つに分かれます。
一つは虫がそのままの大きさで大量に出てくるもの。
1976年のアメリカ映画『スクワーム』なんかが代表作ですかね。
ここで出てきたのはゴカイの大群です。B級といえばそうなんですが、
ストーリーがしっかりした、なかなかいい作品だったと思います。
これ系の映画のはしりは、チャールストン・ヘストン主演の1954年作品、
『黒い絨毯』でしょうか。アマゾンの人食いアリが黒い絨毯という題名の由来です。
もう一つは、虫が何らかの理由で巨大化して暴れまわるもので、
『スパイダー・パニック』とか、これ系はいっぱいあります。
あと、SF映画の『スターシップ・トゥルーパーズ』のシリーズも、
敵の宇宙人は、ゴキブリとかクモが巨大化した造形でしたね。
あと、『メン・イン・ブラック』でも、ゴキブリから進化した
エイリアンが出てきていました。

ハリウッド系の映画は、オリジナルの怪物をつくるのが苦手だという
話があります。これはキリスト教国なので、すべての生物は神が
創造したものであるという概念からなかなか抜け出せないためである、
という説がなんですが、これはどうなんでしょう。
1998年のハリウッド版『GODZILLA』では、ゴジラがトカゲのような
造形になっていたので、そういう面はあるのかもしれません。
あと、上の2つの分類にちょっと当てはまらないのが、
1986年の『ザ・フライ』です。これはSF系のホラーで、
物質転送機「テレポッド」を発明したノーベル賞科学者の主人公が、
転送の際に、手違いで入り込んでしまったハエと遺伝子レベルで
融合してしまい、だんだんにハエ人間化していくというお話でした。
ただこれ、虫系というよりは変身物の要素のほうが強かったと思います。
最後に主人公は、またまた手違いによって機械と融合してしまうという
ドジな結末でしたね。・・・まあ、今回はこんなところで。
悪魔『ベルゼブブ』