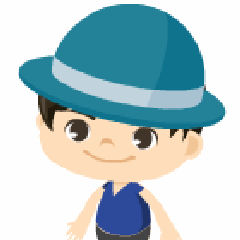さて、釈迦十大弟子の話に戻ります。その一人に目連(もくれん)尊者という人があります。目連は、神通力(じんつうりき、人間の考えの及ばぬ、霊妙自在の力。)第一と言われ、特に孝心の深い人でありました。
彼には、以前も説明した、お盆の意義と関連した有名なエピソードがあります。
お盆は、正しくは盂蘭盆(うらぼん)と言います。
仏説盂蘭盆経から来ています。
彼が神通自在を得て三世を観た時に、亡き母が餓鬼道に堕ちて苦しむ事が分かりました。
彼は深く悲しんで鉢に飯を盛って母に捧げましたが、母が喜んで食べようとすると、忽ちその飯は火焔と燃え上がり食べる事ができません。
泣き崩れる母を彼は悲しみ、
「どうしたら母を救う事ができますか」
と釈尊にお尋ねしました。
釈尊は、
「そなた一人の力ではどうにもならぬ。七月十五日に、飯、百味、五果等の珍味を十方の大徳衆僧に供養しなさい。布施の功徳は大きいから、亡き母は餓鬼道の苦難から免れるであろう」
と仰いました。
目連が釈尊の仰せに順ったところ、母は忽ち餓鬼道から天上界に浮かぶ事ができました。喜びのあまり踊ったのが盆踊りの始まりとも言われます。
盂蘭盆は、この故事から祖先供養の日となって今日に至るのですが、これは何を教えているのでしょうか。
ウラボンという梵語は倒懸という事で、即ち「倒さに懸れる者」です。
盂蘭盆経とは、「倒さに懸れる者を救う方法を教えた経」です。
果たして、倒さまに懸って苦しむのは目連の母だけでしょうか。
死後にだけ餓鬼道があるのではありません。
迷いを迷いと思われず、真実を真実と信じられず、迷いを真実と誤解して苦しみ悩む者は、仏眼からご覧になると、皆倒さに懸って苦しむ餓鬼です。
キリのある身命を持ちながら、キリのない欲を充たしてから仏法を聞こうとする人の如何に多い事か。
総ての考えが顛倒していますから四方八方ただ愁歎の声のみが満ちています。
まさに餓鬼の姿です。物を求め、物を惜しみ、闘争諍乱の世界。
この深刻な現実の自己を凝視する時、餓鬼こそ自己の実相である事に驚きます。
祖先の後生ばかりを案じて、我が身が餓鬼である事を忘れています。
お盆は、亡き祖先を救う日ではなく、今現に倒さに懸って飢え渇き苦しみ続けて、未来永劫、流転せんとする、我が身自身を救う聞法精進の日である事を忘れないようにしたいですね。
彼には、以前も説明した、お盆の意義と関連した有名なエピソードがあります。
お盆は、正しくは盂蘭盆(うらぼん)と言います。
仏説盂蘭盆経から来ています。
彼が神通自在を得て三世を観た時に、亡き母が餓鬼道に堕ちて苦しむ事が分かりました。
彼は深く悲しんで鉢に飯を盛って母に捧げましたが、母が喜んで食べようとすると、忽ちその飯は火焔と燃え上がり食べる事ができません。
泣き崩れる母を彼は悲しみ、
「どうしたら母を救う事ができますか」
と釈尊にお尋ねしました。
釈尊は、
「そなた一人の力ではどうにもならぬ。七月十五日に、飯、百味、五果等の珍味を十方の大徳衆僧に供養しなさい。布施の功徳は大きいから、亡き母は餓鬼道の苦難から免れるであろう」
と仰いました。
目連が釈尊の仰せに順ったところ、母は忽ち餓鬼道から天上界に浮かぶ事ができました。喜びのあまり踊ったのが盆踊りの始まりとも言われます。
盂蘭盆は、この故事から祖先供養の日となって今日に至るのですが、これは何を教えているのでしょうか。
ウラボンという梵語は倒懸という事で、即ち「倒さに懸れる者」です。
盂蘭盆経とは、「倒さに懸れる者を救う方法を教えた経」です。
果たして、倒さまに懸って苦しむのは目連の母だけでしょうか。
死後にだけ餓鬼道があるのではありません。
迷いを迷いと思われず、真実を真実と信じられず、迷いを真実と誤解して苦しみ悩む者は、仏眼からご覧になると、皆倒さに懸って苦しむ餓鬼です。
キリのある身命を持ちながら、キリのない欲を充たしてから仏法を聞こうとする人の如何に多い事か。
総ての考えが顛倒していますから四方八方ただ愁歎の声のみが満ちています。
まさに餓鬼の姿です。物を求め、物を惜しみ、闘争諍乱の世界。
この深刻な現実の自己を凝視する時、餓鬼こそ自己の実相である事に驚きます。
祖先の後生ばかりを案じて、我が身が餓鬼である事を忘れています。
お盆は、亡き祖先を救う日ではなく、今現に倒さに懸って飢え渇き苦しみ続けて、未来永劫、流転せんとする、我が身自身を救う聞法精進の日である事を忘れないようにしたいですね。
AD