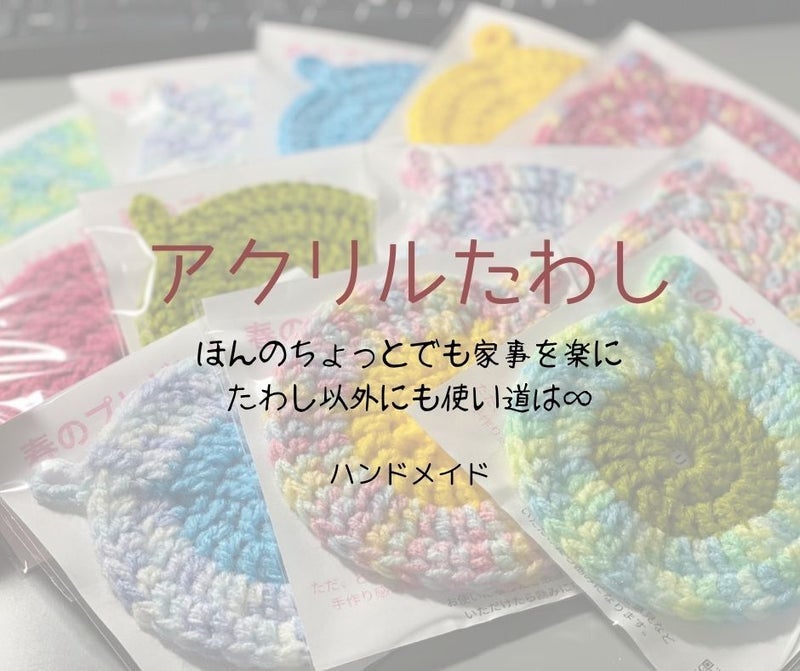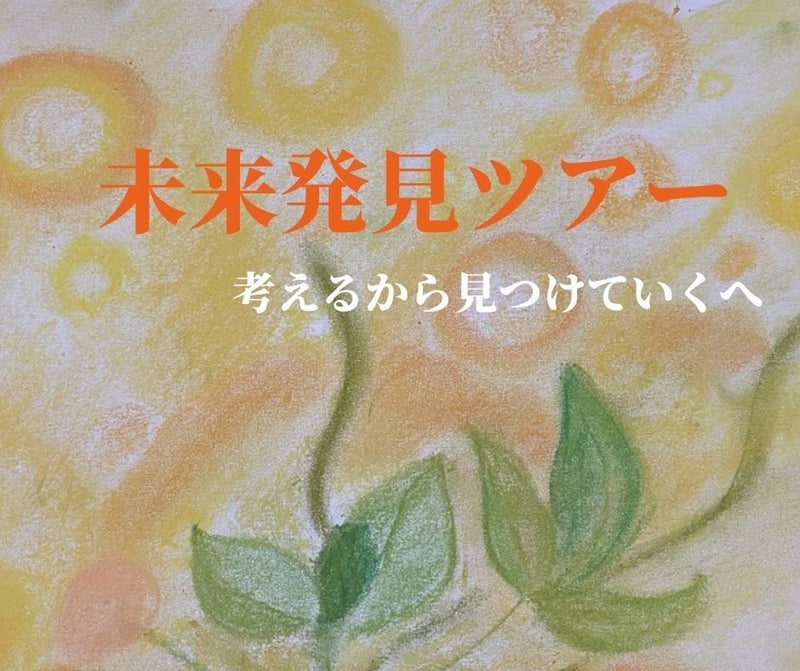みなさん、こんにちは。
明日3/3は女の子の健やかな成長と健康を願う「ひな祭り」ですね。
ひな人形は2月4日の立春。2月19日の雨水の頃に出すといいと言われています。
雨水のころに出すと良縁に恵まれるといわれていることもあって雨水のころにひな人形を飾る人も増えてきました
こちらにひな人形の飾り方を追記しました
うっかり出し忘れていた![]() と慌てて今日出すのは「一夜飾り」になるのでおススメしません。
と慌てて今日出すのは「一夜飾り」になるのでおススメしません。
出し忘れてしまった人は、ひな祭りを食べ物やお菓子などで楽しんでいきましょ!
わたしはひな祭りがやってくると、子どもの頃はひな人形を飾るのが楽しかったなー、お内裏様とお雛様って右と左どっちだっけ?と毎年飾り方がわからなくなったりした子どもの頃の記憶が蘇ってきます。
ひな段の後ろに隠れて遊んでいたこと。
隠れたはいいけど抜け出すときに土台に身体がぶつかって、ひな人形を落としてしまいそうになったこと。
親に隠れてひなあられをつまみ食いしていたこと![]()
幼馴染の家に飾ってあるひな人形は、かご、重箱、御所車がるのに、なんでうちのはないんだろう・・・。
なんてちょっと羨ましく思ったりもしたこと。
そんな幼少期の思い出が、春の暖かさと共に蘇ります。
毎年、当たり前のようにひな祭りにはひな人形を飾り、ひなあられをお供えしているけど
ひな祭りの由来をお話していきますね。
ひな祭りとは
3月3日のひなまつりは、「桃の節句」「弥生の節句」といわれ、女の子の美しい成長と幸福を願うもの。
ひな祭りはもともと五節句のひとつ、「上巳(じょうし)の節句」でした。
《五節句》
- 1月7日の「人日(七草がゆ)」
- 3月3日の「上巳(桃の節句)」
- 5月5日の「端午(菖蒲の節句)」
- 7月7日の「七夕(星祭)」
- 9月9日の「重陽(菊の節句)」
実は古代中国の「川で身を清めて邪気を払う上巳(じょうし・じょうみ)節」が日本に伝わりました。
日本古来の「人形(ひとがた)流し」という厄払いの風習と結びついて、それが平安時代の貴族のおままごとである「ひいな遊び」と組み合わり、徐々に今のような形になったといわれています
上巳(じょうし・じょうみ)の字のごとく、3月上旬の巳(み)の日で、3月に入って最初の巳の日に行われていた上巳節でした。
現在の3/3に固定されたのは3世紀ごろといわれています
この日は古代中国では忌日(いみび)とされ、川で身を清める習慣があった中国では、そのけがれを祓うため水辺で体を清め、厄払いが行われていたのでしょう
日本では紙などで作った人形で自分の体を撫でて穢れを移し、川に流すことで邪気祓いをする行事として広がっていったといわれています。
「流しびな」の風習が、現在でも残るひな祭りの行事のルーツと言われています。
昔は、子どもが生まれると人形をつくって保管しておき、3歳ごろになってから流すという時代もありました
昔は生後1年未満の子どもの死亡率が高く、3歳まで生きられる確率はかなり低かった推測からすると、もともと厄払いの行事だった上巳節が、子どもの健康と成長を祈る行事になった流れに変わっていったのでしょうね
そして、時を経て人形が豪華になっていくにつれ、流さずに素早く片付けるようになったようです
初節句のお祝いと献立
女の子が生まれて初めて迎えるひな祭りを初節句といい、祖父母や親しい方をお招きしてお祝いをします。
当日は、部屋にひな人形を飾り、桃の花や菜の花などの春の花を彩りに添えた祝い膳をいただきます。
祝い膳は
ちらし寿司に、はまぐりのお吸い物が定番で、はまぐりの殻は他の貝の殻とは決して合わないため、貞節のシンボルとされてきました。
さらに、焼き魚や春野菜の小鉢などを添えると、春らしさを感じることができます。
ちらし寿司の具材
エビは、腰が曲がるまで長生きできるように
レンコンは遠くまで見通せるように
豆は健康でマメに働けるようにという願いが込められています。
ハマグリのお吸い物
はまぐりの貝殻はもともと対だったものだけがぴったり合い、貝合わせなどの遊びで使われたことから、良い結婚や良縁の象徴とされ、結婚式やひな祭りで食べる風習があり、一生添い遂げる仲の良い夫婦にちなんでいます。
節句菓子
ひし餅とひなあられ、よもぎ餅、干菓子などをいただきます。
ひし餅
ひし形になっていますが、これは心臓や、桃の葉を表すといわれています。
ひし餅の色や形は諸説あり、ひし餅の白は雪、赤は花、青は若草、黄色は紅葉を意味し、四季を表現しているという説もあれば、植物のヒシ(菱)は、水面に拡がって繁ることから、ヒシ形は成長や繁栄のシンボルとして古くから親しまれ、桃の節句のひし餅には、女の子の健やかな成長と豊かな人生への願いが託されているという説もあるようです
ひなあられ
ひし餅を外でも食べやすくするために砕いて焼いたことが発祥とも言われています
関東地方ではお米の形のままの「ポン菓子」も一般的
花
ひな祭りの別名は、「桃の節句」
ひな飾りとともに桃の花が飾られるのは、旧暦上巳のころに桃の花が開花することと、中国では桃の木が邪気を祓ったり、子孫繁栄をもたらしたり、実が不老長寿をもたらす仙木と考えられ、長寿のシンボルとされていて、門にさしておくと邪気を払うという言い伝えから、祝い花として使われるようになりました
ひな人形をしまうのは
ひな人形を片付けるのが遅いとお嫁に行くのが遅くなる。
なんて、誰に聞いたか?どこで聞いたか?記憶は定かではありませんが、そんな話を聞いたことがあると思います
そういわれるようになったのは、ひな祭りが厄払いとして始まったという由来から、人形を水に流す代わりに素早く片付ける意識が残っていると考えらています
片付けが遅れると、人形に代わってもらった厄が戻ってくるという考えから、早く片付けて休んでもらおうということからといわれているので、片付けは3月4日〜4月中旬の晴れた日にしまうのがおすすめです
季節ごとにいろいろな行事で楽しめるのは、日本の四季のおかげですね
お天気や気候だけではなく、昔から伝わる季節の行事を楽しむことも、じぶんを労わり、大切にすることにつながるとおもっています
そして、四季を取り入れる暮らしは住んでいる家にも安らぎや癒しを取り入れることができるので、すべてではなくても少し季節を取り入れてみてはいかがでしょうか
家のことで気になる方は「開運!間取り鑑定」もお受けしています。
住まいは、その家に住む人が元気で健康でいることで
家のパワーもアップすると、わたしは考えています。
そして、その家で心地よく、楽しく、嬉しく過ごせる空間であることも大切だなと考えています![]()
お知らせ