与党の人達は、その前に人として、いや人の親として少しばかり「政策」が間
違っているとは思わないのだろうか・・・。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~
チェルノブイリ事故(1986年4月26日)のときは、原発から120km離れたウク
ライナの首都・キエフの子供たちすべてが、5月半ばから9月までの間、旧ソ連
の各地の保養所に収容された。

日本でも政府は国内の国民宿舎などすべてを借り切って、被曝が疑われる地域
に住む妊婦と子供たちの収容に踏み切るべきである。
それなのに、日本では政府が逆のことをやっている。福島市と郡山市の学校の
土壌が放射能に汚染されていることを受け、政府は子供の被曝量の基準値を、
毎時3.8マイクロシーベルト、年間20ミリシーベルトとした。これには国内か
らだけでなく、世界から猛烈な批判が出ている。
「20ミリシーベルト」という数字は、「国際放射線防護委員会(ICRP)」が、
「非常事態が収束した後の一般公衆における参考レベル」とされる<年間1~
20ミリシーベルト>のもっとも高い数値であり、大人を対象にしていること
はいうまでもない。
それが特に子供たちにとっていかに高い被曝量であるかは、私の知る限り、
チェルノブイリに汚染された土地のどの地域を居住禁止地区にするかについ
て、1991年にウクライナ議会が行った決定が参考になる。
そこでは1平方キロメートルあたり15キュリー(放射能の旧単位)の汚染地
域を立ち入り禁止地区とする、つまり居住禁止地区に規定したのだ。現在の
単位に換算して、ここに住むと、年間5ミリシーベルト被曝してしまうとい
う理由である。

日本ではその4倍を許容量として、子供たちの学校の使用を許可したのであ
る。また、「毎時3.8マイクロシーベルト」という数字は、いまは死の街と
なったプリピャチ市の数値とほぼ同じである。私はかつて5万人が住んでい
て、いまや荒涼としたプリピャチの廃墟の中に、日本の子供たちが走り回る
姿など想像したくもない。
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/n_nuclear_power_plant_5__20110518_106/story/postseven_20367/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この少年・少女の内部被爆の疑念が解消されない問題に対しては、それこそ
「票に結びつかない」という唾棄すべき思いが内心あるのか・・・。

聞こえの良い言葉を連呼して「国民の生活が第一」の前に将来を託すべき幼
子こそが「国の宝」だからこその「子供手当て」のはすが、一切言及しない
その舌の「醜さ加減」に反吐が出る。
これから老い先短い者達は、票は持っている。しかし「子供を犠牲の延命」
は誰も考えていないだろう、先に子供の避難が浮かびのはずが、その「今後
何があっても子供の生命は守る」とかの表明なら、見直すものを・・・。
どの道、こ政権の先は長くないのは、国民すべからく「呆れた対応」にある
を自覚出来ない「施政者」では・・・。
そして奪われるかもしれない「二度と戻らない」輝く時間はそれがどんな時
代でも「ほろ苦く、そして懐かしさ」そして忘れていけない人としての「情」
において、その機会を失ってしまう危惧は、万死に値する「政権の失政」に
あるとなって来る。
で、男であれば少年となり、その成長期の経験は、その後をそして「振り返
った時」、その時代が輝いて見えるものだろう。
こんな「過失のない子供たち」の不憫な被爆に対して、ずいぶん前に取上げ
た「少年時代」を再び取上げた。

「少年時代」 九十年公開作
「長い道」の原作を藤子不二夫漫画化して、そしてそれが映画となった。
太平洋戦争末期、東京から疎開した少年と、疎開先の田舎の少年の触れ合いを
軸に、切なくも大切な心の成長に寄与する体験を通じて、出会いと別れを日本
の美しい景色と、そして普遍的な少年期からの脱皮を描いて、特にガキ大将の
せつな過ぎる友情に、ほろりとしてしまう・・・。
別れのバックに流れる井上陽水の曲が、より一層、そしてトンネルという光を
失う暗闇が、少年から青年への「決別」を意味して、なんとも「ほろ苦い」想
いを募らせる・・・。
同時に戦争の混乱の中でも少年達にとってその濃密な人間関係が、善き付け悪
気に付け日本的な情緒を醸しだしている。
隣町への外出でも、異国にでも出かける警戒心とか、なんとも過ごしてきた時
間は違えども、活動範囲の狭い幼少期の冒険には共通するものがあり、体験で
しか味わえぬ成長が、そこに生き生きと活写されていた・・・。
この映画でもそうたが、生きることに何の疑問も持たず、その時間の経過を受
け入れ全力でその時を生きている姿は、やはり振り返った中年が切ない苦さを
かみ締める「二度と戻らない愛すべき幼き自分」のその姿・・・。
海の向こうでも、やはり自分の幼少期がやはり「輝いて」それに共感する観客
が多いのは、共通なのだろう。
「スタンド・バイ・ミー」 八十七年公開作
さて、被爆した少年・少女が発病せずに、こんな貴重な時間を過ごせたら、
良いのにと思うしだいで・・・、もしそれらを奪われてしまったとしたら、
日本の損失は、計り知れないものとなる。
少年時代 [DVD]/藤田哲也,岩下志麻,仙道敦子
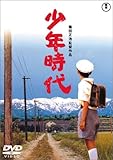
¥4,725
Amazon.co.jp といったところで、またのお越しを・・・。