自分の居場所のない人々の精神性は、嫌われている意識を根底に認識しながら、それ
を殊更「ないもの」として扱い、あるいは無視して「強弁」にこれ務め、自分の都合の良い
妄想を垂れ流す。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
在日韓人歴史資料館開設5周年記念大阪シンポジウム(16日)に出席した各パネリス
トの発言要旨はつぎの通り。
■金宣吉・神戸定住外国人支援センター理事長=上滑りの「共生」という言葉が広が
っている。もっと発信していかなければならない。在日ベトナム人の民族名使用が減
っている。アジアの子どもたちはなかなか本名を名乗れない。
学校現場に本名の教師が一人でもいること、本名で働ける環境を作り出すことが重要
だ。自分は何者であるかは人権の基本だ。ニューカマーの人たちの苦労は我々の歩
んできた苦労と重なっている。
在日がなんら政治的権利を持たぬということは裸で外を歩いているようなもので、非常
に厳しい。「多文化共生」「多民族共生」の本当の中身が問われている。
■伊地知紀子・愛媛大学法文学部准教授=「オモニ学級」など大阪のオモニたちから
は人として生きることとはどういうことなのかを考えさせられた。未来を考えるにあたり、
我々が学ぶものが沢山ある。解放後、公的書類の「通名」使用は「在日の人たちのた
め」とされてきた。政府・自治体による「通名」使用誘導では多民族共生はありえない。
国家とはなにか、共同性とはどのように生まれるのか、連帯感はどういうふうに生まれ
るのかという視点から深く幅広く見ることのできる立ち位置に在日の人びとはいる。
多文化共生社会の実現へ在日の経験の共有と裾野を広げていければと思っている。
■李美葉・多民族共生人権教育センター理事長=日本人を対象に「反差別・人権」に
ついて語ってきた。「差別」はなくなってきているが、まだ沢山ある。自分の子どもたちも
受けた。日本人は在日についてあまりにも知らない。韓流ブームは在日のことを見えな
くさせている。「共生」実現のためには、「在日外国人の先輩」として「差別」と向き合い闘
っていかなければならない。若い人たちが、本当に自由に生きていけるようにしなければ
ならない。我々は今一度、コリアンが歩んできた道を振り返りながら、これからの多民族
社会を真剣に考えていく必要がある
■鄭炳采・民団大阪本部事務局長=行政で「通称名」を認め、誘導していることが通称
名使用につながっている。選択の自由はあるが、名前の持つ意義は非常に大きい。地
方参政権の獲得はもちろんだが、外国人公務員や教員はいても管理職にはなれない
という制限はなくしていかねばならない。民団は在日にルーツを持つ人たちの団体であ
ると同時に、在日外国人の人たちの先駆者としての役割を担っている。これからは在日
外国人の先輩として、もっと彼らと共に諸課題を実現していくことが必要だ。
■白真勲・民主党参議院議員=朝鮮日報の東京支社長のころ、朝鮮日報の特派員も
入居差別を受けた。選挙では「日本と韓国の友好は日本の国益になる」とうったえてき
た。10年、20年前だったら私は当選できなかっただろう。これは日本人が変わりつつあ
るということだ。だが、政治家の頭の中は8割が選挙のことであり、政策の中に「外国人」
はないのが現実だ。外国人に対する不安心理を煽る人たちがおり、非常に残念だ。
先進国のなかで、重国籍を認めず、生地主義を認めず、そして永住外国人の地方参政
権を認めていないのは日本だけだ。
■在日の課題共有 会場参加者の声
全国在日外国人教育研究所(京都市)の小西和治さんは、「未来予測」を当事者の側か
ら発信するタイムリーで、貴重な催しだったと歓迎。
京都国際学園前理事長の宋基泰さんも「韓日の100年を通して、これからの在日の未来
を考えていく良い企画」と喜んでいた。
神戸市の朴真由美さん(31、主婦)は、「とても有意義な時間だった。様々な問題や課題
が残っている、こういったことに取り組めるというのも在日だからこそではないか」と評価。
奈良県の申載季さん(64、主婦)は「やっと子どもから手が離れたので、パネリストたちか
らなにか一つでも学びたかった」と参加の動機を語った。
元高校教員の藤川正夫さんは、公立学校の外国籍教員に対する任用差別について、
「緊急を要する課題」と取り組みへの決意を新たにしていた。(以上)
http://www.mindan.org/shinbun/news_view.php?page=10&category=2&newsid=13525
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
殊更「人権」をたてにして自分達の領域を広げることのみに熱中しているから、それこそ
「村社会」形成の排他性を表立って「差別意識」は、そちら側にあると「身の丈姿勢」は皆
無に近く、「村社会」の論理のみに傾注するから、大多数の国民からは「つまはじき」状態
へと自ら追い込んでいるを気付かない。
そのいびつの姿勢が改まらない限り、意識の錯誤はそのうち自分自身の「二重人格」へと
帰結していく・・・。
と、この「村社会」の閉鎖性をサスペンス・スリラー仕立てにした映画が「ビレッジ」である。
http://www.youtube.com/watch?v=oB55bv4B8LQ
「ビレッジ」 〇四年公開作
辺鄙な地にある「村」は、不気味な森に囲まれ、その森には「怪物」が棲んでいて
村人は「村」から他の地に行くことが出来ずに、また人の往来もない。
小さな社会が形成された村は、独自の「戒律」によって平穏な日々を過ごしていた。
そんな村の若者の中には、違和感を抱く者も出てきて、森に好奇心を抱き、秘かに
森に入り込む者が出て、森の怪物の監視小屋からの「警告音」によって村は大騒ぎ
になる。
と、じわじわと中世の暮らしの「迷信」やら「言い伝え」を忠実に守る村の秩序が崩れ
はじめ、そこに事故で負傷した者が出て、村の診療所では「治癒」が出来ぬ事態と
なって、負傷した若者を慕う盲目の女性が、助けたい一心で村の戒律を破ってでも
町の病院に薬を取りにいくと申し出る・・・。
その決意に村の重鎮である父が、村の成立の秘密と森の怪物の正体を告げて、
いよいよ盲目の女性は、果敢にも一人で森を抜け町への冒険に旅立つ・・・。
しかしそこは足を踏み入れたことのない未知の地であり、町への村の存在を知られ
てはならぬ「戒律」に忠実な怪物の登場とかで苦難を経験するが、教えられた道の先
にあったのは、行き止まりの高い壁であり、女性は意志の強さでそこをも乗り越えて、
むらの外に出た実感を肌で感じるが、盲目の悲しさでそこがどこだか認識でない。
そこに現れる「監視区域パトロール」の車で、観客は一気に村の現状と物語が現代
のものであるを悟り、盲目の女性は目的の薬を手渡されて、勇んで村へと帰っていく
そして重症の若者は、盲目の女性の活躍で一命を取り留める・・・。
森の怪物役を担った村人は、村の重鎮の合議で、森の怪物に「殺された犠牲者」と
みなされ、村の秩序も戒律も守られて、「村社会」は何事もなく、再び平穏を取り戻し
よそ者を寄せ付けない「村」は、誰にも知られず静かに息づいていく・・・。
と、町で被害にあった者達が、町を逃れて村を形成し、そこで小さなコミニティーを共同
生活に平穏を見出し、そして頑迷な意識は次代への教訓として「村独自の戒律」を守ら
せあらされること、また若者の好奇心を森の恐怖で押し込めるという手法で、排他性を
存分に発揮して・・・。
と、人間の「黄金郷」の姿を見せて、穢れなき精神性を堅持している「存在のない人々」
の存在・・・。
だが、ちょっと待って欲しい、文明の利器としての「電気」は、堅固な建物はどうやって
建てた?。
と、精神性は理解出来ても、映像に移る建物には村社会では無理な発展を見せていて
は、違和感がありすぎて、重鎮の者たちの言葉と相容れない不具合が、映像に映って
いては、あの警護隊の隊員の言葉だけでは、「有り得ない話」になってしまう・・・。
ただ現代で「穢れなき世界」を描くとすれば、完全保護区としての「孤立」を見せる戒律
による「縛り」が懸命な方法ではある。
「他にも迷惑をかけないが、迷惑も被らない」不干渉な世界、自己責任で完結する人生
を村人は覚悟を持って遂行する。
と、上の「我が物は我が物であり、醜い性格を隠そうともせず、喚きチラシ」の民族性と
は全く違った「村社会」のそれを見せている・・・。
「干渉されたくないなら、干渉するな」と当たり前の「配慮」に欠けた人々は尊敬される
ことはない・・・。
- ヴィレッジ [DVD]/ホアキン・フェニックス,エイドリアン・ブロディ
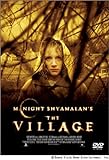
- ¥3,990
- Amazon.co.jp といったところで、またのお越しを・・・。


