コロディ映画というものにもシュールなむ笑いもあれば、ブラック・ユーモアをちりばめた
ものとか、そしてキャラクターそのものが醸す可笑しさとか、笑いの中にも数々ある。
そんなコメディだが、その当時の世相を反映して、それらと相容れない生き方に笑いを
求めると、こんなナンセンスな学生が主人公をする映画になる・・・。
http://www.youtube.com/watch?v=cgMHoNCrR30
「嗚呼、花の応援団 役者じゃのぅ」 七十六年公開作
七十年後半となると、吹き荒れた学生運動も静かになり、世の中自体も保守
的傾向を強めて行く、そんな中アナクロ全開のかなりアブナいバンカラな学生を
主役に据え、無軌道な青春を笑いに変えてエログロ・ナンセンスの王道を突き進んだ
漫画が人気を呼び、その人気から実写化してみれば、見る人はいて二年間に三作品
を公開したのが青田赤道なる応援団親衛隊長をメインにしながら、新入生の目線で描
いて見せる、お色気あり喧嘩ありの当時、ロマン・ボルノに傾斜して行った日活の映画
日活自体が無国籍アクション映画を得意として関係からお色気と、「こんなやつ、おら
んやろ」と思えるトンデモさんだけに、漫画のギャグには七転八倒する面白さがあったが
それを映画化してみれば、そりゃ無理があり、漫画に忠実になれば浮いた存在がより浮
いて笑いも薄ら寒くなる・・・。
ただ、笑い飛ばすバンカラな服装の学生は体育会系に存在し、学生服を特注して裏地は
龍の絵柄とか、刺繍での名前入り、そして極め付けが学生服の詰襟が異常に高く、学生
服なのに威圧感バリバリを、それぞれに見ている若者が多く、またその風体に憧れを抱く
中高生もいて・・・。
この青田赤道は一種のスーパーマンなのだが、とてもどじな点もあり愛嬌もあり好かれる
キャラクターだった・・・。
原作はどうくまんなる人で、成人向け週刊漫画で、名も知らぬ大学の応援団・・・。
その風体のさまはそれでも体育会系学生の威圧感ばりばりに、新鮮さを覚える向きと
毛嫌いする向きと両極端・・・、そこに応援となると、応援なのか脅しなのかスポーツに
おいての応援の威力とか、それらを茶化すにはうってつけのキャラクターだが、根底に
流れるバンカラな覚悟は心地良い・・・。
まぁこんな応援団には、応援されるのははた迷惑かも知れないが、突拍子もなく無軌道
なさまには、閉塞感があふれる時代には風穴を開けるインパクトがあり、男ならちょっとは
憧れを持つ・・・。
何よりスポーツをするでなく、試合とかの応援に命をかけるってのも、それはそれで「かっ
こいい」・・・。何かに熱くなる・・・。
そんな単純さは羨ましいし、応援も受けて見たいと思わせる・・・。
http://www.youtube.com/watch?v=XJsC28KxpwY
総裁選応援 北村弁護士
で、応援で熱いとなれば、二年前の総裁選でのこの人も・・・。
今ではマスコミの総バッシングでメロメロな麻生総理だが、ここまでひどい言われ方される
程の失政は犯していないのに・・・。
メガティブ・キャンペーンに踊らされる国民を見て、北村弁護士は「そこまで言うか」と憤慨し
ていそう・・・。
http://www.youtube.com/watch?v=ZWtbfOwpl8g
熱狂的なロッテ・マリーンズ応援
熱い応援といえば、この野球チームも千葉に移転して大成功だろうし、ここの応援も熱い
良くペタをくれる「かもめ26」さんも、このどこかで応援しているのかしら・・・。
このロッテの以前の惨状を知っているこちらとしては、「世の中、変わったなぁ・・・」
何しろ警備員のバイトで球場のそれも外野席担当していた当時、バイトの方が人数が多く
やることなくて寝ていた・・・、後はホームラン待ち・・・。今はない後楽園球場での思い出である。
それがこの投稿を見ると「熱い」選手もやる気が出るだろう・・・。
http://www.youtube.com/watch?v=83WxY4cZQoU
「応援歌」 湘南乃風
ありていに言えば、応援もやっている選手を力づけたり、あるいはプレッシャーをかけたりと
一概にすべてが素晴らしい訳ではないが、応援するその気持ちはどんな場面でもいいものだ。
たとえ、この「嗚呼、花の応援団」みたいなトンデモ・バンカラだとしても・・・。
- コンプリート「鳴呼!! 花の応援団」/異邦人
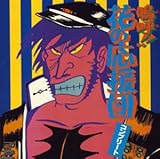
- ¥2,088
- Amazon.co.jp といったところで、またのお越しを・・・。

