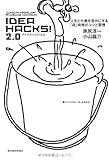IDEA HACKS!2.0 原尻淳一、小山龍介 | 気まぐれエンジニアの セルフ・デザイン&セルフ・マネジメント
- IDEA HACKS!2.0/小山 龍介
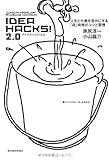
- ¥1,575
- Amazon.co.jp
- IDEA HACKS!2.0 原尻淳一、小山龍介
- 「人はスキーマを持っていることで少ない情報であってもその全体像を把握することができる」
おいう一文が一番印象に残りました。
当然普段からマクロからミクロへとういことで各論から入るのではなく、総論から話ができるように考えているし、人に説明するときも総論から話すように心がけています。
しかし、なぜそれが大事かというと、単に全体を話すだけでなく、相手が知っているスキーマに訴えかけて、類似するスキーマなどを思い起こさせて理解してもらうため、とこの一文を読んで気づかされました。
またよくアンテナを立てて物を見るようにとか、問題意識をもっていないと気づかないとか言われますが、その際のアンテナの1つがスキーマなんだろうなぁと思います。
物を習うときに物真似から入るのもその世界の型(基本形)であるスキーマを覚えるためで、繰り返し練習するのは、いつでもそのスキーマで考え動けるようにするためなのだと理解しました。
以下、気になった文を列挙してみました
- --------------------------------------------------------------------
- 報酬ではなく贈与を優先して考える
- 業界や社会といった「場」を豊かにすることで自分も結果的に豊かになる
- 個人が豊かになるためには、その個人が所属している場が豊かでなければならない
- 世界を少しでもワクワクするものに変えていこうとする献身
- 断捨離で「アイデア環境」を作る
- ①今やらなくてもいいタスクは先延ばしにする
- ②机の上をキレイにする。もしくはキレイな机につく
- ③気分をすっきりさせるための儀式をする
- 運動することで脳が鍛えられる
- 脳と手を直結させるプライベート・ライティング
- →とにかく思いついたことを書き出す
- チェックは後回し、まずはアウトプットに集中する
- 時間的制約の中に身をおくと火事場のバカ力が発揮できる
- →危機的状況が人の能力を引き出す
- アイデアを出すための質問パターン SCAMPER
- S Sustitute? 何かほかの物に置き換えられるか?
- C Combine? 結合できないか?
- A Adapt 応用できないか?
- M Maginity?Modify? 拡大できないか?修正できないか?
- P Put to other use? 他の使い道がないか?
- E Eliminate? 除去できないか?
- R Rearrange?Reverse? 並べ替えられないか?逆にできないか?
- 優れたアイデアは常に想定外
- セレンディピティ(偶然をきっかけに新しい発見をすること)に必要な3つのA
- ・Action 行動
- ・Awareness 気づき
- ・Acceptable 受容
- 正しいことを言いたいという執着を手放し、
自分の直感に従って体の正面でまっすぐに一刀両断にする
- 周りにいる人やリソースなどの環境から「直観を頂いている」
- 他人のために使うと、才能は内在化し、血肉化する
- 人はスキーマを持っていることで少ない情報であってもその全体像を把握することができる
- 同じものを見ていても、発動させているスキーマが異なると
まったく違うものを見ているかのように、入ってくる情報が異なる
- ①スキーマを確認するには何かをアウトプットするしかない
- (自分のセンスを確認する)
- ②他人のアウトプットを見て、自分にフィードバックする
- (自分と他人のアウトプットを比較する)
- ③一度体験をしたら忘れないアハ!体験を繰り返す
- (アート作品を見てうける衝撃...こんな見方があるのか)
- スキーマの獲得に効果的なのが異文化体験
- 経験によってスキーマを獲得し、それが知識にとどまらない知性として働くことによって
新しい目でものごとを眺めることができる
- 「なるほど!」を口癖にする
- →どんな想定外のことが起こっても常に「なるほど!」
- カメラで写真を撮るということは、新鮮な目で風景を見直すきっかけになる
- ツイッター:意図した外部スキーマを構築することができる
- Facebook:情報に対して交わされるコメントによって、スキーマも共有できる
- 膨大な情報が流通する中でどの情報に価値があるのかを見極める【キュレーション】
- 2つの分野でプロフェッショナルになる
- →スキーマが大きく広がり切り口を2つ持てるのでものごとが立体的に見えてくる
- スキーマの獲得は主体的な体験によってのみ獲得できる
- 情報の鮮度とパワーは明らかに一次情報のほうが上であり、斬新なアイデアが生まれやすい
- 現場に入る前は、本も読まず、Webで検索もしないで「素人の眼」を大事にし、
「自分オリジナル」に引っかかった発見や疑問を大事にする
- ソーシャルメディアを使い、複数の視点を確保する
- インタビューではやたらと質問せず、相手の発言を繰り返す
- 子供といっしょにフィールドワークをすると、相手の警戒心を解きほぐしながら
同時に素朴な好奇心に従って研究を進められる
- 情報が絶え間なく循環し、メンバーの関係性が深まっていくと自然と
チーム内でのアイデアの発芽条件が整う
- 定期的にゲストを招き、情報循環を活発化させる
- 対象になりきって対象の中に入り込んで観察する【エスノグラフィー】
- スキーマという道具をコンテキストとして活用することで
アイデアを生み出すのがコンテキスト思考
- スキーマの多様性を把握するのに便利なツールが「ハーマンモデル」
- アイデア会議を成功させる3つのツール
- ①ブレーンストーミング
- ②質問会議
- 課題提示者1人、他の参加者は質問しかできない。
- ポイントは素人を1人入れること。
- →あたり前だと思って気にも留めてなかったことが、
よくよく考えてみると問題解決の突破口になりうる - ③第三レベルの傾聴 グローバルリスニング
- 仮説思考
- ①反対側から見る
- ②両極端に振って考える
- ③ゼロ・ベースで考える
- 直観に基づいて突拍子のない仮説で問題解決する【アブダクション】
- できるだけ早く失敗する(Fail Fast)→ラピッドプロトタイピング
- サイエンス思考:再現性、過去の分析、一つの事実、一貫性
- アート思考: 一回性、未来の創造、多くの仮説、多様性
- ゴッホのひまわりは、ひまわりはこのように描けるのではないか?という仮説提示
- デザインとは中身とかたちの関係だ
(Design ia a relationship between form and content)
- 個人のブランド化→企業と個人の間のシナジーが働き始める
- 経験を積んでも積みっぱなしにせず、仕事の節目節目で経験をこれまでの総括し、
今後の仕事で使えそうなスキルやノウハウを文字に残しておく「自分教科書」
- 会社業務やプロジェクトが終了したら率先してコンテンツエディタとして情報をまとめあげ、
仲間と共有してしまう
- 会社内個人として外部にも通用するスキル人材になるには、自分の「器」を広げることも必要
- 世界に出れば同世代の人たちがライバル
- 業界では当たり前のことでも、他の業界では新鮮なことはたくさんある
- 他の業界人に説明すると、今度は自分の業界の存在意義にも気づく
- 考えるきっかけを得るという意味では、他人に質問するというプロセスも非常に効果的
- 時代を超えた天才のパフォーマンスを見ることによって視野を広げモチベーションを高める
- 身近なとことにも仕事が進むパワースポットがあるはず(カフェなど)
- →自分の普段の立場から離れて考えることができる
- ブランドを作るというのは、「価値の創造」に他ならない
- 仕事だけでキャリアを形成するのではなく、本来やりたいことを
もう1ライン走らせてキャリアを複線化する - →人生が豊かになり、また仕事にもプラスになる
- 子供の頃のあなたの夢はなんだったのか?
- 小学校の卒業文集を読んでみる
- 創造性を伴う活動は「疲れない」
- 消費するだけの視点と創造も踏まえた視点では着目点にも差異が生じる
- ライフワークがあれば気兼ねなく、いろいろな実験ができる。
振り子のように経験とスキルを行き来させ、増幅できる
- 今まで記憶に残っている出来事は自分がアクションを起こし、勇気を出して行動したことでは?