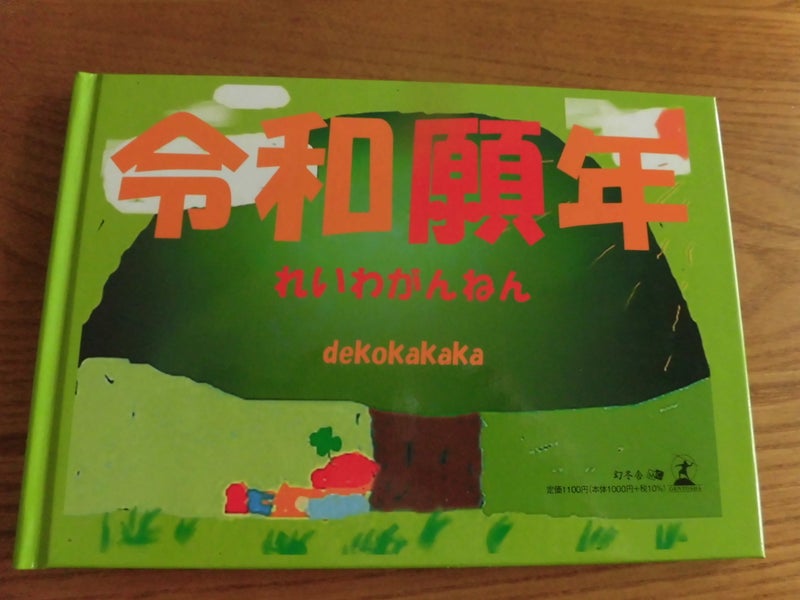今の気持ちを俳句で綴ってみよう!
気楽さん
俳句の日だって!
※
土曜日は
気楽道場
たのも~しに
※
今日は木
今から鍛え
土曜へと
※
俳句かな
どうかな出来る
出来ないね
※
うだるなか
俳句をうなる
びっしょりとや
※
鳴いている
蝉も暑いと
俳句かな
※
なにげにね
暦を見れば
秋模様
※
うそだよね
そんな筈ない
此の暑さ
※
よ~いどんと
かけごえだけは
俳句かな
※
止まらない
俳句は此処に
置いとけば
▼本日限定!ブログスタンプ
俳句の日・俳句記念日(8月19日 記念日)
「俳句の日」は、
正岡子規研究家で
俳人の
坪内稔典らが提唱し、
1991年(平成3年)に制定。
「俳句記念日」は、
俳句作家の上野貴子氏が主宰する「おしゃべりHAIKUの会」が制定。
日付は
「は(8)い(1)く(9)」(俳句)と読む語呂合わせから。
句会などを通して、
俳句の楽しさ・奥深さ・季節感の大切さなどを知ってもらうことが目的。
記念日に合わせて
イベントや大会などを行っている。
「俳句記念日」は一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。
俳句について
俳句は、
主に五・七・五の十七音で表現され、
「世界一短い詩」とも言われる。
江戸時代に俳諧が流行し、
最初の五・七・五の発句を重要視したのが
松尾芭蕉(1644~1694年)である。
芭蕉の有名な句として「古池や蛙飛びこむ水の音」がある。
そして、
明治時代になると
正岡子規(1867~1902年)によって
近代の俳句が確立された。
生涯に
20万を超える句を詠んだ
>物凄いね!
子規の作品のうち最も有名な句として
「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」
がある。
>dの中学校時代
同級生の男子
俳句を作らされたんだね
国語の時間かな!
よく覚えてないけど
此の子ね
「柿食えば鐘が鳴るなり南蔵院」
って
詠んだね
>先生が
何かどっかで聞いたことが有るような
>皆どっと
>こんなに楽しかった授業の思い出は有りません
はっきり覚えている子規の句?
☆くんの句だね^^
☆くんどうしてるかな
戦争直後
長屋みたいなところに住んでいた☆くん
南蔵院が傍に有ったんだよね
因みに
南蔵院はdの実家の菩提寺です^^
上記の芭蕉の句と並んで俳句の代名詞として知られている。
「俳句を作る」ことを「俳句を詠む」と言うが、
「詠む」はもともと「読む」と同じ言葉で、
「数を数える」という意味に由来する。
現在でも「サバを読む」「票を読む」「秒読み」などの使われ方が残っている。
数を数えることが、
文字を一字ずつ声に出して読み上げることに通じるとして、
「詠む」は「文章を読む」という意味になった。