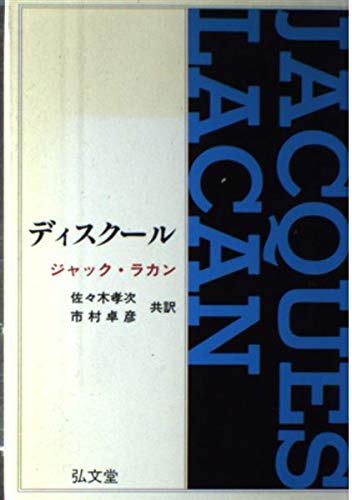決して著者の研究の蓄積を軽視するものではないが、本書の内容は最初の「まえがき」と第3章の一文に言い尽くされている。つまり、
出発点は江藤淳(p.14)
そして
江藤淳は効果が上がらなかったことを理解していた(p.181)
はい、おしまい。
WGIPは江藤淳がアメリカで発見した(アメリカの研究者からコピーを渡された)ことになっているが、もしこれが別の歴史研究者によって発見されたとしたら、「ドラフト(下書き)」と記された文書のWGIPという言葉に「戦争についての罪悪感を日本人の心に植え付けるための宣伝計画」などという恣意的、作為的、というより扇情的な訳はあてなかっただろう。ためしに機械翻訳にあててみよう。
War Guilt Information Program(戦争責任情報プログラム 訳:DeepL)
DeepLによる直訳調の違和感はともかく、元の文字列に「植え付ける」という動詞は何処にも見当たらない。
1990年代後半から今もはびこる保守論壇のGHQ陰謀論は江藤淳が出発点だ。そして江藤自身も『閉された言語空間』の中でWGIPはさして効果がなかったとしている。
はい、おしまい。御名御璽。
と、本来ここで終わる話しなのだ。しかしいまGoogleで「WGIP」という言葉を検索すると約 183,000件、AmebaBlogだけでも428件の記事がヒットする。内容は推して知るべしだろう。
著者の賀茂道子氏は国会図書館のキーワード検索で「自虐史観」という言葉が1996年あたりから急増していると指摘している。その原因とされている「WGIP」も同じように増加しているはずだ。
賀茂氏はそれが「作る会」の発足と同時期だとしているが、ネットという閉された言語空間にまで広まる契機となったのは小林よしのり『戦争論』だろう。
普通ならここから小林よしのりの悪口を始める所だが、彼のコロナ騒動への応接を見てから、別の見方もあるのではないかと思うようになった。
小林よしのりはコロナ対策のために経済を止めるべきではないという。何故なら経済苦による自殺者ウン万人の時代に再びなってしまうからだという。
はて、小林よしのりのパブリック・イメージに自殺問題専門家というものはあっただろうか、と考える(荻上チキ氏あたりならわかるが)。ゴー宣の何処かでは取り上げていたことはあるのか知らないけど、単著で『自殺論』とかないよね。
そして「自殺論」という言葉からふと思い出したのが「戦争があると自殺者が減る」という社会学の知見だ。戦うべき、滅殺すべき「敵」の出現と国家の勝利という大目標は人を高揚させ自殺は減る。精神病患者も減るという。
雑誌連載から単著『戦争論』が出版された1995年から1998年にかけて、日本の自殺者数は激増している。
警察庁の自殺統計に基づく自殺者数の推移
「作る会」の発足や『戦争論』の出版が自殺者激増の原因だと言いたい訳ではなくむしろ逆だ。
小林よしのりは自殺激増時代に面接して無意識的に日本を「戦争状態」にして自殺を防遏しようとしたのではないか。事実、近代化以降で日本で一番自殺率が少なかったのは太平洋戦争期だ。そして近年自殺者数が減り続けていたのがロシアだ。ウクライナ侵攻は当事者の感覚からすれば8年前のマイダン革命の頃から始まっていたという。ロシアで自殺者が減り始めたのはウクライナ騒乱の一年後の2015年。ロシアにおいて戦争状態はその頃から始まっていたのだ(ウクライナのデータは不明。
しかし日本では戦争状態を作り出す為の最大の障壁がありそれが日本国憲法だ。潜在的自殺志願者に擬制的な大目標(憲法改正)を与えればその実現までは彼は生きて行ける。
1997年のエレファント・カシマシ「昔の侍」の歌詞はこの時代の雰囲気をよく伝えている。
もちろん改憲派の実存的心情を唄っているようにも聞こえる歌詞を是としているわけではない。宮本浩次は「戦う術」があった時代にはもう帰れないので「さよならさ」と決別している。
新刊書店の書架を見る限りWGIP神話は一時退潮したかに見えたが、古本屋やWebのログにはにはおどろおどろしい煽り文句とともに今この時も再生産され続けている。賀茂道子さんのような真っ当な歴史研究手法に根ざした実証研究もこのクソ熱い昨今の日本の熱帯化に向かって扇風機で立ち向かうようなものだろう。
そして今後も扇風機で立ち向かい続けて欲しい(絶唱。