=自己宣伝= 暇なら読んでチョ
執事の読書室 http://plaza.rakuten.co.jp/deaconblues/
記事一部追加(完了)
http://ameblo.jp/deaconblue/entry-10301314656.html
☆ 「休日モード」の投稿が載り始めた掲示板は,「お気楽」や「toshi」あたりだったかなと思う。「休日モード」と断って書く理由は投稿の内容が長くなることで単純掲示板時代によく見られた「ログ流れ/流し」のトラブルを避ける目的があったからだろうと思われる。
☆ 「ログ流れ/流し」とは,単純掲示板において長文の投稿が入ると,それ以前の投稿が遥か遠くに押し流されてしまうことをいい,中には確信犯的に長文の投稿を入れたり,投稿を巡る議論でヒートアップしてくると,相手をねじ伏せんばかりの長文投稿を書き始める者もいたりするので,長文投稿者は疎ましがられることがあった。
☆ これに対して「休日モード」という断り書きを入れる投稿者は,自分のポジション或いは興味のある分野(銘柄)について独自の考察を表明するのが目的で,それに基づく議論もOKという立場であった。もとより休日であれば場も立っておらず,長文投稿に対して長文で返答を書く余裕も出来る。そういう事もあって,これらの掲示板では「休日モード」ののんびりした雰囲気の中,銘柄発掘や市場の話題についての真剣な議論が一部に見られたのも事実だ。
☆ 10年以上前の話である。当時はまだネットの揺籃期に近く,ブロードバンドもなければHP構築にはHPビルダーが必要な時代であった。だから今で言えば自分のブログに書くようなことも,こうした「自主的な掲示板」への投稿(むしろ「寄稿」感覚があったと言っても良い)によるものが全てであった。この傾向は,この時期一部の投資家達のファイナンシャル・リテラシー養成に大いに寄与する反面,情報のフリーライドを求める「クレクレ投資家」やそれにつけ込む一部の悪質な運営者(傍で見ている分には中々面白かったが)をも養成してしまったきらいがある。
☆ このあたりの事情は米国でも同じで,『東京ジョー』という本が貴重な記録として残っているが,孫正義の「タイムマシン理論」ではないが,数年足らずの速度で一気に日本のウエブ(1.0ですかな=藁=)でも同様の病状が見られるようになった。そしてこの病理を決定付けたのは(初代運営者の意思とはほぼ関係なく)「あめぞう(株式)」に代表される巨大掲示板(あめぞうを1ちゃんねるとすれば。。。以下略)の登場であった。ここにファイナンシャル・リテラシーの萌芽(グリーンシュート)は物の見事に摘み取られていってしまうのだが,それはそれで仕方ない。インターネットの病理は,そのまま孤独で病んだ現代社会の病理であり,形を変えてもその本質はオルテガやリースマンが指摘した20世紀型の大衆社会社会(病理)と何の変りもないからだ。
- 大衆の反逆 (ちくま学芸文庫)/オルテガ・イ ガセット
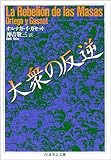
- ¥924
- Amazon.co.jp
- 孤独な群衆/デイヴィッド・リースマン

- ¥4,725
- Amazon.co.jp
=続くかな?=