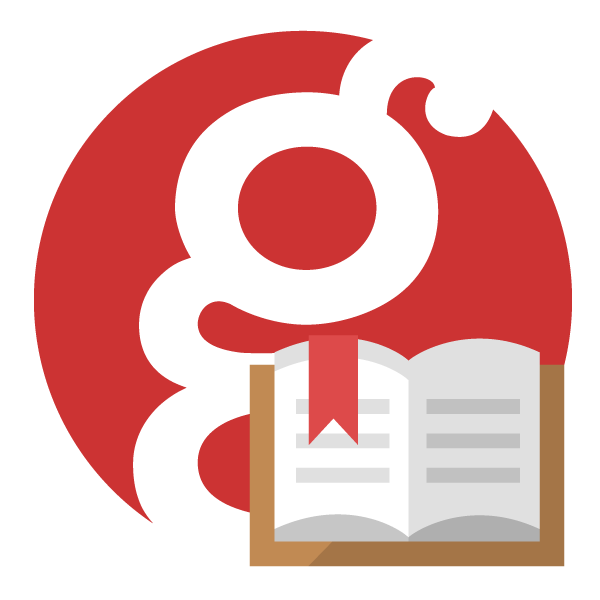令和七年の御題は「夢」
また作家の頭を悩ませる言葉ですね。
では、来年の予想を
①夢見草【ゆめみそう】
実はこれ桜の雅称です。なかなかおもしろいですよね。
桜の絵や、桜の意匠、桜色の釉薬、桜の象嵌など色々な技が考えられます。
なつめなら夜桜棗をそのまま夢見草として使えそうですね!
②邯鄲の夢【かんたんのゆめ】
盧生という貧乏な書生が、趙の都・邯鄲で栄耀栄華が意のままになるという枕を仙人から借り受け、うたた寝をした。このあいだに、50年余の栄華の思いを遂げることができたが、夢が覚めると、炊きかけの粟もまだ煮えておらず、自分は相も変わらぬ貧乏書生であったという、李泌の物語にもとづく説話。
邯鄲城や、枕の絵などもありです。道具組みとして旅枕を邯鄲の夢として使うのもありですね。
③胡蝶の夢【こちょうのゆめ】
夢と現実の境があいまいで、区別できないことのたとえです。
荘子(荘周)による、夢の中の自分が現実か、現実のほうが夢なのかといった説話に基づく故事成語。
蝶の絵や、象嵌、透かしなど、色々出来そうですね。
個人的には蝶形の窓とか面白そうだなぁ~と思います。
道具組みとしては、三蝶蓋置などを使うなどもありですね。
④槐夢【かいむ】南柯の夢【なんかのゆめ】
淳于棼という人が、酔って古い槐の木の下で眠り、夢で大槐安国に行き、王から南柯郡主に任ぜられて20年の間、栄華をきわめたが、夢から覚めてみれば蟻の国での出来事にすぎなかったという、唐代の小説「南柯記」の故事成語。
邯鄲の夢と似たようなお話ですが、こちらは槐の木と眠る人の絵になりますかね。
蟻塚に似た稲塚花入などにつける銘としてもいいかも?
⑤槿花一朝の夢【きんかいっちょうのゆめ】
白居易「放言」にある一節で、栄華がはかないこと。
木槿の花を描くなんてのものもいいですね。ムクゲの形にするというのも茶盌ならあり。
⑥春夢草【しゅんむそう】
牡丹花肖柏による和歌集および連歌集。和歌集は永正13年(1516)から永正15年(1518)頃の成立とされ、連歌集は永正13年(1516)頃の成立とされている歌集の名前。ここから一首を取り出して書くのもまた一興。
ここに掲載されている和歌を一首軸として掛けるのもいいですね。
⑦酔生夢死【すいせいむし】
「程子語録」にある話で酒に酔ったような、また夢を見ているような心地で、なすところもなくぼんやりと一生を終わることをいいます。瓢箪を持った仙人の絵でも描いて、酒を煽ってる姿は一興でしょう。
道具組みとしては、瓢箪関係のものや、瓢の材などがいいでしょうか。
⑧竹久夢二【たけひさゆめじ】
今でもコレクターが居るほど人気の高い絵師・竹久夢二の絵の道具なんて素敵じゃないです?
⑨平家物語
冒頭に「春の夜の夢の如し」という一節がありますから、これもありですよね。
琵琶法師の絵なんて如何でしょう?
琵琶の香合が道具組みに使えますね!
⑩夢窓疎石【むそうそせき】
解説は面倒なので辞書をリンクします。
⑪夢双窓【むそうまど】
無双窓と書くのが本来だそうですが、夢双窓ともかくそうです。
こんなところでしょうか。
作家さんの発想の一助になれば幸いです。