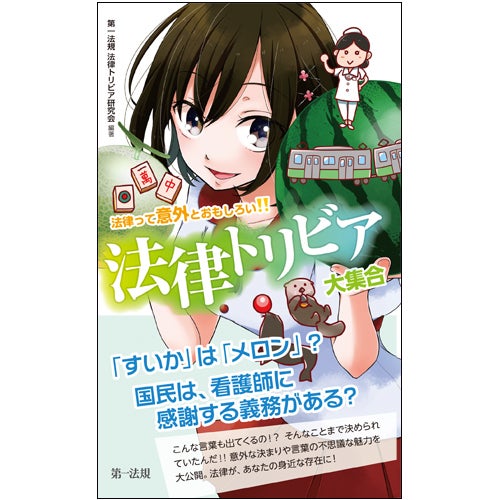こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です![]()
最近、勉強系ユーチューバー、特に数学の講義をするユーチューバーさんが大勢いますね。
学生のころは苦労した数学ですが、話が面白いので、ついつい動画に見入ってしまいます。
さて、法律の中には、少し込み入った計算式が書かれているものがあります。
「農地法施行法」という法律には、農地を買った人がさらに他人に売った時は、
定められた計算式に沿って算定された金額を国に支払わなければならないとされています。
その計算式が、
というものです。
(支払金の徴収)
第14条第1項
Pやnといった記号が何を意味しているかを、
条文から読み取って、置き換えながら計算をする必要があります。
○「÷」と「-」が一つの数式に使われている
ちなみに、「÷」という記号は、法律に使われている例は見当たりませんでした。
政令では使われている例があるのですが、その中で、
割り算を表す「÷」と「-」(「括線」といいます)が
一つの数式に同時に使われている例がありました。
それは、「指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令」(昭和35年政令第54号)
という政令の第11条に出てくる、

という計算式です。
こちらは、計算式の中でPやnといった文字を使わずに、
長い括線を使った分数がありますが、分子をよく見ると、「÷」の記号が使われています。
「それなら、÷の後の部分を分母に持っていったほうが分かりやすいのでは?」
とも思いますが、このようにして書くことで
ひとかたまりの分子としての意味があるのでしょう。
全体が長いので、これも計算式をよく見て、間違えないようにしないといけませんね。
(この記事は、2019年4月24日時点の法令情報に基づいています)
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
法令がもっと身近に!
”カシャ”から始まる法令検索アプリが登場!
▼ いますぐダウンロード! ▼
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
いかがでしたでしょうか。
ブログ本『法律って意外とおもしろい 法律トリビア大集合』もぜひご覧ください!
是非、次回もお楽しみに![]()
![]()