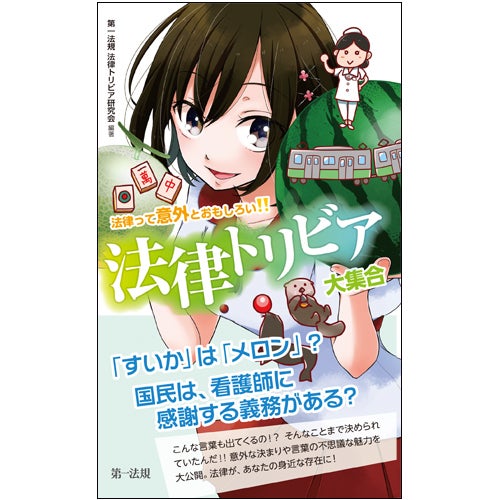こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です![]()
法律という切り口から、鉄道の世界を探る「法鉄」シリーズ。
前回の記事では、車掌さんに関する規定を見てみましたが、
その最後に、プラットホームの長さについての規定が登場しました。
多くの人たちの出会いと別れの舞台である、プラットホーム。
そこには、どんな決まりがあるのでしょうか。
![]()
![]() 法鉄記事の一覧はこちら ⇒ 「法鉄」の世界 ~ 記事まとめ
法鉄記事の一覧はこちら ⇒ 「法鉄」の世界 ~ 記事まとめ ![]()
![]()
○プラットホームのサイズ
まず、プラットホームの長さについては、前回ご紹介したように、
・そのプラットホームに停まる列車の、一番前の旅客車から、一番後ろの旅客車までの
長さ以上であること
・ただし、車掌がそれ以外の車両に乗る場合は、その車両も含めて長さを決めなければ
ならないこと
という規定があります。
★鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)
(プラットホーム)
第36条第1号
この規定に続いて、プラットホームの幅についての定めがあります。
それによると、
・プラットホームの幅
・プラットホーム上にある柱や壁と、プラットホームの端との距離
は、お客さんが安全に、そしてスムーズに移動できる長さであることが必要とされています。
★鉄道に関する技術上の基準を定める省令
(プラットホーム)
第36条第2号
○お客さんがスムーズに移動できるように
また、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」によると、
新しく旅客施設を造るときや、大規模な改良を行うときなどは、
高齢者や障害者の方がスムーズに移動できるように定められた規準に適合することが
必要とされています。
★高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)
(公共交通事業者等の基準適合義務等)
第8条第1項
この規定に基づいて、
「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令」
には、プラットホームについて、以下のような詳細な基準が定められています。
・プラットホームの端と車両の床面の端との間隔は、できるだけ小さくする
・プラットホームと車両の床面は、できるだけ平らであること
・隙間や段差があるときは、車いすでも乗り降りができるような設備を備える
(※よく駅員さんが、車いすの人が乗り降りできるように、板を渡していることがありますね)
・排水のための傾きは、1%が標準
・床の表面は、滑りにくい仕上げをする
・ホームドアや点字ブロックなどを設置する
・列車が接近したら、文字や音声で警告する設備を設ける
・照明が設置されている
★移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)
(プラットホーム)
第20条第1項
・・・
○危険物が通る配管は、プラットホームから離れたところに設置しましょう
「危険物の規制に関する規則」と、
それについての詳細を定めた「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」
によると、
危険物が通る配管を地上に設置する場合は、
1日に2万人以上が利用する駅のプラットホームから水平距離で45メートル以上
離れていなければならない
・・・とされています。
★危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)
(地上設置)
第28条の16
★危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)
(施設に対する水平距離等)
第32条
○同じプラットホームで乗り継ぎができるようにしましょう
「鉄道事業法」と「鉄道事業法施行規則」によると、
鉄道事業者は、他の事業者と協力して、お客さんがスムーズに列車を乗り継げるように、
同じプラットホームで、対面で接続することなどの努力をしましょう・・・
と定められています。
★鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
(乗継円滑化措置等)
第22条の2第1項
★鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)
(旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置)
第37条の2
このように、プラットホームについては、
私たちが安全でスムーズに鉄道を利用できるように、
多くの決まりが定められていることが分かりました。
(この記事は、2018年8月20日時点の法令情報に基づいています)
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
いかがでしたでしょうか。
ブログ本『法律って意外とおもしろい 法律トリビア大集合』もぜひご覧ください!
是非、次回もお楽しみに![]()
![]()
by 第一法規 法律トリビア編集担当