独特の歴史を遂げた沖縄の城(グスク)
沖縄県の城は「グスク」と呼ばれ、本土とはまったく異なる歴史と文化で成り立っています。グスクはかつて「御城」とも書かれ、12世紀から16世紀にかけて、沖縄の各地を支配していた「按司(あじ)」と呼ばれる豪族層が築いた城のことを指しています。
沖縄本島は、1322年ごろから1429年までは「三山時代」と呼ばれ、北山・中山・南山の3つの国が支配していました。その後、勢力分布の変遷により、1429年に琉球王国が成立。明治維新後の廃藩置県で滅亡するまで存在したのです。
沖縄県には200から300のグスクが存在すると言われ、2000年12月には「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として、5つのグスクと4つのグスク関連遺産が世界遺産に登録されました。
沖縄の城(グスク)はココがおすすめ!
世界遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群」には、5つのグスクと4つのグスク関連遺産が世界遺産に登録されています。この中でも特に見どころが多い5つのグスクを紹介します。

大陸の文化を色濃く受けた沖縄の首里城
2)なだらかで美しい曲線の城郭が目を引く「浦添城(うらそえぐすくじょう)城」
浦添城(うらそえじょう、浦添城跡)は、沖縄県浦添市にある城(グスク)跡。1989年(平成元年)8月11日、国の史跡に指定されている( 浦添大公園)。
浦添大公園)。
浦添城跡北側崖下中腹には浦添ようどれがある。土台は隆起珊瑚礁が長さ約400メートル続いている断崖の上に築かれた。舜天王の時代に創建され、12世紀-15世紀初頭にかけて舜天、英祖、察度の3王朝10代にわたって居城した所との伝承をもつが史実かどうかについては確証を欠いている。規模は、東西約380メートル、南北約60ないし80メートルで、北は急崖をなしているが、南は緩斜面となっている。

なだらかで美しい曲線の城郭が目を引く「浦添城(うらそえぐすくじょう)城」
知念城
![知念城 [1/2] 海を見下ろす断崖上に築かれた新旧グスク – 城めぐりチャンネル](https://akiou.files.wordpress.com/2019/06/chinen_gusk-09_2313.jpg)
具志川(ぐしかわ)城跡は、沖縄本島の最南端である海岸の断崖にあります。城門のある東側以外は、三方すべて海に囲まれており、城跡からはダイナミックな風景を望むことが可能。
具志川城が築城されたのは正確には不明ですが、遺物から推測し13~15世紀頃に使用されたとされており、1972年(昭和47年)には、国の史跡として指定されました。石垣は基本的に野面積みが採用されていますが、城門には切り石を使用して積まれた跡も確認することができます。
城跡内は20分程度で周ることができますが、足場が不安定であるため、歩きやすい靴で観光すると良いでしょう。

玉城城跡 琉球創生の神アマミキヨによって築かれた伝説を持つ
玉城(たまぐすく)城跡は、沖縄県南部にある南城市に存在する史跡です。1987年(昭和62年)に国の史跡として指定されました。玉城城の築城主や築城年数が不明であり、「アマミキヨ」と呼ばれる沖縄の開闢の神様、もしくはアマミキヨの子孫が築いたとされています。そのため玉城城には「アマヅツ城」という別名もあり、かつては琉球国王も参拝した「天つぎの御嶽」があるということから、観光だけでなく参拝を目的に訪れる人も。
標高およそ180mの立地であるため、晴れた日には美しい風景を望むことも可能。玉城の城門は、自然の一枚岩をくりぬいて円形に造られています。

2)なだらかで美しい曲線の城郭が目を引く「中城城(なかぐすくじょう)跡」
中城城跡は、標高150m以上の陵上地帯に立つ山城。中城村と北中城村にまたがり、東北から南西に直線状に伸びた城郭が特徴です。
築城年代は分かっていませんが、14世紀の後半には築かれたとされています。1440年頃、座喜味城主だった「読谷山按司:護佐丸」が王朝の命令により移ってから、当時の最高の築城技術を駆使して増築しました。
6つの郭で成立し、琉球石灰岩で積まれた城壁がなだらかで美しい曲線美を作り上げています。太平洋戦争の被害がきわめて小さく、当時の原型をほとんど残していることから、文化財的な意味でも高い価値があります。
軍事的な要衝としてもその面影が濃く、東側には中城湾や太平洋、西側には宜野湾市や東シナ海。そして北側には勝連半島や読谷方面、南側には与那原や知念半島をぐるっと見渡すことができるため、沖縄本島の一大景勝地としても有名です。

中城城(ナカグスクジョウ)は沖縄本島の一大景勝地
(3)「続日本100名城」に選ばれた「座喜味城(ざきみじょう)跡」
築城の名人として、中城城の増築も行なった、読谷山の按司・護佐丸の手により、15世紀はじめ頃に築かれたとされるグスクです。標高約120mの丘陵地に立ち、最高部からは読谷村をぐるっと見渡せる素晴らしいロケーションが楽しめます。
2つの郭で構成された城壁は、ダムのアーチ構造のようでとても優美。地盤が弱くても強固な構造です。城壁は主に「布積」という方法で石が積まれていますが、「相方積」や「野面積」といった技法も使われ、沖縄の城(グスク)での主な石積み技法を一度に見ることができることも特徴です。

座喜味城(ザキミジョウ)は、標高約120mの丘陵地。読谷村をぐるっと見渡せる素晴らしいロケーション!
糸数(いとかず)城跡 壮大な城壁が残る南部最大のグスク
慶良間列島まで見渡せる高台に、中世をしのばせる壮大な城壁が続く。沖縄本島南部最大級のグスクである糸数城跡は、玉城城の西の守り城として築かれたそう。琉球石灰岩を積み上げた城壁、天に向かってそびえ立つようなアザナ(物見台)の景観はまるで映画のような迫力。
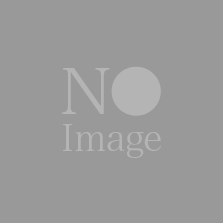
安慶名城(あげなじょう、琉球語: あげなグスク、あげなグシク)は、沖縄県うるま市安慶名にあったグスク(御城)の城趾である。安慶名闘牛場に接した丘がグスクで、ほぼ全周石垣による輪郭式の縄張りが堪能できます。
安慶名城(あげなじょう、琉球語: あげなグスク、あげなグシク)は、沖縄県うるま市安慶名にあったグスク(御城)の城趾である。
15世紀(三山時代)から16世紀にかけて同城を拠点に沖縄本島中部一帯を三代にわたり支配した安慶名大川按司(英祖王の男系子孫)の拠点として知られ、1972年(昭和47年)5月15日に国の史跡に指定された。
天願川の平地に隆起した珊瑚性石灰岩の岩塊の断崖と傾斜を利用した山城で、自然の岩と岩との間に石垣や城門を構えている。形態は、外側と内側に二重の石垣を巡らす輪郭式のグスクである。城の北に天願川が流れており、その別名が「大川」であったことから安慶名城も「大川城」という別名を持っている。

安慶名城(あげなじょう、琉球語: あげなグスク、あげなグシク)は、沖縄県うるま市安慶名にあったグスク(御城)の城趾である。
(4)当時の風景をバーチャル体験できる「勝連城(かつれんじょう)跡」
沖縄の中でももっとも古いとされるグスクで、その歴史は12世紀ごろまで遡ると言われています。
元々は、勝連半島を勢力下においていた按司の阿麻和利(あまわり)の居城で、阿麻和利は東アジアとの貿易を進めるなどして地域の繁栄に努めました。
高い山の断崖を利用した構造は難攻不落(攻撃するのがむずかしく、たやすく陥落しないこと)と言われていますが、なだらかな曲線を描く城壁は優雅さもただよわせます。グスクの最上部までは石造りの階段を歩く必要がありますが、南には中城湾、東には海中道路が見えるなど、その景色は最高です。
休憩所と城郭内にはWi-Fiが通り、城内の各ポイントでは、当時の風景を再現するバーチャルツアーをスマートフォンで楽しめるなど、ハイテクな観光スポットでもあります。

勝連城(カツレンジョウ)はハイテク城。当時の風景をバーチャル体験できる。
(5)首里城に匹敵するワイドさが自慢の「今帰仁城(なきじんじょう)跡」
沖縄本島北部の本部半島にあるグスクで、「北山城」との別名でも知られている今帰仁城。日本100名城にも選定される名城です。
面積は約4ha、城壁は全長1.5kmもある規模は、首里城に次ぐ圧倒的なスケール。琉球王朝の成立前の三山時代に「北山王」の居城として作られた城で、琉球王朝の成立後は、王府から派遣された監守の居城とされたといわれています。
石垣は「野面積み」といわれる、もっとも古い工法を見ることができます。
標高約100mの高台にあるグスクで、城跡の「御内原」というポイントからのロケーションは最高です。
毎年1月頃には、カンヒザクラが咲く桜名所でもあり、これは「日本一早く咲く桜」として人気です。

今帰仁城(ナキジンジョウ)のカンヒザクラは「日本一早く咲く桜」として人気
以上となりますので、こちらのお城は、入場料や、整備が上手くされていなとこがあったりしており、
サバゲーや、フラッグパーティー、コスプレといったインスタ映えとして非常に利用する事が出来ますので、
良かったら、行ってみる事によって、その時代の、歴史を感じる事が出来、自分が城主として。昔の気持ちを
味わってみるのもいいかもしれませんね。
