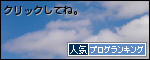私の主治医は「副作用が心配だから、薬は飲ませたくない」が最近の口癖になっている。
一応、診断では「自閉傾向の注意欠陥障害」と「全般性不安障害」という2つの診断名が付いているけど…実際の治療(?)は毎週のカウンセリングと2週に1回のお話しを中心とした診察(精神療法)を受けていて、薬は眠れないので睡眠薬のみ処方してもらっている。
(最近はあまり感じていないけど)不安感や、発達の偏りから来る感覚過敏や気分の変調に対しては「薬は根本的な解決にならない」とか冒頭に書いた口癖で、これまでずっと投薬ナシで薬に頼らずに乗り切る方法を一緒に模索したり、アドバイスをもらったりしている。
某掲示板で「全般性不安障害だけど、薬は睡眠薬しかもらっていない」という書き込みをしたら「睡眠薬しか出さないのはヤブ医者だ」というレスをされた事がある。
一部の人から私は「神経質な投薬治療反対派」だと思われているようですが、私は「投薬治療"消極"派」なだけです…必要のない薬は欲しいとは思わないし、私の抱えている問題は薬だけではどうにも出来ないという事をきちんと理解しています。
薬に対して神経質なのは当然のことだと思います…特にメンタルの薬は副作用が強いものが多く、一歩間違えると命に関わったり、後遺症が残るものもあります。
私がこれまで睡眠薬や抗不安薬、一部の抗うつ剤しか処方されなかったことや、今の主治医が「副作用が怖いから」と言って安易に薬を処方しないのはヤブだからではなく「症状や障害だけでなく、私の性格などあらゆる面を考慮して」の結果だと思うのです。
前にも書きましたが、メンタルの病気は「環境・性格・気質などの要素が複雑に絡み合って」発症するもので、最近言われている「脳の機能の異常」と考えて結論づけてしまうのは非常に短絡的であり、その人の全体像ではなく「その人の症状や障害だけ」に目が行ってしまいこれでは病気が治るどころかかえって悪化する危険性もあるのでは?と思うところがあります。
例えば、全般性不安障害の場合…単に薬で不安を抑えるだけでなく「どうして不安になるのか?」「どうすれば不安が起こりにくくなるのか?」という事も一緒に考えていかないと根本的な解決には全くならないと思うわけです。
体の病気でいうなら「生活習慣病」の場合も、薬を飲むだけでなくそれと並行して「生活習慣の見直し」も指導されるものです。
メンタルの薬は増やすのは簡単ですが、それを減らしたり止めるのは難しいのです…「副作用がでたらやめればいい」という医者は多いですが、それは行き過ぎた効率主義であり、そもそも患者に対する「思いやり」が欠如していると思います。
患者のリクエストに応じて処方せんを書くような医者は論外…こういう人は薬売りにでもなるべきです。
この問題に関しては患者の方も考え方を改める必要があると思います、とりあえず薬をもらうとか薬を飲めば治る(かもしれない)という考えを捨てるべきだと思っています。
メンタルの病気でも、発達障害でも「自分を理解すること(自力で努力するという意味ではない)」「環境の調整」「周囲の理解や支えを得ること」が状態改善のためには絶対に欠かせない3つの要素だと思っています。
私から見たら…患者とまともに話をしようとせず、すぐに投薬に頼る医者の方がヤブに思えてなりません。