「たとえ外国人には奇異に見えようとも、
生きている都市には固有の伝統が存在する。
それを無視して都市を切り売りすることはできない。
(中略)これがわれわれの街なのだ。
(中略)これがわれわれの伝統であり、われわれの街なのだ。
われわれは長い間共産主義者の独裁のもとで生きてきたが、
実業家の独裁のもとで暮らすようになっても
生活はいっこうに良くならない。
彼らは自分たちがいる国のことなど
まったく気にしていないのだ」
グレゴリー・ゴーリン
「真理を広めなければならない。経済学の法則は工学の法則と同じである。
ある一連の法則があらゆるところに当てはまるのだ」
ローレンス・サマーズ
ハーバード大学は、ロシアの民営化と
投資信託市場の準備を任されていた。
そのロシア・プロジェクトを率いていた同大学経済学部教授
アンドレイ・シュレイファーと助手のジョナサン・ヘイ
創設に取り組んでいた市場から
2人が直接、利益を得ていることが明らかとなった。
シュレイファーが民営化政策に関するガイダルのチームの
主任顧問を務めていたとき、彼の妻は民営化された
ロシア企業に多額の投資をしていた。
ヘイは、民営化されたロシアの石油株に個人的に投資、
ハーバードとUSAIDとの契約に直接違反していたといわれる。
また新たな投資信託市場の創設でロシア政府に協力している間、
恋人(のちの妻)が設立した投資会社がロシアで許可第一号となり、
創業時には米政府の資金を得て設立された
ハーバードの事務所で管理業務を行っていた。
こうしたことが明るみに出て米司法省は、
シュレイファーとヘイの商取引が契約違反だとハーバード大学を訴える。
7年経過後、ボストン地裁はハーバードが契約に違反、2人の研究者が
「共謀して米国に詐欺行為を働き」
「シュレイファーは明らかな自己取引に関与」
「ヘイは父親と恋人を通じて40万ドルの資金浄化を図った」と判決を下す。
ハーバード大学は、設立以来最高額となる2650万ドルの和解金を支払い、
シュレイファーは200万ドル、ヘイは100~200万ドルの支払いに同意
だた法的責任は認めなかった。
このお金はロシアではなく、米政府に支払われた。
U.S.District Court ,District of Massachusetts ,"United States of America,
Plaintiff, v.President and Fellows of Harvard College,Andrei Shleifer and
Jonathan Hay,Defendants;Civil Action No.00-11977-DPW,"
Memorandum and Order ,June 28,2004
https://casetext.com/case/us-v-president-and-fellows-of-harvard-college-2
McClintick ,"How Harvard Lost Russia."

ショック療法によって、ロシアには短期で移動する投機や
為替取引の資金が流れ込み、1998年、無防備だったロシア経済は崩壊する。
国民はエリツィンを非難し、支持率は6%に落ち込む。
1999年12月31日プーチンへと政権交代
エリツィンは刑事免責特権を要求、汚職であれ、
民主化運動の活動家の殺害であれ、刑事訴追を受けないことになった。
エリツィンは、経済的ショック療法の「付随的損害」
つまり、ゆっくりとした大量虐殺を行った、新自由主義革命という大義で。
大飢饉や天災、戦闘もなく、これほどの短期間に
これほど多くの人がこれほどのものを失ったことはなかった。
1998年には、ロシアの農場の8割以上が破産、
およそ7万の国営工場が閉鎖、大量の失業者が発生した。
1989年、約200万人が1日当たりの
生活費4ドル未満の貧困状態にあった。
ショック療法が施された90年代半ば、
貧困ラインを下回る生活を送る人は、7400万人にも上った。
ロシアで行われた新自由主義改革によって、
たった8年間で7200万人が、貧困に追いやられたことになる。
1996年、ロシア人の25%、約3700万人が
貧困の中でも「極貧」とされるレベルの生活を送っていた。
Sabrina Tavernise ,"Farms as Business in Russia,"
New York Times ,November 6,2001
Josefsson ,"The Art of Ruining a Country with a Little Professional Help
from Sweden"
"News Conference by James Wolfensohn ,President of the World Bank Re :
IMF Spring Meeting ,"Washington DC.April 22,1999,www.imf.org
Branko Milanovic ,Income ,Inequality and Poverty during the Transition
from Planned to Market Economy (Washington ,DC: World Bank ,1998),68
https://documents1.worldbank.org/curated/en/229251468767984676/pdf/multi-page.pdf
Working Center for Economic Reform, Government of the Russian Federation,
Russian Economic Trends 5,no 1(1996):56-57,cited in Bertram Silverman
and Murray Yanowitch ,New Rich ,New Poor ,New Russia :
Winners and Losers on the Russian Road to Capitalism
(Armonk ,Ny:M.E.Sharpe,2000),47.

共産主義時代には、少なくとも住む場所はあった。
暖房のないアパートに一家がすし詰めで暮らすという悲惨な状況だったが。
2006年、ロシア政府はホームレスの子どもが71万5000人と発表
ユニセフの推定では、350万人にも達する可能性があるという。
"Russia Has More Than 175,000 Homeless Children -Health Minister ,"
RIA Novosti news agency ,February 23,2006
https://www.upi.com/Top_News/2006/02/23/Russia-has-715000-homeless-children/58431140687692/
Carel De Rooy ,UNICEF ,Childre in the Russian Federation ,Novemver 16,2004
page 5,www.unicef.org
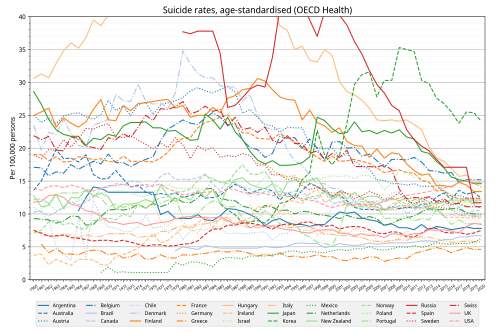

(P212~P224より抜粋)
スティグリッツ 1998年の危機
(略)やがて、ロシアは通貨の切り下げを余儀なくされた。
(略)過大評価された交換レートは、IMFがロシアに押しつけた
その他のマクロ経済政策の影響もあり、経済を破綻させ、
公式の失業率は下がったものの、
統計にあらわれない失業者の数は膨大なものとなった。
多くの企業経営者は、しかるべきセーフティ・ネットがないため、
労働者の解雇をためらった。
失業の実態は隠されていたが、状況はまさに深刻だった。
労働者は働くふりをする一方で、
企業経営者は給与を支払うふりをするだけだったからだ。
これらの労働者にとって、また国家全体にとって、過大評価された交換レートは
諸悪の根源だったが、新興の実業家にとってまさに天の恵みだった。
ベンツ、シャネルのバッグ、イタリアの高級輸入食材を手に入れるには、
わずかなルーブルを支払うだけでよかったからだ。
資産を国外に退避させようとしていたオリガルヒにとっても、
過大評価された交換レートは天恵だった。
それは、手持ちのルーブルでさらにドルを買い入れ、その儲けを
外国の銀行口座にためこむことを可能にしたのである。
ロシア国民の大多数が辛酸をなめているにもかかわらず、
改革論者とIMFの顧問はさらなるハイパーインフレを
引き起こすのではないかと、
通貨の切り下げに二の足を踏んでいた。
そして交換レートのいかなる変更にも強く抵抗し、
変更を回避すべく、ロシアにたいし数十億ドルを投入した。
1998年5月、遅くとも6月には、交換レートを維持するためには
国外からロシアへの支援が必要なことは明らかだった。 通貨の信頼性は失われた。
(略)予想どおり、IMFは1998年7月に48億ドルの緊急財政援助を行った。
危機が起こる数週間前に、IMFは危機を誘引する政策を推しつけ、
実際に危機が起きると、さらに誤りをおかした。
(略)
IMFの官僚は自分たちが市場より頭が切れると思いこみ、
市場がうまく機能していないロシアの国債を積極的に買い入れた。
(略)
IMFは、借金を背負ったロシアが債務の支払い停止に追い込まれたことについて
責任の一端を負わなければならないのである。
貧困と不平等の拡大
(略)
1989年には、貧困層はロシアに暮らす人びとの2%だった。
1998年には、その数は23.8%にのぼり、
彼らの一日あたりの平均支出は2ドルだった。
世界銀行の調査によると、一日当たりの支出が4ドル未満の者は
国民の40%以上にのぼった。
また、子供のいる家庭の50%以上が
貧困層だというさらに深刻な問題があらわれた。
(略)
1人当たりの所得が年間4730ドルの国で起こる
ベンツの交通渋滞は、不健全さのあらわれでしかない。
(略)
移行によって貧困層の数が大幅に増え、ひと握りの者が
繁栄の頂点に立つ一方で、ロシアの中産階級は逼迫した。
インフレは中産階級のなけなしの貯蓄を消してしまった。
給与がインフレに追いつかず、実質的な所得は減った。
教育費や医療費を削減したことにより、
中産階級の生活水準はさらに低下した。
(略)
共産主義体制が暮らしを楽にすることはなかったが、
貧困を深刻化させることもなく、
教育、住居、医療、育児などのサービスを平等に提供するために
共通限度枠を設け、生活水準を比較的平等に保っていた。
(略)
現在のロシアは、半ば封建的な相続が基盤となっていたラテンアメリカなどと並んで
世界でも最悪の水準の不平等をかかえているのである。
ロシアは、考えうるかぎり最悪の状況におちいっている。
生産は極度に落ち込み、不平等もいっそう深刻化している。
そのうえ将来の展望もなく、深刻な不平等が成長を、
とくに社会と政治の安定につながる成長を阻害しているのだ。
こうやって振り返ってみると、言葉の選択に困る。
これはもはや戦争行為ではないか、と考え込んでしまう。
スティグリッツも批判はいいのだが、
自分たちが教えている、あるいは学んできた経済学が
根本的に間違っていて、人類を不幸にすることに想いを馳せないのだろうか。

(P330~P335より抜粋・要約・脚色)
視点は、リンドより。



