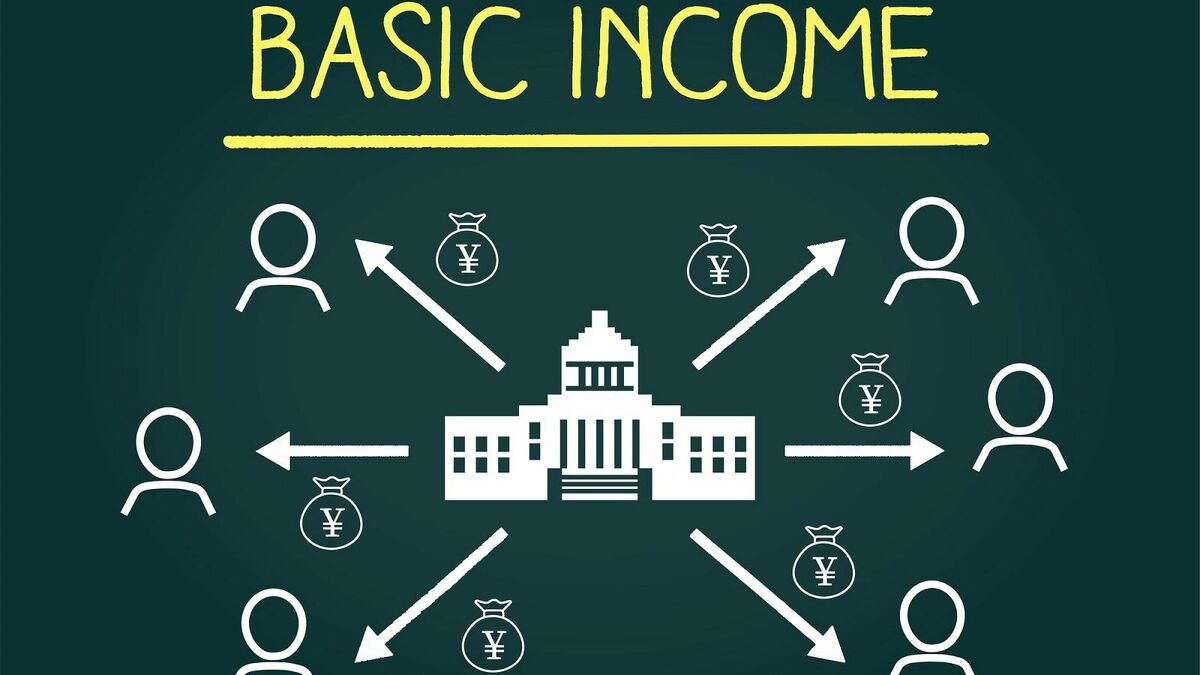アベノミクスの見直しから官僚人事まで、ことごとくぶつかり合う岸田文雄・首相と安倍晋三・元首相。だが、この2人が唯一、歩調を合わせられる政策があった。年金の支給額引き下げである。2人は、自民党政権がついてきた「100年安心」という国民への嘘を隠蔽し続けなければならない“共犯者”なのである。
年金改革は政治家の嘘の歴史といってもいい。最大の嘘は「年金100年安心」という言葉だろう。覚えている人は多いはずだ。小泉純一郎政権が年金制度の大改革(2004年)を行なった際、当時の坂口力・厚労相が掲げた標語だ。
小泉年金改革では年金財政を維持するために保険料の大幅値上げなどが決まった。それに対する国民の不満が高まると、政府与党は「これで年金制度は100年安心」と説明し、現在も自公政権は「100年安心」を掲げ続けている。
このとき導入されたのが、年金減額の第一の仕組みである悪名高い「マクロ経済スライド」だ。年金制度の変遷に詳しい「年金博士」こと社会保険労務士の北村庄吾氏が語る。
「いきなり年金支給額を減らすと言えば政府はたいへんな批判を受ける。そこで物価スライドの仕組みを巧妙に変えた。本来なら物価が上昇したときは、年金も同じ上昇率で引き上げなければならない。
だが、『年金の支え手である現役世代の賃金の変化や少子化、年金受給者の平均余命の延びなどマクロ経済の変化に合わせる』という建前で物価上昇率より0.9%差し引いて年金を上げることにした。これなら物価上昇時にも少しだけ年金額が増えるので、国民には目減りしていることがわかりにくい。長期にわたって年金支払いを減らしていく巧妙な仕組みです」
炊き出しのオニギリにたとえるとわかりやすい。政府が炊き出しでお年寄りにオニギリを配っていた。だが、このままではお釜のごはんが足りなくなりそうだと考えて、途中からオニギリをどんどん小さくしていくことにした。いずれひと口大のとても小さなオニギリになるかもしれないが、「これなら100年間配り続けられる」というわけだ。
だが、国民から“将来、オニギリがご飯1粒になるんじゃないか”との不安の声が上がると、当時の小泉首相は“いやいやそんなことはありません”とばかりに、「厚生年金は将来にわたって現役世代の所得の50%より下がらないことを保証します」と約束した。これが「所得代替率50%」と呼ばれて現在も厚生年金の最重要目標とされている。厚労省の直近の年金財政検証(2019年)では、現状の所得代替率は約61%と計算されている。
空想上の数字
北村氏が続ける。
「100年安心と聞かされた国民は、100年先まで年金で安心して生活できると受け止めた。しかし、本当の意味は、マクロ経済スライドで年金支給額を目減りさせていけば国の財政は100年持つということで、国民の老後の生活を保証したものではない。その証拠に、厚生年金受給者の多くは、すでに現役世代の所得の4割とか3割の年金しかもらっていない。
厚労省がシミュレーションしている所得代替率は、夫が40年間会社勤めをして、妻が40年間専業主婦をしていたというモデル世帯。そんな世帯がどれだけあるのか。
大卒サラリーマンの場合、途中で転職したりで加入期間35年ほどの人も多く、妻も基礎年金の加入期間40年に満たないケースが大半です。厚労省はいつまで現役世代の所得の50%を保証するという“空想上の数字”で国民を誤魔化そうとするのでしょうか」
実は、小泉政権の年金改革は完全に失敗だった。日本経済は長いデフレが続いたため、物価上昇時に年金の増額を抑える「年金目減り作戦」(マクロ経済スライド)が一度も発動できなかったからだ。国民に保険料値上げの痛みを強いても、年金財政の面では100年安心どころか、危機的状況は変わらなかった。
アベノミクスの見直しから官僚人事まで、ことごとくぶつかり合う岸田文雄・首相と安倍晋三・元首相。だが、この2人が唯一、歩調を合わせられる政策があった。年金の支給額引き下げである。容赦ない「年金減額」を実践したのが安倍晋三・元首相だ。
8年間の長期政権でなんと年金を6.5%も引き下げたのである。第1次政権時代に「消えた年金」問題で煮え湯を飲まされた安倍氏は、政権に返り咲くとまず「年金特例水準」の解消に乗り出した。
これは自公政権が過去の物価下落時(2000~2002年)に「高齢者の生活に配慮する」と年金を引き下げずに据え置いたことで、受給額が本来の年金額より高くなっていたことだ。とはいえ、当時すでに20年近くが経ち、年金生活者にとって特例水準の年金額が生活の基準となっていた。
安倍政権はこれを、「もらいすぎ年金」と批判キャンペーンを張り、高支持率を背景に13年から3年間で2.5%減らした。それが終わると、2015年にはマクロ経済スライドを初めて発動した。
そして2016年に「年金減額法」を成立させ、物価が上がっても賃金が下がれば年金を減らす新たな年金減額の仕組みをつくった。
矢継ぎ早の高齢者狙い撃ちだ。年金制度の変遷に詳しい「年金博士」こと社会保険労務士の北村庄吾氏が語る。
「それだけではありません。安倍年金改革では、キャリーオーバーという仕組みを導入した。物価上昇率がマクロ経済スライドの0.9%より低かったり、物価が下がってスライド(減額)が発動できない場合、マイナス分を翌年以降に繰り越して、次に物価が上昇したときに一気に適用して年金を目減りさせる仕組みです。この導入で物価上昇と賃上げが同時に起きた場合も、年金アップが非常に難しくなった」
どこまでも年金は増やさないぞと網をかけたのだ。キャリーオーバー分を合わせると来年度のマクロ経済スライドは1.2%マイナスになる見込みだ。物価上昇率と賃上げがそれ以上の水準にならなければ、物価が上がっても年金は全く増えない。
それだけ年金生活者を苦しめても、年金の破綻はいまや明らかだ。国民に「100年安心」の嘘をはっきり突きつけたのは、「老後は年金の他に2000万円が必要」と指摘した2019年の金融庁審議会の報告書だった。国民の年金不安が高まると、安倍首相は報告書を撤回させてこう嘯いたのである。
「マクロ経済スライドも発動されましたから、いわば『100年安心』ということはですね、確保された」
どこまでも安心の嘘を押し通す姿勢で、それは岸田首相も踏襲しているようだ。
「6月支給分から、年金が前年より0.4%減となりました。夫が一般的な収入のサラリーマンとして40年働き、妻が専業主婦という“モデル世帯”が受給する年金は、月額22万496円から219593円へと、903円も引き下がりました。年間では10836円ものマイナスです。しかも、急激な物価上昇により、年金は額面以上に“減っている”状態です」
こう語るのは、年金博士こと、社会保険労務士の北村庄吾さんだ。そもそも、物価が高騰するなか、なぜ年金が減額されたのだろうか。
「少子高齢化で現役世代の人口は減っているのに、寿命が延びたことで年金受給者は増えていきます。現役世代の負担を軽減するため、2016年の年金改定で、現役世代の賃金が下がれば、その分、年金受給額も下げるというルールになったのです」
コロナ禍による景気の落ち込みなどで、過去3年の賃金変動率などが0.4%減ってしまったことで、年金額も同じように減額されてしまったのだ。
■年金額は2割減に…生活の見直しが必須
年金の減額はさらに続くと、前出の北村さんは分析する。
「年金の条文の中でも、将来的に所得代替率が50%になることに触れられています。所得代替率とは、現役男子の手取りに対する年金受給額の割合のことです」
現在、モデル世帯といわれる男子の平均給与は357000円で、所得代替率は61.7%になっている。
「これが50%となれば、年金の受給額は178500円に。現行よりも約2割も減る計算です」
つまり、物価が下落する見込みはなく、年金額は下がり続けていく。
「主食を小麦製品から価格の上昇していない米に切り替えるなど、生活のあり方の根本的な見直しが必要です」(生活経済ジャーナリストの柏木理佳さん)
厳しい老後が待っていそうだ。
竹中流ベーシックインカムはどこが問題なのか
だまされるな、本質は新種の「リバース年金」だ
竹中提案に問題はないのか。そんなことはない。その第1は、彼の提案がそもそもベーシックインカムにすらなっていないところにある。
もう一度、彼の発言を伝える記事を読んでみよう。彼は、自身の提案をベーシックインカムだと言いながら、他方で「所得が一定以上の人には後で返してもらう」と付け加えている。しかし、いったん給付しながら後で返してもらうというのでは、政府による生活資金貸付と同じことだ。単純な貸付と違うのは「所得が一定以上の人には」という条件が付いていることだが、そんな条件を付けても、彼の提案がベーシックインカムになっていないことに変わりはない。
住宅資金を借りて後で返済する住宅ローン(モーゲージ)の順番を逆にして、住宅を担保に生活資金を借りて後で住宅を売って返済するローン商品を、「リバースモーゲージ」と呼ぶ。その用語法を借りれば、竹中提案は要するに「リバース年金保険」であって、ベーシックインカムなどではないことになる。彼の提案の本質は、ベーシックインカムつまり全国民対象の無償現金給付ではなく、全国民を網に掛ける強制的国営金融プランの一種なのである。
竹中氏へのインタビュー記事には生活保護と年金をまとめて縮小あるいは廃止して財源とすることを考えているような節がある。だが、これまた気になる点である。生活保護をベーシックインカムに吸収するという話なら聞いたことがあるが、年金保険をベーシックインカムに吸収などというのはありえない筋と言うほかはない。
厚生年金であれ国民年金であれ、そこに積み立てられている資産は年金制度に参加していた人々が過去に積み立てた汗の結晶であり、国家が人々に贈与を行うための準備資産などではない。生活保護と年金は別のものなのだ。それを混同して「年金を今まで積み立てた人はどうなるのかという問題が残るが、後で考えればいい」などと片付けてしまっては、日本という「国のかたち」が変わってしまう。
↓社会保障に関する各党の公約。