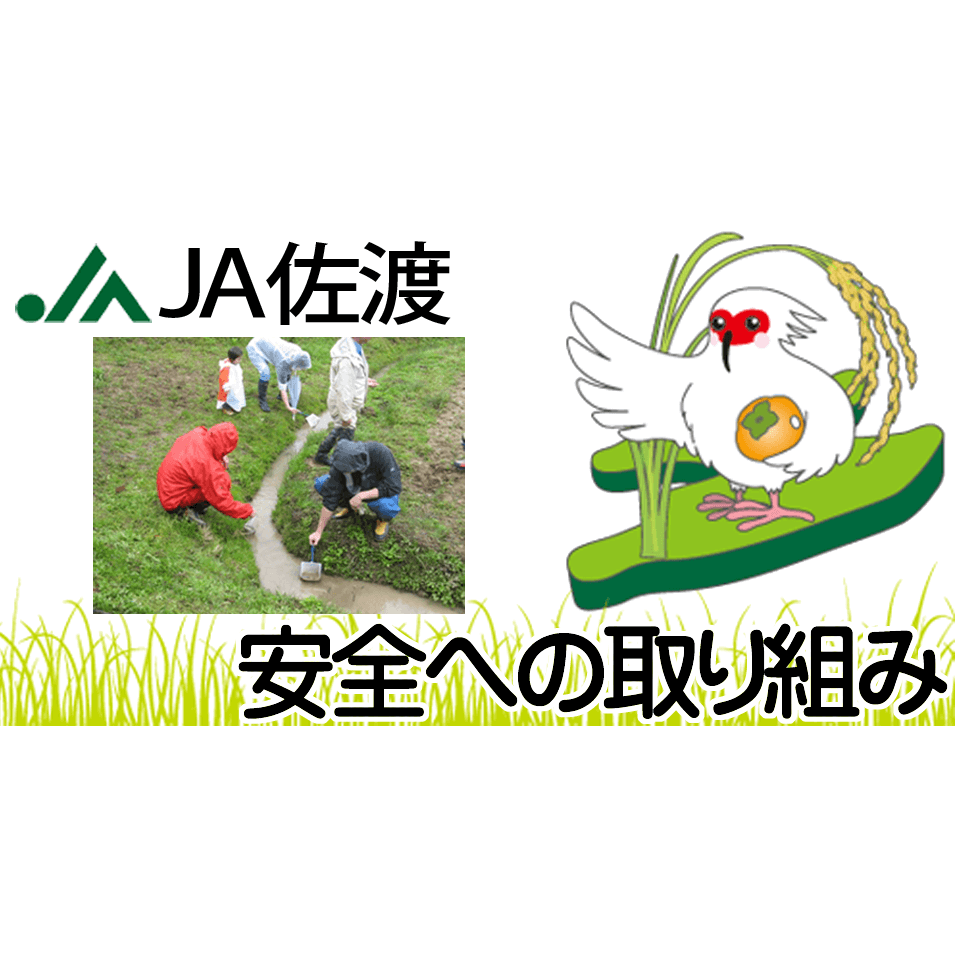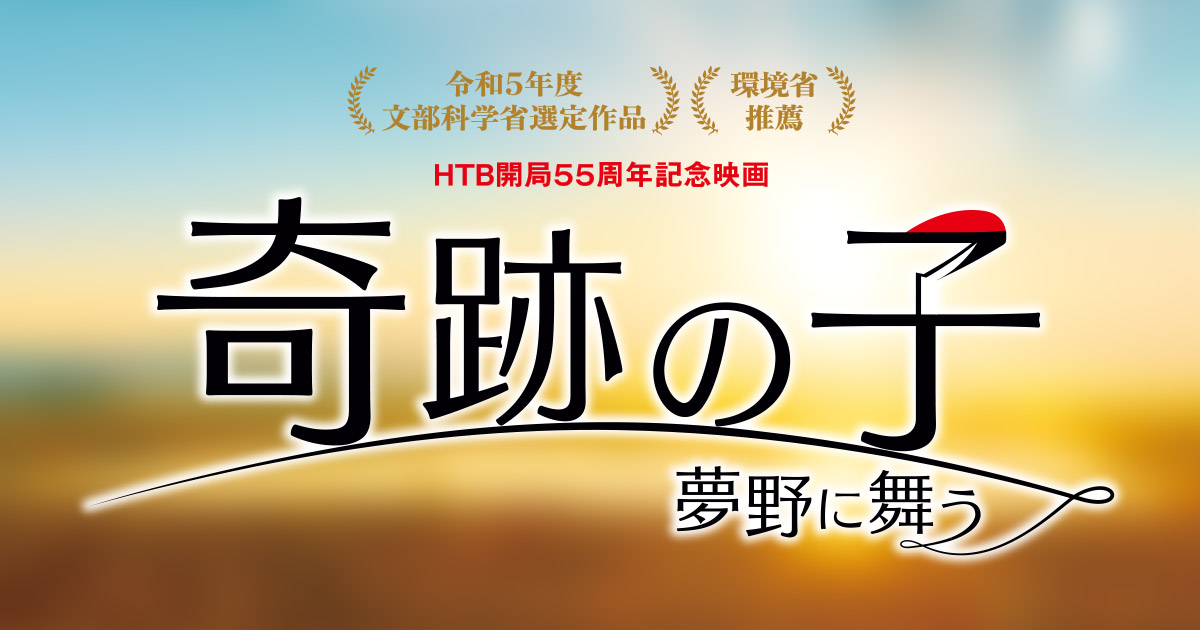久しぶりに映画館で映画を観てきました。
オオタヴィン監督の「夢みる給食」。
大きな映画館(シネコン)ではやってないんですよね。
戦後、人間中心の利便性を追求してきた社会に、
副作用として低体温やアレルギーで苦しむ子どもが増えたり
それまで人間と一緒に生きていた生き物たちがいなくなったり。
そういう歪(ひずみ)が目に見えて現れてきて、
じゃあどうする?となった時、
「子どもたち」や「生き物」の命を大切にすることで、
新たな道筋が見えてくる・・・・。
その先鞭をつけてくれるのが、
この映画に出てくる「夢みる」大人たちです。
先端医療の立場から「栄養学の重要性」を語るお医者さん達。
ネオニコチノイド農薬を扱わないことで、一度は絶滅したと思われていた朱鷺(トキ)を再び蘇らせた新潟県佐渡市の農協の決断。
市長さんや公務員さんが先導して農薬を使わなくなったとたん、まるで物語のようにコウノトリが戻ってきた田んぼ。
給食センターでの調理が難しいと思われていた、形のバラバラな有機作物を現場で実際に給食に使っている栄養士さん。
アレルギーの子どものために、ひとりで無農薬の野菜を作り始めたお母さん。
「私はこれをみんなに伝えたい!」
と天に向かって叫んだ数日後、とある雑誌から取材依頼が来て大きな反響を呼び、夢が叶ったそうです。すごい。
その他にも、夢みる大人たちがたくさん出てくる素敵な映画。
画像はここからお借りしました。
ほんとうに守るべきものがなんなのか、ちゃんとわかっていて
それを実践する人たちがこうやって社会を変えていくんですよね。
自分ができることをできるところでやっていく。
それが自然を蘇らせ、子どもたちを健やかにし、
今までとは違う新しい未来を形作っていく。
私はこういう生き方をしている人たちにとても惹かれます。
できたら私もなんらかの形で、その一翼を担っていけたらいいなと思っています。
この映画を作ったオオタヴィンさんは、
ご自分の個人スタジオ「まほろばスタジオ」で
企業や行政のバックを持たずに自由な作品を創られています。
まさにこれからの「水瓶座の時代」にふさわしく、
「ひとりひとりが微生物のように
情報交換して、手をとりあって、良い社会をつくる。」
(「夢みる給食」ナレーション担当の上野樹里さん)
そういうことを実践されている方。
もうひとつ気になる作品があって、
「奇跡の子 夢野に舞う」っていう、
明治期の乱獲などで姿を消してしまったタンチョウを再び町に呼び戻そうと、
夢に向かって奮闘する14人の農民たちのドキュメンタリー。
東京では公開初日に満員になり、関係者も驚いたのだとか。
この映画も、ぜひそのうち観てみたいものです。