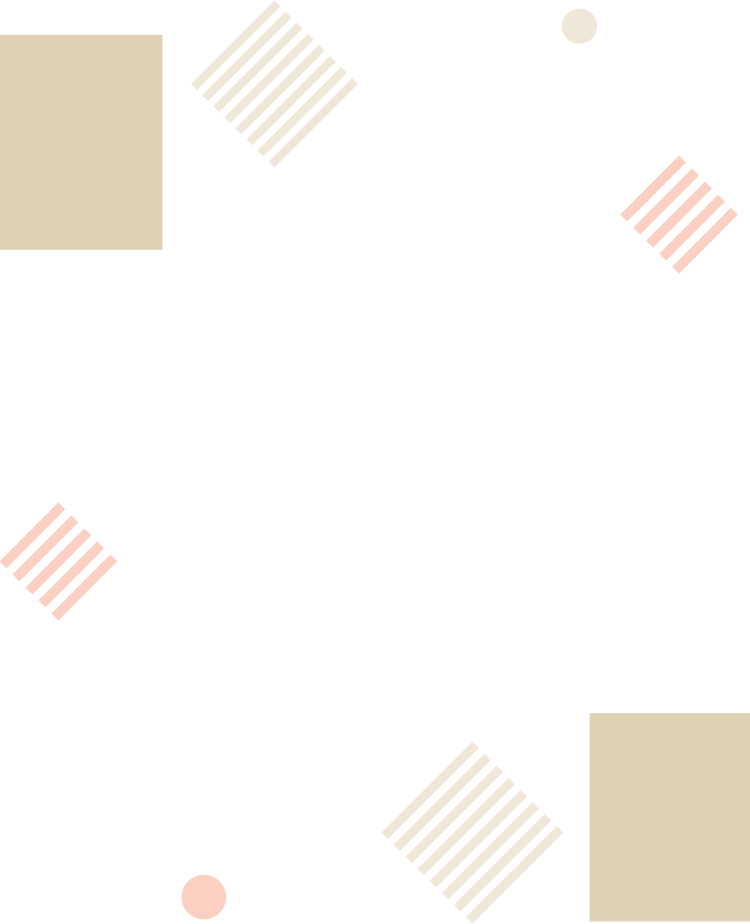ひとみはいつだって相原徹の笑顔が好きだった。少し乱れた髪を無造作にかき上げる仕草や、冗談を言っては目を細めて笑うあの表情。教室の窓際で菊地英治と笑い合う彼を見ているだけで、ひとみの胸は温かくなり、同時に小さく締め付けられるような痛みを覚えた。
でも、徹は友人の恋人だった。ひとみの親友、橋口純子の大切な人。純子が徹のことを話すたびに目を輝かせるのを見ると、ひとみは自分の気持ちを押し殺さずにはいられなかった。
「トオルくんってさ、昨日こんなこと言ってて笑っちゃったよ」と純子が無邪気に笑うたび、ひとみは「うん、そうなんだ」と相槌を打つだけで精一杯だった。
ある日、放課後の教室でひとみは徹と二人きりになった。純子が生徒会で遅れると言っていたから、少しだけ荷物を預かっておくつもりだった。徹は窓の外を見ながらつぶやく。
「中山ってさ、いつも落ち着いてるよな。なんか癒されるわ」
その言葉にひとみの心臓は跳ね上がった。顔が熱くなって、目を逸らすしかなかった。
「そんなことないよ」と小さく呟くのがやっとだった。
徹は軽く笑って、「いや、本当だよ。純子といるときもさ、ひとみがいるとホッとする」と続けた。その一言が、ひとみの心に鋭い針のように刺さった。徹にとって自分は「安心できる存在」でしかない。恋でも愛でもなく、ただの背景の一部だ。
その夜、ひとみはベッドに横になりながら涙をこらえた。相原徹が好きだ。ずっと前から好きだった。でも、純子の幸せそうな顔を思い出すたび、その想いは喉の奥に詰まって出てこなかった。徹と純子が並んで歩く姿を遠くから見つめるたび、ひとみは自分に言い聞かせた。
「あたしは我慢すればいい。友だちを傷つけるなんてできない」と。
それでも、時折ひとみは思う。もしあのとき、勇気を出して気持ちを伝えていたら。もし純子が徹と出会う前に、自分の想いを形にしていたら。徹の笑顔が自分だけに向けられる瞬間を、ひとみは夢の中でだけ許した。